▼探す
▼情報収集する&学ぶ
- 人事ポータルサイト【HRpro】
- 連載・対談
- 連載・コラム一覧
- 雇用管理・賃金
雇用管理・賃金の連載・コラム一覧
| フリーワード | 指定なし |
|---|---|
| ジャンル |
雇用管理・賃金
|
-
 社長の年金
社長の年金第3回:個人オーナーの年金はどうすれば増えるのか(1)
個人オーナーの老後の年金は、どうすればもっと増やすことができるのだろうか。これまで当シリーズでは、国民年金、厚生年金といった2つの制度、また、個人オーナーと法人の代表取締役の違い、といった観点から「社...
2018/11/16
雇用管理・賃金 -
 特別読み切り
特別読み切りデスク回りから残業削減
最近の社会的趨勢か、長時間労働対策に対するお悩みを受けることが多くなった。長時間労働対策は企業全体で取り組むべきものだが、これを推進するにあたり、必要な業務の整理の段階で、足踏みする企業が多いのではな...
2018/10/31
雇用管理・賃金 -
 社長の年金
社長の年金第2回:社長は“いくら”年金をもらうのか
『第1回 社長はどんな年金をもらうのか』(平成30年7月9日付)では、個人オーナーは、国民年金という“1つの制度”から年金を受け取り、法人の代表取締役は、国民年金と厚生年金保険の“2つの制度”から年金...
2018/10/10
雇用管理・賃金 -
 特別読み切り
特別読み切りBlack or White?
「働き方改革法」が成立した。今後、「ブラック企業」or「ホワイト企業」という言葉に、企業も従業員も、より一層、敏感になる時代になると思われる。法令遵守は当然のこととして、今、必要以上に「ブラック企業」...
2018/08/03
雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -
 社長の年金
社長の年金第1回:社長はどんな年金をもらうのか
「将来、自分はどんな年金を受け取ることになるのか」。企業・組織のリーダーを務める立場であれば、しっかりと理解しておきたいものである。しかしながら、日本の年金制度は極めて複雑で、難解である。果たしてリー...
2018/07/09
雇用管理・賃金 -
 働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~
働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~最終回 インセンティブ導入のポイント(その2)
前回は、営業職の目標設定について述べたが、営業職以外にインセンティブを適用できる職種は存在するのだろうか?答えはYes。但し、目標を定量的に設定できることが条件となる。 例えば、サービスマンや技術職な...
2018/07/06
雇用管理・賃金 -
 企業にはびこる名ばかり産業医
企業にはびこる名ばかり産業医第3回 社員の健康度UPは、一人あたり30万円の損失削減に繋がる
ここまで読んできて、「健康経営は確かに理想だけど、やっぱりお金も人も余裕のある大企業のやることだ」と思った人もいるかもしれません。「うちは日々の業務で手いっぱいで、とてもそこまでする余裕はない」と。確...
2018/07/03
雇用管理・賃金 福利厚生・安全衛生 -
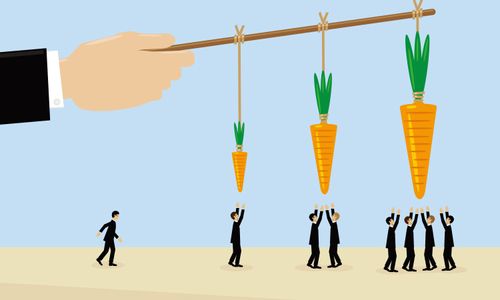 働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~
働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~第5回 インセンティブ導入のポイント(その1)
前回は、改めて裁量労働制の意義を問うと同時に、その導入や賞与の調整などで、インセンティブの原資を確保する方法を会社側の視点で記述した。無論、会社側の視点だけでインセンティブを導入しても、それで社員の満...
2018/05/11
雇用管理・賃金 -
 働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~
働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~第4回 働き方改革の切り札とは?
3月1日の日本経済新聞・朝刊で、働き方改革関連法案から裁量労働制の対象拡大部分を削除することが報じられた。具体的には、課題解決型提案営業と裁量的にPDCAを回す業務に従事する労働者を裁量労働制の対象に...
2018/04/11
雇用管理・賃金 -
 働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~
働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~第3回 裁量労働制の現状
去る1月29日の衆議院予算委員会で、「裁量労働制で働く人の労働時間は平均的な人で比べれば一般労働者よりも短いデータもある」と安倍総理が答弁したことから、野党の反発を買った「働き方改革関連法案」。2月1...
2018/02/27
雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -
 働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~
働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~第2回 かつての成果主義は何故絶滅したか?
日本企業には、年功序列型人事評価が深く根付いており、個人の業績をあまり重んじる文化にない。これは戦後の高度成長期を支えた昭和一桁の世代や、バブルの中核を担った 団塊世代の方々が深い愛社精神をもって会社...
2018/01/30
雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -
 働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~
働き方改革 実現への切り札とは? ~インセンティブ制度がもたらす企業と社員のWin-Winの関係~第1回 働き方改革関連法案いよいよ可決か?
第二次安倍政権下において第一回「産業競争力会議」が開催されてから早5年が経とうとしている。その間、「未来投資会議」、「働き方改革実現会議」に場を移して議論されてきた労働規制緩和、いわゆる「働き方改革関...
2018/01/30
雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -
 グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ
グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ外国籍の方のアルバイト雇用編
今回は、外国籍の方をアルバイトで雇用する際の留意点についてご紹介します。外国籍の方をアルバイト雇用する理由の一つとして、社員雇用などで勤務させたくても就労VISAが取得できないことが挙げられます。原因...
2016/12/08
雇用管理・賃金 オフィスサービス -
 グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ
グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ外国籍の方の中途採用編
今回は、既に就労可能なVISAを持っていて日本国内の他の法人で勤務している方を正社員等フルタイムで中途採用する際の注意点についてご案内します。既に就労可能なVISAを持っている点で前回紹介した外国人留...
2016/11/01
キャリア採用 雇用管理・賃金 -
 グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ
グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ外国人留学生新卒採用編
今回は、日本の大学院・大学・専門学校に在学中の外国人留学生を新卒採用する際のVISA申請の留意点についてご紹介します。留学生新卒採用を検討中の企業に皆様のみならず、既に留学生採用のご経験のある企業の皆...
2016/10/12
新卒採用 雇用管理・賃金 -
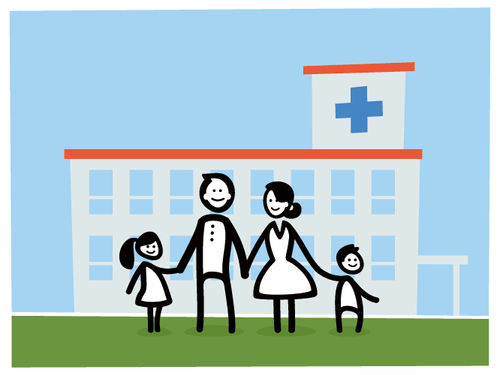 経営者として知っておくべき労働法
経営者として知っておくべき労働法労働保険、社会保険の仕組み(社会保険編)
健康保険は、労働者とその被扶養者の業務外の傷病のほか、死亡、出産に関する保険給付を行う制度です。原則として、全ての法人事業所、5人以上の従業員を使用する個人事業所は、健康保険の適用事業所という扱いとな...
2016/10/07
雇用管理・賃金 -
 グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ
グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ海外からの出向者編 Vol.3
前回は、出向者の方が取得する主だった就労ビザとして、企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)と技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)について紹介しました。
2016/09/12
採用全般 雇用管理・賃金 -
 経営者として知っておくべき労働法
経営者として知っておくべき労働法労働保険、社会保険の仕組み(労働保険編)
労働保険と一言でいいますが、中身は、労災保険と雇用保険のふたつがあります。いずれも法律で定めた要件を満たしている場合は、強制加入・強制適用となります。
2016/09/08
雇用管理・賃金 -
 経営者として知っておくべき労働法
経営者として知っておくべき労働法労働時間、休日、休暇
使用者は、労働者に休憩時間を除き、1日8時間・1週間に40時間を超えて労働させることはできないと、労働基準法32条で定められています。これを法律が定める労働時間であることから法定労働時間といいます。
2016/08/18
雇用管理・賃金 -
 経営者として知っておくべき労働法
経営者として知っておくべき労働法賃金と処遇との関係
労働基準法は、「賃金」を「労働の対償」として「使用者が支払うもの」としています(労働基準法11条)。賃金、給与、謝礼、寸志などの名称は一切関係ないのです。「労働の対償」とは具体的な労働への対価という意...
2016/08/05
雇用管理・賃金





