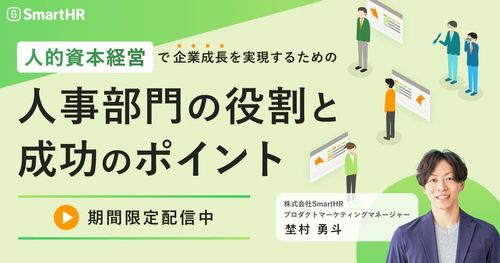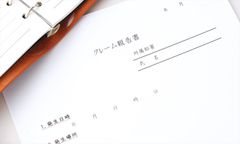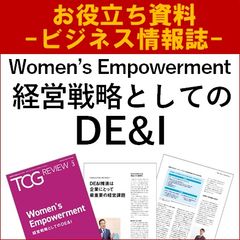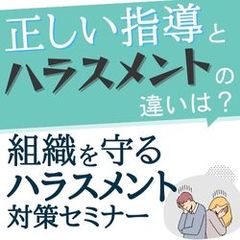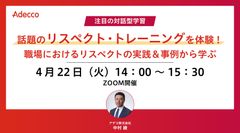「採用」と「組織風土」はつながっている
まずは採用における面接の場面を想定します。求職者のストレス耐性などを確認するために、面接官が威圧的な態度をとったとします。いわゆる、圧迫面接です。そうした質問をするのは、「威圧的な態度をとることも、時には必要だ」という企業の考えが根底にあるのかもしれません。例えば、「仕事がうまくいかない部下に、上司が威圧的な態度をとることで改善できる」と考える場合です。
また、面接官が「普段お酒を飲むか」を質問したとします。場を和ますために聞いたかもしれませんが、その裏側には「勤務時間外も大事にする」という企業の考えが根底にあるのかもしれません。例えば、「部下が飲み会の場面で、気の利いた対応をすることで、職場の人間関係を円滑にできる」と考える場合です。
このように面接などの「採用」に関わる特性は、「組織風土」の特性につながっていることが考えられます。従業員はストレス耐性が強い方が良いかもれませんし、気の利いた対応ができた方が良いかもしれません。しかし、このような面接は、求職者側の「人権への配慮」が欠けているとも捉えられます。
採用は、求職者から「選ばれること」
多様なワークライフバランスが尊重されている中、就職先を選ぶ理由は、必ずしも給与額や終身雇用だけとはいえません。「働きやすさ」が重視されてきています。求職者が「働きやすさ」を重視すれば、上司に威圧的な態度は求めないでしょうし、気の効いた対応で自らが疲れてしまうことも求めないでしょう。そして何より、人権尊重・コンプライアンスが重視されている昨今において、このような面接は“従業員を見下す組織風土”と捉えられるおそれもあり、「この企業は、安定的な経営ができるのか」と疑念を抱かれる要因ともなりかねません。
つまり、企業が採用を「求職者を選ぶこと」と捉えている限り、求職者から「選ばれること」は難しいということです。
厚労省資料より「公正な選考採用を行うポイント」を考える
厚生労働省では「公正採用選考特設サイト 公正な採用選考を目指して」というサイトを開設しています。そのサイト内のリーフレットの中で、公正な採用選考を行うポイントとして、以下の2つを掲げています。自社の採用が、2つのポイントに従ったものとなっているかを確認していきましょう。※厚生労働省「公正採用選考特設サイト 公正な採用選考を目指して」サイト内『事業主の方へのリーフレット』より
1.応募者に広く門戸を開く
出自、障害、難病の有無及び性的マイノリティなど特定の人を排除せず、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにしましょう。
なお、法律上、事業主は労働者の募集及び採用について、
●性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません(男女雇用機会均等法第5条)
●障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません(障害者雇用促進法第34条)
●原則として年齢制限を設けることはできません(労働施策総合推進法第9条)
2.本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とする
応募してきた人が「求人職種の職務を遂行するにあたり、必要となる適性や能力をもっているか」ということに基づいた基準による採用選考を行いましょう。
職務内容によって、適性・能力を判断するのにどのような事項が適当であるかは異なりますが、「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)」はそもそも本人の適性・能力とは関係のないことです。
本人の適性・能力とは関係ないことを面接時にたずねることはもちろん、エントリーシートに記載させたり、作文の題材としたりすることは、就職差別につながりかねません。十分に気を付けましょう。
企業の「人権方針」を拠り所とした採用を
人権の配慮へ欠けた採用選考となる要因として、組織風土に影響された“場当たり的な対応”になっていることが考えられます。また、育児休業やハラスメント防止などの規程が整備されていたとしても、役員・従業員一人ひとりが人権の配慮に欠けていたとしたら、その機能を果たすことができません。採用、育児休業、ハラスメントなどを縦割りに捉えることがないよう、それぞれを礎となる企業の「人権方針」に従ったものにしていきましょう。「人権方針」を策定していない場合は、ぜひ策定していきましょう。例えば、自社の特性をふまえ「外国人労働者の権利を大事にする」、「消費者の安全を大事にする」、「安全な労働環境を大事にする」、「従業員の社会保障を大事にする」、「こどもの権利を大事にする」など、特に何を大事にしていくかを掲げることです。
その人権方針を実現するために「採用はどうあるべきかを、ぶれずに考えていくこと」が公正な採用選考へとつながっていきます。
- 1