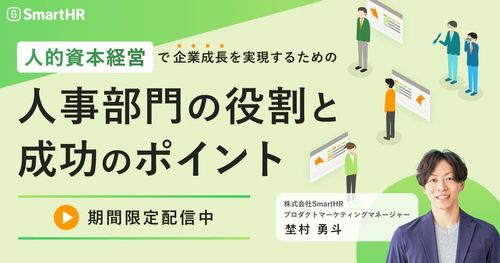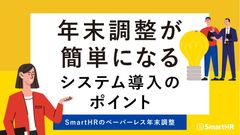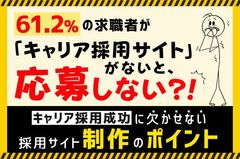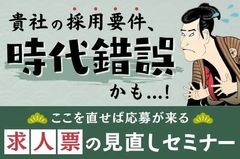離職票の直接交付のための3つの条件
会社が行う資格喪失手続の内容には変更がありませんが、直接交付のためには条件が3つあります。すべての条件を満たすと、自動で離職票の直接交付が行われます。(1)届け出たマイナンバーが雇用保険被保険者番号と紐づいていること
これまでハローワークにマイナンバーを届け出ていない場合等、マイナンバーと雇用保険被保険者番号の紐付けが行われていないと、離職票の直接送付ができません。例えば、マイナンバー制度の導入前に雇用保険の資格取得をした方は、そもそもマイナンバーの登録をしていない可能性が高いですし、資格取得時に前職の被保険者番号が未記載だった場合には正しく紐付けが行われていないことがあります。マイナンバーが雇用保険被保険者番号に紐付いているかの確認方法は2つあります。1つ目は、被保険者自身がマイナポータルの「わたしの情報」で確認する方法です。2つ目は、会社が被保険者全員の情報を確認する方法です。「雇用保険適用事業所情報請求書」をハローワークへ提出すると、会社の雇用保険被保険者のマイナンバー登録有無を確認することができます。一度情報を取得しておくと良いかもしれません。
マイナンバーが登録されていないときには、「個人番号登録・変更届」をハローワークへ提出することで登録可能です。
また、マイナンバーが前職の被保険者番号に紐づけられたままになっているケースもあります。このときは「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークへ提出します。登録手続きには2週間程度かかるとのことですので、離職直前の登録手続きでは間に合いません。余裕を持った登録手続きが必要です。資格喪失届にもマイナンバーの記載欄がありますが、前述のとおりマイナンバー登録には一定期間がかかるので、資格喪失届出にマイナンバーを記載しても、離職票発行までの間にマイナンバーと被保険者番号の紐付けが間に合わないと、直接交付の対象とはならない点も押さえておきましょう。
(2)離職者自身がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定をしていること
離職者自身がマイナポータルから設定をしていないと直接交付ができません。被保険者用のリーフレット(下記リンク参照)がありますので、案内してあげると良いでしょう。なお、マイナポータルでの連携設定は離職予定のない方でも設定が可能な上、一度連携設定をしていると、本人が設定解除をしなければ離職後に職場が変わってもずっと連携は有効のままです。
(3)会社が資格喪失手続きを電子申請で行っていること
会社の手続きの内容自体は変わりませんが、電子申請をしていることが直接交付の条件です。なお、直接交付を希望する離職者から電子申請の要望があった場合、必ず会社が応じなければならないわけではありません。ただし、会社にとってのメリットも少なくないので、これを機に電子申請を始めるのも良いでしょう。電子申請の開始には電子証明書等必要なものがありますので、電子申請を始める会社は前もって準備しておきましょう。離職票の直接交付の注意点やポイント
直接交付対象の方の資格喪失手続きを行うと、手続き完了時に「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」とのメッセージが会社の電子申請システム上に届きます。このとき会社に届く公文書は「離職証明書(事業主控え)」のみです。離職票が届かないため、離職票に記載されている「離職区分コード」を会社が知ることはできません。個人情報に該当するとのことで、ハローワークへ問い合わせても教えてもらえない点は注意が必要です。
前述の3つの条件のうち1つでも満たしていない場合には、従来通り会社にすべての公文書が交付されるため、離職者用のものは会社を経由して送付します。あくまで希望者のみが利用できる制度ですので、直接交付を会社が強制することはできません。
しかし、直接交付できると会社の作業・郵送料等が削減できるメリットがあります。離職票だけでなく、資格喪失確認通知書をはじめとした資格喪失手続時に離職者用に発行されるすべての公文書が離職者に直接交付されますので、直接交付を推進したいと考える会社もあると思います。強制はできませんが、制度の案内や設定のためのリーフレットを社内周知することは問題ありません。
直接交付は利用のための条件があり、希望者しか利用できない制度ではあるものの、会社にとって利便性が上がる制度です。入退社が増える時期でもあり、離職者から直接交付について質問されることも十分考えられますので、今のうちに制度の確認と周知を進めておきましょう。
- 1