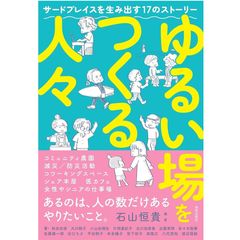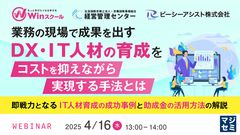拡充された「両立支援等助成金」の主な内容
拡充されたのは、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」と「育休中業務代替支援コース」です。1. 出生時両立支援コース
(1)第2種の申請要件緩和これまで、「出生時両立支援コース」第2種(育児休業取得率の上昇等による加算)の申請には、第1種(男性の育児休業取得による助成)の受給実績が必要でした。しかし今回の拡充により、第1種の受給実績がなくても第2種の申請が可能となりました。
この改定により、男性の育児休業取得を促進したいと考える中小企業にとって、助成金がより利用しやすくなりました。
(2)男性の育児休業取得率向上に対する新たな支援
企業が男性の育児休業取得率を30%以上向上させ、かつ50%以上の取得率を達成した場合、新たに60万円が支給されます。これにより、前年度の育休取得率が0%だった企業にも第2種受給の可能性が出てきたことになります。
2. 育休中等業務代替支援コース
(1)対象となる企業の拡大これまで、育休中等業務代替支援コースは、中小企業事業主のみが対象でしたが、「常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主」も対象となりました(手当支給への助成のみ、新規雇用は除く)。
(2)支給額の増額
育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給した場合、最大で一人当たり140万円が支給されることになりました。
なお、育休期間が1ヵ月以上でかつ社会保険労務士等の専門家に労務コンサルティングを依頼した場合には、業務体制整備経費助成が20万円にアップし、育休開始1ヵ月経過時点で先行して支給総額のうち最大30万円が支給されます。
同じく短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給した場合、最大で一人当たり128万円が支給されます。これにより体制整備を進めれば、離職防止や周辺労働者のモチベーションアップ、業務効率化などの効果が期待できます。
「両立支援等助成金」の申請時の注意点とは
「両立支援等助成金」を受給するためには、次の点に注意が必要です。1. 申請期限の厳守
助成金の各コースには、申請期限が定められています。例えば、「出生時両立支援コース」第2種の場合、取得率上昇等の支給要件を満たした事業年度の翌事業年度開始日から起算して6ヵ月以内に申請する必要があります。申請期限を過ぎると受理されないため、事前にスケジュールを確認し、適切に準備を進めましょう。なお、第2種の申請を行った事業主は第1種の申請をすることはできないので、申請の順序にもご注意ください。
2. 必要書類の準備
申請には、次のような書類が必要です。
●雇用契約書やタイムカード
●育児休業期間中の給与台帳 など
これらの書類は、不備がないように作成・保存してください。書類の整合性が確認できない場合、審査に時間がかかり、最悪の場合は不支給とされる可能性があります。
3. 中小企業の定義確認
助成金の一部コースは、中小企業事業主のみを対象としています。中小企業の定義(資本金や従業員数)を満たしているかどうかを確認しましょう。小売業では資本金が5千万円以下、または従業員数が50人以下の場合に中小企業として扱われます。4. 就業規則および育児介護休業規程の整備
助成金を申請するためには、育児休業や業務代替に関する規程が、就業規則および育児介護休業規程に適切に盛り込まれていることが求められます。規程が未整備の場合は、助成金の対象外となります。事前に内容を確認し、不足があれば整備することが必要です。「両立支援等助成金」を活用し、育児休業が取得しやすい企業を目指しましょう
今回の拡充により、企業が従業員の育児休業取得を支援しやすくなりました。育児休業取得率の向上は、従業員の仕事と育児の両立を支えるだけでなく、企業のイメージ向上や人材採用定着率の改善にもつながります。また、代替要員への手当の支給や業務体制整備を通じて、職場全体の業務効率の向上も期待できます。企業がこうした助成金を積極的に活用できるよう、サポートするのが社会保険労務士の役割です。ぜひお近くの社会保険労務士へ相談してみてください。
- 1