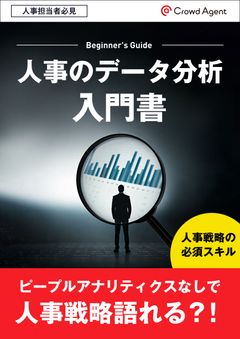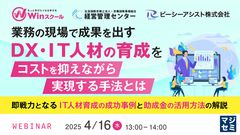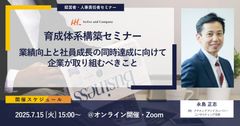「多様な働き方」を希望する社員のニーズに合わせた“複線型人事制度”とは
昨今の「多様な働き方をしたい」という社員のニーズを踏まえ、それを支援するため色々な“複線型の人事制度”を採用することが増えてきました。以下のように、「転居を伴う異動の可否」や「範囲の広さ」での分類、「職種別」での分類、「多様な正社員制度」によるもの等による“複線型人事制度”があります。(1)「総合職群」、「一般職群」
「総合職群」は転居を伴う異動を受け入れ、将来管理職を目指す職群。「一般職」は転居を伴わない異動のみ受け入れ、管理職を目指さない職群。(2)「グローバル勤務型」、「全国勤務型」、「エリア限定勤務型」、「地域限定型」
勤務地を以下のいずれかにする。全世界とする。全国とする。近畿地方東海地方というように、勤務地を「会社が決めたエリア内」とする。または転居を伴わない異動のみとする。(3)「ライン管理職群」、「専門職群」、「専任職群」
部下を統括する「ライン管理職群」、高度な専門能力を発揮する「専門職群」、技能的に優れた能力を発揮する「専任職群」に分ける。(4)職種別人事制度
「営業職」、「製造職」、「事務職」、「整備職」、「設計職」、「配送職」等、職種別に分ける。(5)多様な正社員制度
「勤務時間限定社員」、「職種限定社員」、「地域限定社員」など。主に、非正規社員を正社員に登用する際に活用する。「昇格制度」および「降格制度」とは
上位等級への昇格は、過去の人事考課ランクが一定以上の昇格候補者から、面接、試験等を経て会社が昇格者を決定します。逆に下位等級への降格については、挽回できる仕組みも必要です。
「職務分析」の必要性と進め方
等級制度の構築に際し、職務分析を実施することで、会社全体の業務内容を十分把握し、それに応じた「等級」、「人事考課制度」とすることができます。具体的には、前編の「等級基準書」の詳細説明、及び人事考課表の考課基準として活用します。職務分析のメリットは下記になります。
(2)求められるスキルや経験を明確にできるため、適切な人材の配置がしやすくなる
(3)職務内容が明確になることで、評価基準が客観的になる
しかしながら、デメリットもあります。
(2)業務内容が変化するたびに分析結果を見直す必要がある
(3)細かすぎると現場に馴染まない等、実務に即さない形式的な内容になると運用が難しくなる。
では、“会社業績の維持向上や人材育成に必要なレベルで職務を整理する方法”を説明します。このとき、簡易さと詳細さのバランスを取ることに留意します。
(1)仕事調べ(「営業職」、「技術職」、「総務職」等の職種ごと、かつ職位別)
個々の社員が毎日、毎週、毎月、毎四半期、毎年担っている仕事を「洗い出し表」にまとめます。(2)職務のまとめ
「洗い出し表」は作成者によって表現方法やレベルに差があるため、取りまとめる者が作成者にヒアリングしたり業務を観察したりして、業務内容や役割を一覧表にまとめます。そのうえで、必要なスキル、責任範囲を整理します。(3)職務と等級の整理表の作成
「主な業務(具体的なタスク)」、「責任範囲」、「難易度(等級レベル、必要なスキル・資格)」を一覧化します。その際、先に決めた「等級基準書」に基づき業務と等級を紐づけます。*
等級の決定に当たっては下記「(2)点数法」の方が客観性が高いとされますが、スコアリングの点数決定自体には感覚的な判断が残ります。どこまで時間を掛けても、完全に客観的で隙のないものはできません。むしろ、「(1)分類法」の方が、短時間で納得感のある等級決めができるでしょう。
(1)分類法
あらかじめ定めた等級基準に照らして、最も合致する定義の等級に当てはめる方法。評価が容易ですが、主観的判断になる可能性があります。(2)点数法
職務の複雑性や責任の重さ、職務の知識・技能、職務の対人関係の必要性、職務の判断力・決定力、職務の環境的・物理的要求等の観点で、スコアリングする。分析的で主観が入りにくいですが、作成に多大な時間を要します。*
次回は「賃金制度」について解説します。
- 1