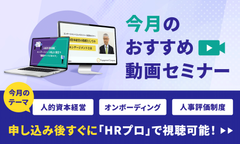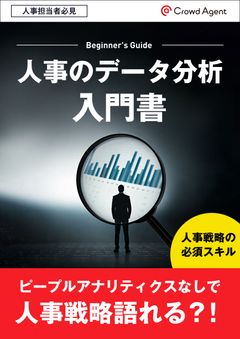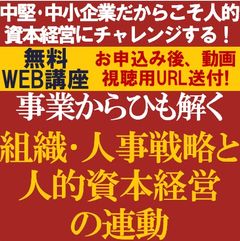プロフィール

萩原 佑一 氏
PayPay株式会社
コーポレート統括本部
HR本部 本部長
大手メーカーにて、グローバル人事(制度企画・HRBP)、グループ副社長直下組織等で国内外関係会社や事業の戦略立案・実行に従事後、2019年PayPayへ入社。HRとしてコロナ禍における事業と組織のレジリエンスを高める。WFA(Work From Anywhere at Anytime)の制度企画・導入も含めたHRMサイクルの全般やコンプライアンスに携わり、事業戦略に沿った中長期人員計画の立案、データドリブンでの組織コンサルティングによる組織と人のポテンシャル最大化も担う。また、ソフトバンクグループで生成AI事業検証を開始。2024年10月より現職。

三浦 孝文 氏
株式会社ノンピ
CHRO/取締役 人事本部長
NTTドコモと電通のつくったモバイル広告会社のD2C、レシピサービスのクックパッドで人事を経験後、2017年に当時のオイシックスに入社。大地を守る会、らでぃっしゅぼーや、シダックスとの経営統合プロセスを人材企画や経営企画の部長として経験。2024年2月からノンピへ出向し現職。
※ノンピの企業様向けケータリングサービス『EAZY CATERING』

なぜエンプロイーファーストではなく、「ユーザーファースト」でいたいか
三浦氏:まずは、貴社の経営課題からお聞かせいただけますか。萩原氏:今、私たちは、金融業界でNo.1プレイヤーを目指しています。決済サービスからスタートしましたが、カードにも事業を広げ、グループ全体のアセットを活かしてさらにシェアを獲得していこうと考えています。ソフトバンクグループの戦略として大事にしているのが、PayPayを通じたプラットフォームの確保。そこをトリガーとして、今後はカードや銀行などのサービスがPayPayを介して一気通貫でできるようになり、ユーザー体験の向上によって、企業価値を最大化していく。それをいかに実現させるかが、一番の経営課題です。
三浦氏:萩原様が人事として、経営課題にどのように向き合っているのか気になります。
萩原氏:2点あります。まず、1つはPayPay本体だけでなく、カードや銀行、証券など各会社のコアポジションに関するサクセッション・プランニングやアサインが重要だと思っています。2つ目は、グループ全体の生産性を上げにいかなければいけないということです。そのためにも、人事制度や規程を統一したり、同じ業務を中央に集約したり、シェアードサービス化していったり、PayPayイズムであるベンチャースピリットをグループ会社に浸透させていこうとしています。そうしたグループ内での活性化に人事として積極的に取り組んでいかなければなりません。
三浦氏:そのようななかで、人事として、経営戦略や事業戦略と人材戦略を連動させていく上でどのような点に気をつけているのでしょうか。
萩原氏:経営会議はもちろんですが、事業部の事業戦略ディスカッションや営業戦略会議にも人事が参加しています。私以外にも、HRBP部が事業部の会議に参加しているので、そこから事業ドリブンで人事を考えています。人事としては、事業部と連動する形で、一体化を意識しているところです。
なぜ、それをやるかと言うと、エンプロイーファーストではなく「ユーザーファースト」でいたいからです。どうしても、人事だけの会議で個別に人事テーマを論じると、「従業員の昇給、福利厚生、働き方の話が多くなりがちです。「ユーザーファースト」で、事業部と連動すれば、経営や事業に関する議論をせざるを得ません。
三浦氏:貴社の人事部門はどのような人員で構成されているのか、気になります。特徴などはありますか。
萩原氏:事業部のエースで人事のメンバーを固めているのは特徴的だと思います。例えば、営業系のエースだったメンバーもいますし、戦略系、エンジニア系のエースもいます。なので、何か会話をするとなると、「どうしたら売り上げを伸ばせるか」といった議論に人事内でなります。
もし、給与管理だけを10年、15年担当している人を採用したら、それを着実に実行するようなオペレーションに偏った組織になってしまうでしょう。人事のスペシャリストというよりかは、多様なバックグラウンドを持った人材を取り入れることで、例えば、給与管理一つにしても、新しいやり方を導入するかもしれませんし、もっと言えば「この業務は10個のうち7個は、事業目線では必要ないかもしれない」といった発想もできます。実は、自分が入社した2019年当時の人事メンバーは、今ではもうほとんどいません。それだけ事業成長との連動に向けて、人事内の人材も流動化しています。
三浦氏:かなり人事制度は特徴的にされていますね。
萩原氏:事業ステージに合わせて評価制度は、相対評価で行う仕組みに変えています。それに連動して処遇も付けているので、低い評価をもらうと処遇に影響が出ます。しかも、評価するにあたってはパフォーマンス(結果)しか見ません。正直、そこで低評価のフィードバックをすることで、「この会社ではもう無理だ」と諦めてしまう人もいます。ドライに見えるかもしれませんが、そうでないと事業変化にスピーディーに対応できる組織はつくれないと思っています。
本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。
続きは、下部よりログイン、または無料会員登録の上、ご覧ください!
この後、下記のトピックで、インタビューが続きます。
●人事部として「従業員満足度を上げるためにこんなことをやってみたい」と言わない
●PayPayは「厳しすぎだ」とよく言われていた
●ユーザーファーストを基に、何をしなければいけないかを考える必要がある