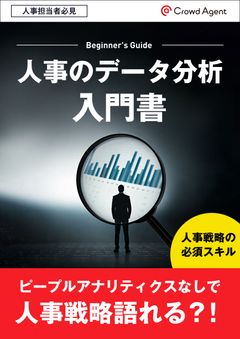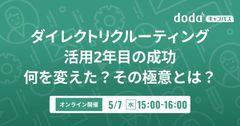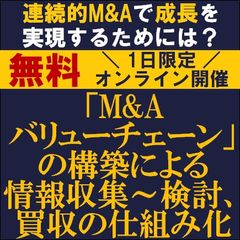そこで今回は、同社 経営管理本部 人事部長の江縁隆氏と、同社にアセスメントやトレーニングを提供する株式会社リードクリエイトの三原淳氏、巽遥介氏が対談。取り組みに至る背景や人づくりに対する想い、目指していくビジョンなどをお伺いしました。(以下敬称略)
【対談者プロフィール】

■江縁 隆氏
1993年に山善入社。管理本部 人事部 人事課からキャリアをスタートさせる。その後、財務経理部、内部監査部、国際管理部、安全保障貿易部での経験を経て、人事部長に就任。現在に至る。
株式会社山善
経営管理本部 人事部長

■三原 淳氏
大手通信会社、教育会社を経て2019年よりリードクリエイトに参画。2021年に西日本支社長に就任。西日本支社のマネジメントに従事する傍ら、講師として日々のマネジメントを通じて得た生きた学びを企業の管理職層を中心に提供する。
株式会社リードクリエイト
西日本支社長 兼 シニアコンサルタント

■巽 遥介氏
大学卒業後、大手総合リゾート運営会社に入社。2021年よりリードクリエイトに参画し、コンサルティング営業としてキャリアを重ねる。これまで100社以上のクライアントとの対話を通じて、人事制度改定(等級、評価、昇進昇格など)、社員育成施策(経営人財育成、リーダー人財育成など)の企画・実行支援を行っている。
株式会社リードクリエイト
ソリューション事業本部 西日本支社 プランナー

「切拓く経営」ができる人財を育てなければならない
三原 御社は今、「人づくりの経営の再起動」をメインミッションに掲げておられますが、まずは“起動”ではなく“再起動”とした意図や理由からお聞かせいただけないでしょうか。江縁 当社は戦後、創業者である山本猛夫が戦争から帰ってきて、裸一貫で立ち上げて、ここまで大きくした会社です。立ち上げ当初から、ずっと大事にしていたのが、いわゆる「切拓く経営」という考え方でした。山善はもともと機械工具商から始まり、現在は大きく5つの事業を展開し、さらに新たな事業も立ち上がろうとしていますが、何も持たない裸一貫のところから、ここまで会社を成長させるためには、変わり続ける社会や経済環境に合わせて、新しい価値を生み出し続けること、つまり、時代を切拓くことが不可欠だったのです。

三原 「切拓く経営」が実践できていたのは、同時に「人づくりの経営」も実践していたからだということですね。そもそもこの「人づくりの経営」とは、御社の中でどのように定義・言語化されているのでしょうか?
江縁 ひと言で言うと、「切拓く経営」ができる人財をつくること。これに尽きます。当社の経営理念は、「人づくりの経営」、「切拓く経営」、「信頼の経営」の3点ですが、この並び順にも意味があり、まず第一に重要であるのが「人づくりの経営」です。つまり「人づくりの経営」を実践するからこそ、当社の人財が世界中のお取引先様に喜んでいただけるような価値を切拓くことができ、それを継続することで、最終的には広く社会から信頼を得ることができるという、まさに価値創造ストーリーになっています。
では、「切拓く経営」ができる人財とは、具体的にどのような人を指すのか、ひと言で言うと、当社の“自業員”という言葉に結びつきます。当社では、従業員のことを自業員と呼称しています。一般に使われる従業員という言葉は、「生業に従う人」と書くため、会社からの指示に従う人、という意味合いで捉えることもできます。
しかし我々はそういう人財を必要とはしていません。自らも経営者であるという気概をもち、自ら生業を起こせる人こそ山善の求める人財であると考えています。山善が活躍する世界の各現場にはさまざまなニーズがあり、そのニーズに対して会社が逐一指示を出すことは不可能です。そうなると結局は、一人ひとりが各現場でニーズを見出して、お取引先様にどんな価値を提供すべきか、そのために何をすべきかを自分で考える必要があるのです。そうした自業員を育てていくこと。それが当社にとっての「人づくりの経営」だと考えております。
三原 この30年間、「切拓く経営」ができていなかったということは、裏を返せば、この30年間、自業員も思うように輩出できていなかったということかと思いますが、なぜそれほどの長い期間、人づくりが進まなかったのか、江縁さんが思う要因をお聞かせください。

しかし、この30年間は、「切拓く経営」を忘れてしまったのでしょう。そしてもう1つ、日本社会全体が高度成長期から安定成長期に入り、無理にトライしなくても、会社の将来に悲観することなく安定飛行ができたという時代背景もあったかと思います。
この後、下記のトピックが続きます。
続きは、記事をダウンロードしてご覧ください。
●山善の人財マネジメントに必要な「人起点のジョブ型」「適財適職」とは
●時代とともに変化するこれからの経営管理職像と育成・選抜の仕組みづくり
●経営管理職にとってのキャリア自律とは、稼ぎの自律ができること
●人事制度改革を後押しするアセスメントの役割
●「2030年ビジョン」に向けた今後の組織・人財育成ビジョン
- 1