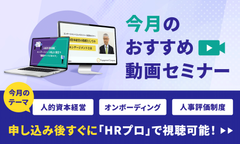そこで今回は、人=セールスドライバーの働きがまさに業績に直結する物流業界の雄・ヤマト運輸株式会社で人事を統括する石井 雅之氏と、ベストセラー『7つの習慣』を世に送り出し、持続的な行動変容を生み出す人材開発・組織開発のプログラムを提供するフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社の竹村 富士徳氏による対談を実施。人的資本経営を成功に導くための最重要ポイントについての考察を進める。(以下敬称略)
【対談者プロフィール】

■石井 雅之氏
1988年、株式会社ブリヂストンに入社。本社、工場、技術センターで勤務した後、アメリカ、スペイン、ベルギーの各事業法人で人事・労務を担当。帰国後は本社でグローバル人事・人材開発、経営企画、コーポレートコミュニケーション、リスク管理、海外事業管理などの業務に従事。2022年10月、ヤマト運輸株式会社に入社。人事・人材開発統括として人事領域全般を牽引している。
ヤマト運輸株式会社 常務執行役員 (人事、人材開発 統括)

■竹村 富士徳氏
1995年、旧フランクリン・クエスト社の日本法人に入社後、経営企画、事業部管理等を経て1998年28歳の最年少で取締役に就任。2000年より現職。HRD事業の開発・販売の指揮をとりながら、自らファシリテーターとして現場に赴き、これまでに1,000回以上の講演・セッションを実施。また研修ツールの小売事業推進から『7つの習慣』をはじめとした出版事業の翻訳及びマネジメント、新規事業開発にも携わる。法人向けサービスだけでなく、学校教育分野における学校改革や児童・教師のリーダーシップ開発も手掛け、10年以上大学での教鞭をとっている。現在、全世界で2,500社以上の組織に導入されているStrategy & Executionの事業本部長兼エグゼクティブ・コンサルタントを務める。
フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社 取締役副社長
国立大学法人筑波大学 客員教授
※取材日:2025年1月31日

業種・業態、そして地域によって人材もそのマネジメント手法も大きく異なる
竹村 富士徳氏(以下 竹村) 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。石井さんはブリヂストンからヤマト運輸へと移られました。当然ながらメーカーと物流では、人材タイプは異なりますよね。石井 雅之氏(以下 石井) メーカーでは、機械に投資して生産性、品質、安全性の向上を追求し、投下する人員はなるべく少なくするというモデルが一般的でしょう。一方、物流業界は、荷物を集め、車に積み込み、運転してお客様に届けるというプロセスのすべてを人手に頼っている業態です。
必然的に期待されるスペック、評価される人材像、人材の生かし方は異なります。物流業界においては、エンゲージメントをより重視して“人の気持ち”に訴えかけていかないと「本来は10個の荷物を運べるのに9個しか運べなかった」ということにもなり得ます。

石井 当社は全国に拠点を持ち、それぞれの土地で採用した人がそこで働き育つ地域密着型の企業。文化や評価軸には地域差があります。たとえば荷物量の多い都心部と広範なエリアを担当する地方ではセールスドライバーに求められる能力や適性は異なります。そうした地域差が人材マネジメントにも反映されます。明文化することができないものも含めて、人材に対する視点や評価基準が異なる面があります。
地域の特性を生かした人材マネジメントをおこなってきた歴史が積み重なった結果として、地域経営の独自性が大きくなります。本社から基本的なマネジメント方針は提示するのですが、例えば評価についても地域間の運用差を必ずしも本社が統制しきれていないところがあります。
竹村 地域差があるとはいえ「本社としてここは譲れない」という部分もあると思います。とりわけ人的資本経営の推進においては、経営戦略と人材戦略を連携させ、全体に浸透させていくための取り組みやメッセージの発信が必要となるはずです。
石井 その通りです。本社の方針にもとづく人材戦略の推進がこれまで以上に必要です。人的資本に関しては、個人が持つ“資本”には3つの種類があると思います。まずは知識、経験、スキル、さらには性格特性まで含めた「ケイパビリティ(能力)」ともいうべき個人資本。2つ目は、どんな人脈を築き、誰とどう繋がっているかを意味する「社会関係資本」。そして最後が、価値観、心の強さや成熟度などを示す「心理的資本」です。
ケイパビリティ向上は本来的に重要で、企業としてもそこには投資しますが、知識やスキルは時代とともに陳腐化することもあります。当社では企業成長に資する事業を強化する方針を掲げていますが、時代や事業が求める人材像を定義し、リスキリングに取り組まなければならないでしょう。社会関係資本も仕事の内容や事業の変化に合わせて個人としてメンテナンスしていく必要があります。
一方、心理的資本は時代や仕事の変化に関わらず成長させることができますし、一度身につけたものは陳腐化することはありません。ここに気づいてもらうことが重要だと思います。
竹村 我々フランクリン・コヴィー・ジャパンが提唱する『7つの習慣』のテーマとも合致する考え方ですね。多くのお客様の人材開発を支援させていただいた約30年の経験からいえるのは「優れた成果は優れた人材によってもたらされる」ということです。そして優れた人材に必要なのは、マインド。意欲と自律性があり、エンゲージメントが高く、新しいものをどんどん吸収する。
そんな心理的資本の持ち主であれば、どんな時代、どんな場所でも成果を生み出せるでしょう。リスキリングより、むしろリマインディング(Re-Minding)、意識改革が必要だというのが『7つの習慣』のメッセージです。

この後、下記のトピックが続きます。
続きは、記事をダウンロードしてご覧ください。
●時代の移り変わりにより、今求められる「リーダーのあり方」
●日本企業のリーダーに必要なリマインディング(Re-Minding)とは?
●人事制度の運用に生じる課題~解決のために向き合うべき「人事の本質」
●社員育成で意識すべき自律性と主体性。ヤマト運輸が推進するエンプロイー・エクスペリエンス(EX)戦略
●人や組織が変わるために必要な「行動変容」と「意識改革」の関係性
- 1