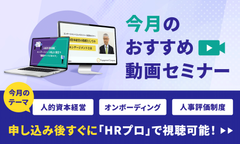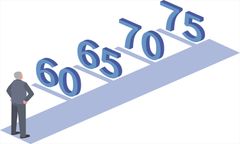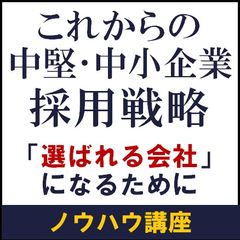「パーパス」とは
「パーパス(Purpose)」とは、直訳すると「目的」や「意図」などと訳される言葉だが、ビジネスシーンにおいては「企業(自社)の存在価値や社会的意義」を意味する言葉として認識されている。もともと企業は、営利=利益をあげることを目的として設立され、存在する。だが近年では社会との“つながり”が重視され、「社会において、どんな役割を果たすのか」、「何のために存在するのか」、「その事業を進める理由・意義は何か」といった点が問われるようになっている。それこそが各企業のパーパスである。
●ミッション、ビジョン、バリュー(MVV)との違い
事業に取り組む姿勢として、ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)を掲げる企業は多い。ビジョンは、企業が目指す「未来の姿」や「展望」、ミッションは企業が果たすべき「使命」、そしてバリューは自社が大切にしている「価値観」や「行動基準」と捉えるといいだろう。これらに対し「パーパス」は、社会とのつながりと貢献度をより強く意識し、自社の存在価値を宣言するものといえる。「パーパス」を追求することで到達するべき目標がビジョン。自社のパーパスを証明・実現するための実際の取り組み・行為がミッション。パーパス/ビジョン/ミッションを成し遂げるための行動指針がバリュー。こうしたイメージで考えることも可能だ。
●経営理念との違い
創業者や現在の経営者が抱く信念、経営を行うにあたっての基本的な考え方・価値観を明文化した経営理念をメッセージとして発信している企業は多い。この経営理念は、社会との“つながり”が必ずしも求められるわけではなく、また社会の動きや時代の変化、経営者の交代によって変更される場合もある。一方「パーパス」は企業の社会的な存在価値を示すもの、事業を展開する根源的理由であり、やすやすと変えるわけにはいかない。経営理念の代わりに「パーパス」を策定・発信する企業が増えていることが、近年の大きな動きである。●クレドとの違い
ラテン語で「信条」や「約束」などを意味するクレドを掲げる企業も増えている。このクレドは、社員が心がけるべき価値観や行動指針を示したもので、概念としてはバリューに近いものだ。バリューが企業全体としての行動指針を内包するのに対し、クレドは個々の社員に期待する行動基準といえる。●「パーパス経営」の重要性
「パーパス」を策定した企業は、社会との“つながり”を強く意識しつつ、自社の存在意義・存在価値を実証するための会社経営=「パーパス経営」に取り組むことが求められる。商品やサービスなどに「パーパス」が十分反映されなければならず、また各種の事業活動は、パーパスドリブン(Purpose Driven)=「パーパス」を起点とした姿勢で取り組むことが重要となる。「パーパス」が必要とされる背景
いま「パーパス」が注目されている背景には、以下のような状況・要素があるといえる。●企業運営・事業活動における価値観の変化
近年、企業にはサステナブル(Sustainable)=持続可能な経営が求められるようになっている。また一企業の持続性だけではなく「世界の持続可能性」が重視され、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)達成に向けての貢献、社会的な責任を果たすことも要求されている。サステナブルな経営の実践には、社会に貢献するという意識が欠かせない。そのため、自社の社会的な存在意義や社会的価値を定義する「パーパス」が必要となってくるのである。
●社会と人材構造の多様化
技術革新などにより社会やビジネスを取り巻く環境は目まぐるしく変化し続けている。直近では新型コロナウイルスの感染拡大といった不測の事態も起こった。未来予測の難しい環境下における経営戦略では、明確な判断基準とスピーディな意思決定が必要となる。また新卒一括採用・終身雇用が主流で、全社員が同じ価値観を抱いて行動していた時代とは大きく様変わり。人材と組織の多様化・グローバル化が急速に進んでいる。明確な判断基準を確立し、多様な価値観の中で行動指針を共有するためには、誰もが理解・共感できる「パーパス」が不可欠となるのである。
●投資家の評価基準の変化
近年の投資家は企業に対し、利益追求だけではなくSDGsへの貢献やESG(環境・社会・ガバナンス)に対する意識の高さを求めるようになっている。そうした企業こそが長く存続し、広く支持され、結果的に大きな利益を生み出すという評価基準を持っているのだ。こうした視点と欲求に応えるためにも、社会的な意義・社会的な貢献度を「パーパス」としてアピールすることが重要となるのである。●DX推進の広がり
現代の企業運営ではDX(デジタルトランスフォーメーション)が大きなテーマ。多くの企業がDXによる業務効率化と働き方改革、ワークライフバランスの向上、新たなビジネスモデルの創出、組織変革などに取り組んでいる。こうした取り組みの拠り所となるのは「パーパス」だ。自社の存在意義や社会での役割が明確になってこそ、DXによって何をどうするのか、顧客や社会に対してどのように貢献するのかが見えてくるのである。●若年層における価値観の多様化
今後、企業活動の中心となるのはいわゆるミレニアル世代=2000年以降に成人あるいは社会人になった、あるいは、なる世代を中心とした若者だ。この世代は、それまでの世代とは異なる価値観や経済感覚を持つとされる。たとえば社会問題に対する関心が大きく、就職先の選択にあたっても「社会的な課題の解決に貢献できるか」といった点を重視するというのがひとつの特徴だ。若く優秀な人材を確保するためには、多くの人たちの共感を得られる「パーパス」が必要となるのだ。●消費行動の変化
ミレニアル世代は消費活動でも中心的な存在となっていく。この世代は単にモノを消費するのではなく、経験(コト)を重視し、環境・地域経済・労働環境といった社会的課題に配慮した「エシカル消費」に対する関心度も高いといわれる。こうした消費活動の指向変化に対応するためにも「自社の社会的意義」を「パーパス」として示すことが重要である。「パーパス」を策定するメリット
「パーパス」を策定することには、以下のようなメリットがあると考えられている。●ステークホルダーからの共感・支持を得られる
「パーパス」によって、社会的な課題と向き合いながら事業活動を行うという姿勢を示すことで、ユーザー・消費者、株主や取引先といったステークホルダーからの共感を得やすくなる。信頼できる企業という印象を多くの人に与え、共感・支持してくれる人が増えれば、売上げ・利益も増え、認知度向上やイメージアップも果たせるはずだ。●従業員のエンゲージメントとロイヤリティが高まる
「パーパス」によって自社で働く人々は「自分の仕事は社会的な解決の課題に貢献している」と実感できるようになる。自信やプライドを持って業務に取り組んでくれることだろう。エンゲージメントが向上し、自社の商品・ブランドに対する愛着や忠誠心=ロイヤリティ(Loyalty)が高まれば、パフォーマンスと生産性も向上する。組織・チームとしての結束力も強くなるはずだ。人材の獲得および流出防止にもつながるだろう。●意思決定がスピーディかつスムーズになる
パーパスドリブンな経営環境では、経営層、リーダーやマネージャー、現場の従業員に至るまで、全員の意志が「パーパスの実現を目指す」という形で統一される。行動の判断基準が明確になり、スピーディかつスムーズな意思決定も可能となるはずだ。●新たなアイディアやイノベーションが生まれやすくなる
「パーパス」があれば「その実現に向けて何が必要か」と自発的・自律的に考え行動する社員が増える。さまざまなアイディアが生まれ、部署の壁や他企業との壁を越えたコミュニケーションも活発化し、イノベーションの創出にもつながるはずだ。「パーパス」の策定から運用までの流れ
「パーパス」を策定し、実際の運用へとつなげるためには、おおよそ以下のようなステップを踏むことになる。(1)自社の強みや事業の意味合いを明確化する
「パーパス」の主旨は「企業としての強みを生かして社会的な課題の解決に貢献すること」にある。まずは自社の歴史、事業内容や商品・サービスの特性を精査したい。さまざまな部署の社員への聞き取りや議論を経たうえで、他社にはない独自の強み、社会の中で果たしている役割を整理し、自社の存在意義を明確化するのである。(2)「パーパス」の言語化=パーパスステートメントの作成
自社が何のために存在するのか。社会に対して提供できる価値は何か。こうした「パーパス」を内外に宣言できるよう言語化したものは「パーパスステートメント」と呼ばれる。パーパスステートメントは、なるべく明快・明確でシンプルであることが望ましい。(3)パーパスステートメントの実行と評価
何よりも重要なのは、「パーパス」に基づいた企業経営を通じて、自社の存在意義を実証していくことだ。社内全体にパーパスを浸透させ、商品やサービスのブランディングなどにパーパスを反映させていかなくてはならない。そうした取り組みの成果を評価することも必要だ。商品・サービスの認知度や売上げの推移、自社が社会にもたらした変化などを調査し、社内外に発信していくことになる。パーパス経営によって社会的な課題の解決に貢献できていることが示されれば、ステークホルダーの満足度は増し、企業のイメージアップも果たせるはずだ。
「パーパス」策定にあたって意識すべきポイント
「パーパス」の策定にあたっては、以下の各ポイントを意識すべきである。●社会的な課題の解決・社会貢献を目指す
「パーパス」には「社会的な課題の解決を目指す」という姿勢が込められていなければならない。身近で起こっている各種の課題に向き合う姿勢がステークホルダーの共感を呼び、自社への支持も広がるのである。●自社の歴史・活動・強みとの合理性がある
自社の企業活動や事業領域とまったく関連性のない社会的な課題に向き合っても、解決は難しく、ステークホルダーからの理解・共感も得られない。企業としての歴史、現在の事業領域、他社にはない強みなどをもとに課題解決を目指す=自社が取り組むことに合理性のある「パーパス」でなくてはならない。●実現可能性がある
あまりに現実離れした目標を掲げても、「パーパス」を実現できる可能性は低くなる。ステークホルダーからは「絵空事」と捉えられ、理解や共感は得られないだろう。事業におけるこれまでの実績を踏まえて実現可能性のある「パーパス」を策定し、その達成に向けての具体的な取り組みや計画まで考えておくべきである。●独自性がある
「自社の強みを生かす」ことで社会的な課題の解決を目指す「パーパス」は、ある意味で他社との差別化を図るものといえる。他社にはない自社だけの強みを前面に押し出し、自社にしか宣言できない「パーパス」を掲げることで、より強いメッセージ性をステークホルダーや消費者に与えることになるだろう。●社員の成長につながる
企業としての存在意義や社会貢献の大きさを示す「パーパス」によって、個々の従業員が自社で働く意義を実感し、自分の仕事に誇りを持てるようになる。モチベーション、エンゲージメント、ロイヤリティは向上し、自発的・自律的な働き方の実践によって成長が促され、生産性も向上するはずである。●企業の利益と持続的成長につながる
社会的課題の解決を目指すとしても、それが無償奉仕、あるいは支出のみでリターンのない活動では投資家をはじめとするステークホルダーに不安と不満を与えてしまう。社会貢献を通じて自社を応援してくれる人が増え、売上げ・利益が増大し、会社が成長していく。短期的には利益を生み出さないが、中長期的に見ると社名・商品・サービス・ブランドなどが浸透して利益につながる。そうした「パーパス」であることが重要だ。パーパス経営の企業事例
最後にパーパス経営を実践する企業の事例を3つ紹介しよう。●ライオン株式会社
ハミガキをはじめとするオーラルケア商品、洗剤、美容・衛生、薬品などの開発販売で知られるライオンが掲げるパーパスは「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する (ReDesign)」というものだ。同社はもともと「習慣をつくることにより社会に貢献する」という姿勢を根幹に置いて事業に取り組んできたが、これを再定義したものといえる。このパーパスに基づき、同社は行政、歯科医学会、学校、さらには他のメーカーまで巻き込んでハミガキ習慣を根付かせるための活動を実践。その結果、1日に2回以上ハミガキをする人の割合は約80%、50年前の約4倍にまで高まり、小学生の虫歯罹患率は50年前の約4分の1に低下する、という実績をあげ、ハミガキのマーケットサイズも50年で約4倍に拡大したという。
●ネスレ
世界最大の食品・飲料会社であるネスレは、世界で初めて粉ミルクなどの乳児用製品を開発し、多くの赤ちゃんを救ったことが事業のスタート地点。「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」というパーパスを掲げ、社会、消費者、生産者、さらにはペットまで対象とした取り組みを進めている。たとえばネスレ日本が進めているのは、「2050年までに温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロを達成する」といったSDGs関連の取り組み、国産コーヒーの特産品化を目指す「ネスカフェ 沖縄コーヒープロジェクト」、保護猫の譲渡会実施といった活動だ。
●ソニー
エレクトロニクス、音楽・映画、ゲーム、さらには金融やメディカル分野まで、事業領域の多角化が進むソニーグループは、企業としての存在意義を見直すべく、それまで掲げていたビジョン、ミッション、バリューの刷新に着手。世界中の従業員から意見を募り、議論を重ね、2019年1月に「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というパーパスを打ち出した。パーパスを全世界11万人の社員に浸透させるための専門部署としてP&V事務局を設立したことも大きなポイントといえる。具体的な取り組みとしては、コロナ禍での活動が特徴的だ。ゲーム内コンテンツのダウンロード無料化などを進めた「Play At Home」イニシアチブでは多くのファンを獲得し、小規模な開発スタジオを支援するために1000万米ドルの基金を設立。また新型コロナウイルスの影響を受けている人々のために1億米ドルにも及ぶ「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」というファンドをスタートさせている。
まとめ~「パーパス」が自社のファンを増やし、成長を後押しする
人々の価値観は多様化した。SDGsの広がりは世界的な潮流となっている。その影響もあって企業の「パーパス」が注目されるようになった。単に利益だけを追求するのではなく「自社の強みを生かして社会的な課題の解決に取り組む」という活動が、いまや企業にとって不可欠なものとなりつつある。志に満ちた「パーパス」があるからこそ、従業員、株主・投資家、取引先は満足感を覚える。これらステークホルダーから共感されることで、従業員のエンゲージメントやロイヤリティは向上し、イノベーションが生まれ、生産性も上がる。資金や資材の調達、人材採用の面でも有利に働くだろう。また消費者や広く社会からも信頼と支持を得られ、自社のファンが増え、社名・商品・サービス・ブランドの認知度は向上する。結果、自社の成長力と持続可能性を高めることになる。
「パーパス」を策定し、企業の社会的意義や存在価値を社内外に発信して浸透させていく。「パーパス」に基づいた事業で社会的な課題を解決していく。そうした姿勢が何よりも求められる時代となっているのである。
よくある質問
●企業における「パーパス」とは?
「パーパス」は、企業が社会に存在する意義や目的を表明したものだ。単なる利益追求ではなく、社会課題の解決や人々の幸せにどう貢献するかを示す存在意義を指す。●企業理念と「パーパス」の違いは何?
企業理念が組織の価値観や行動指針を示すのに対し、「パーパス」は社会における存在意義そのものを表す。具体的に言うと、企業理念が「どのように」事業を行うかの指針であるのに対して、パーパスは「なぜ」その事業を行うのかという根本的な理由を示したものである。- 1