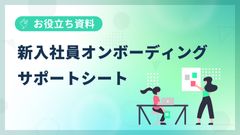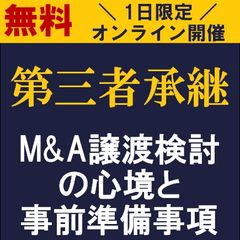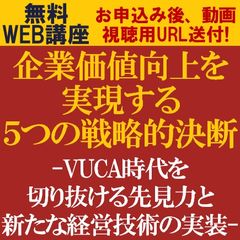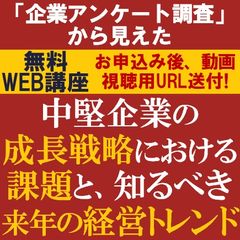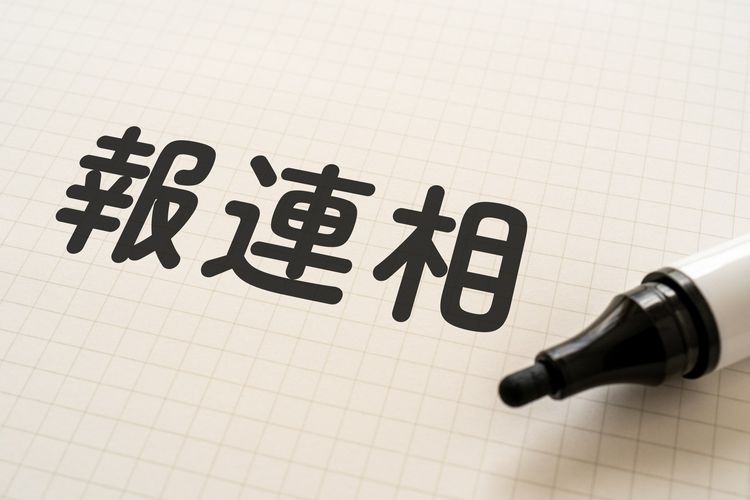
「報連相(ほうれんそう)」とは?
「報連相(ほうれんそう)」は、「報告」、「連絡」、「相談」の3つを指し、それぞれの頭文字を取った言葉である。「報告」、「連絡」、「相談」はいずれも相手に情報を伝える行為だが、目的や意味が異なる。連絡…業務上の事実や決定事項を上司や関係者に共有すること
相談…業務の問題や課題に対して上司や関係者に助言や意見を求めること
「報連相」の重要性と目的
「報連相」がなぜ重要なのか。その目的を説明しよう。●業務効率化
「報連相」をしっかりと実践することで、業務の進捗状況や課題が明確になり、円滑な意思疎通が取れるようになる。つまり上司は適切な指示を出しやすくなり、部下も指示に従って迅速に行動しやすくなるのだ。また情報の共有がスムーズになることで、無駄な作業が減り、業務効率が大幅に向上する。●トラブル回避
「報連相」を徹底することで、トラブルを未然に阻止しやすい。組織として状況を把握しているため、ミスやトラブルの原因をいち早く察知することができるからだ。●早期の問題解決
業務上の問題やミスが発生した際に、速やかに報告・相談をすれば、早期に対策を講じることができ、大きな問題に発展する前に解決しやすい。被害や影響を最小限に抑えることができるというわけだ。●信頼関係の構築
「報連相」を通じて情報共有とコミュニケーションを繰り返すことで、相互理解と協力が促進され、上司と部下、同僚間など組織内の人間関係が良好になる。信頼関係が強化されれば、チームの結束力が高まり、組織全体のパフォーマンス向上につながる。●進捗状況の把握
「報連相」の徹底により、部下の業務進捗状況を正確に把握することができる。遅延が発生すれば、上司は素早く適切な対策を講じることが可能となり、また部下の負担を考慮し、適切なサポートを行うことができる。●得手不得手の把握
「報連相」を通じて、部下の得手不得手を把握しやすくなる。業務スピードに問題が無く、相談も少なければ、得意な業務だと判断できる。逆に進捗状況が思わしくなく、相談が多い業務については苦手だと判断できる。結果、上司は、部下の強みを活かし、弱点を補うための指導や教育を行いやすくなり、組織としても適材適所の人員配置が可能となる。「報連相」がないとどうなる?
「報連相」がないとどうなってしまうのか。デメリットやリスクを解説しよう。●問題の原因が分からない
「報連相」がないと、問題が発生した時に、その原因を特定するのが難しくなる。そのため対策を講じることができず、問題が長期化する恐れがある。また、問題が大きくなってから気づくケースもある。●業務状況が把握できない
「報連相」をしていなければ、上司やチームメンバーが業務の進捗状況を把握するのが難しい。組織としてサポート体制を構築できず、業務遅延や効率的な進行ができない。●トラブルが起きやすい
「報連相」がないために重要な情報が伝わっていなかったり、認識のズレが生じたりすることで、業務上のミスや混乱が発生しやすい。業務の停滞や顧客対応の遅れなど、様々なトラブルが発生する恐れが高まる。●チームワークが低下する
「報連相」ができていないチームは、コミュニケーション不足によって連携がうまく機能しない。個々のメンバーが孤立し、信頼関係の欠如やチーム全体の士気低下にもつながりかねない。「報連相」のポイント
効果的な「報連相」を行う際に重要となる6つのポイントを紹介していく。●正確に伝える
情報を正確に伝えることはなにより重要だと言える。不正確な情報や曖昧な表現は、誤解やトラブルの原因となるからだ。具体的な事実やデータを基に報連相を行い、相手が正確に状況を把握できるよう、簡潔かつ明確に伝えることが肝心だ。●適切なタイミングで行う
「報連相」は遅すぎても早すぎてもいけない。適切なタイミングで行うことが重要だ。悪い報告が遅れると、対策が後手に回り、問題が拡大するリスクがある。特に重要な情報や緊急の問題は早急に伝える必要がある。一方で検討余地の少ない情報を早すぎるタイミングで伝えたところで、聞く側は判断できず、ただ手を煩わせるだけである。●結論から述べる
口頭にしても文書にしても、結論から先に述べることは大切だ。要点を先に伝えることで、相手が理解しやすくなる。具体的な詳細や背景は後に続ける形で補足し、必要に応じて質問や意見を求めると効率的にコミュニケーションが図れる。●相手の都合を考慮する
「報連相」を行う際には、相手の都合や状況を考慮しなければいけない。相手が忙しい時間帯や重要な会議中などに報告や相談をしたところで、望んでいるような対応が得られないだけでなく、相手の手を止めてしまい迷惑をかけてしまう。相手のスケジュールや状況を把握したうえで、「今、お時間よろしいでしょうか」というような伺いを立てることで相手の迷惑になることを避けられる。●事実と私見をまぜない
情報を共有する際には、事実と私見を区別して伝えるように心掛けよう。事実に基づいた情報と、個人的な意見や感想を明確に混在して伝えてしまうと、相手の誤解や混乱を招いてしまう。●解決策を考えておく
単に情報や問題だけを報告するのではなく、解決策も考えて伝えることで、相手の正確な判断を煽ることができ、迅速な問題解決を導くことはできる。さらに、解決策まで提案する姿勢は、積極的な問題解決への意思と取られ、信頼性を高めることにもつながる。「報連相」を社内で定着させる方法
「報連相」を社内で徹底し、定着させるための方法を解説する。●質にこだわりすぎない
質にこだわりすぎると、社員がプレッシャーを感じてしまい、心理的に「報連相」を避ける原因になりかねない。とにかく「報連相」を習慣化することが大切である。完璧な「報連相」を求めるのではなく、タイムリーに情報を共有することを優先し、社員が気軽に「報連相」できるような雰囲気を醸成したい。例えば、短いメモでもいいので情報を共有する習慣をつけさせ、小さな報告でも価値があると認識させることが重要だ。●ルールを定めて仕組化する
明確なルールを作り、仕組化することで「報連相」が格段に定着しやすくなる。以下のようなルールを設けて、社員がいつどんな情報をどのように伝えればいいのかを明確にするのである。・報告頻度:毎日、毎週月曜日、毎月末日など
・連絡方法:チャットツール、メール、緊急の場合は電話
・相談のタイミング:困ったことがあればいつでも
●ツールを導入する
メールや電話だけでなく、チャットツールや情報共有ツールを導入するのも「報連相」を効果的に行うために有効な手だ。目的に応じたツールを活用することで、情報の共有や報告がスムーズに行うことができるうえ、記録を残すようにすれば、後から確認や振り返りができる。●研修を行う
新入社員研修の一環として「報連相」の研修を取り入れることで、社員はその目的を理解し、早期から習慣化することができる。また新入社員以外にも、具体的な実践方法や、実際の業務に即したシミュレーションやロールプレイングを行うセミナーに参加してもらうことで、改めてその重要性を認識したり、「報連相」を受ける側の心得を学んだりすることができる。「報連相」が「時代遅れ」と言われる理由
「報連相」は「時代遅れ」と言われることがある。その理由の一つに、現代のビジネス環境において求められるスピード感や柔軟性に対応し切れてない点が挙げられる。上下関係を重視しすぎるあまり、現場の意思決定や問題解決の迅速性が阻害されたり、資料作成や頻繁な会議の実施によって、むしろ非効率となってしまったりするのだ。また、形式にとらわれすぎて、本来の目的である情報共有や問題解決が疎かになるリスクもある。もっとも、前述した「報連相のポイント」や、以下の項目をしっかりと考慮し、目的に応じた情報伝達をすることで、スピーディーで効率的な「報連相」を行うことができる。
・タイミング
・頻度
・伝える相手が誰か
・伝える手段
・内容の明確さ
・情報量
「報連相」の手法自体が時代遅れなのではないと言える。無駄を省き、適切なタイミングで必要な情報を共有することが重要なのだ。
「報連相」以外の情報共有手法
最後に、「報連相」以外にもビジネスで使える情報共有の手法を3つ紹介しよう。●かくれんぼう(確連報)
「かくれんぼう(確連報)」は、「確認」、「連絡」、「報告」の頭文字を取ったもので、社員の自主性を高めるのに適している手法だ。主に上司と部下の間で用いられ、確認を重視する点が最大の特徴である。「報連相」は「相談」のプロセスを踏むため問題発生時に上司が素早く対応策を伝えられるメリットがあるのに対し、「確連報」は部下が自らの判断に基づいて上司に「確認」するため、自分で考えて行動する力を養いやすい。●ソラ・アメ・カサ
「ソラ・アメ・カサ」はマッキンゼー日本支社で開発された思考のフレームワークだ。以下の3つの流れを意識することで、簡単に状況を整理することができると言われている。アメ「雨が降りそうだ」(解釈・判断)
カサ「傘を持っていこう」(打ち手)
「事実」を正しく認識し、それを「解釈・判断」して“こうなりそうだ”という洞察を行う。そして、その洞察を基に「打ち手」を考えるというものだ。このフレームワークに沿って情報を伝えることで、受け手との解釈のズレが生じづらくなり、スピーディーに問題解決に導ける。
●ざっそう(雑相)
ざっそう(雑相)は、「雑談」、「相談」の頭文字を取ったもので、日常的な雑談を通じて情報を伝え、問題があれば相談するという手法だ。形式的な「報連相」よりも、リラックスした雰囲気で自然に情報を共有され、相談しやすい環境を作りやすい。ただし、受け手側の協力が不可欠であり、会話のコントロールができていないと、重要な情報を得られずに終わってしまう恐れもある。まとめ
「報連相」は、ビジネスにおけるコミュニケーションの基本中の基本であり、業務効率化やトラブル回避、信頼関係構築において重要なスキルである。人事担当者としては、社内で「報連相」を定着させるために、社員にタイムリーな情報共有を促し、気軽にコミュニケーションを図れる環境を整えることが重要だ。さらに目的に応じて、「かくれんぼう」や「ソラ・アメ・カサ」などの情報共有手法を取り入れることで、組織に適したコミュニケーションプロセスを構築できる。本稿を参考に、社内コミュニケーションの見直しを進めてみてはいかがだろうか。よくある質問
●効果的な「報連相」をするためのポイントは?
効果的な「報連相」をするためには、以下の点を意識して行うと良い。・正確に伝える
・適切なタイミングで行う
・結論から述べる
・相手の都合を考慮する
・事実と私見をまぜない
・解決策を考えておく
●「報連相」は必要か?
ビジネスにおいて「報連相」はコミュニケーションの基礎であるため、必要不可欠と言える。「報連相」がなければ、問題の原因が分からなかったり、業務状況が把握できなかったりする。そのため、思わぬトラブルが生じやすく、またそのトラブルが長期化しやすい。さらには、コミュニケーション不足に陥り、信頼関係の欠如や組織の連携が機能しなくなる恐れもある●「報連相」ができない人の特徴は?
「報連相」が上手くできない人の特徴として、以下の点を意識していないことが挙げられる。・タイミング
・頻度
・伝える相手が誰か
・伝える手段
・内容の明確さ
・情報量
以上のことを意識して適切な情報共有を心掛けることで、効果的な「報連相」をすることができる。
- 1