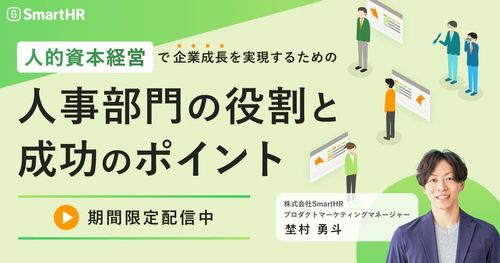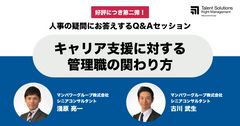■「メンター」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「メンター」とは
「メンター」とは、ビジネスシーンでは若手社員の手本となって助言や指導をし、その成長を促していく先輩社員を意味する。入社3~8年目の従業員が担当するのが、一般的だ。「メンター」を付ける目的は、主にキャリア開発にある。今後どんなキャリアを構築していけば良いか、人間関係をどうすれば円滑にできるかなど、精神的側面・心理的側面から支えていく。同じ部署の先輩だと、どうしても話しにくい悩みもあることから、他部署の先輩が担当することが多い。●「メンター」の語源
「メンター」の語源は、ギリシャの叙事詩「オデュッセイア」に登場する老賢人「Mentor(メントール)」と言われている。メントールは、「勝利を導く者」とされており、その後英語で「メンター」と呼ばれるようになった。そのため、「メンター」は助言者や教育者、指導者、恩師という意味で用いられることが多い。●「メンティー」とは
「メンティー」とは、「メンター」から助言や指導をしてもらう立場の社員を指す。大半は、新卒や20代の若手社員など、経験の浅い社員になる。●「メンター制度(メンタリング)」とは
「メンター制度(メンタリング)」とは、「メンター」である先輩社員が「メンティー」である後輩社員にキャリア開発や精神的なサポートなどを行い、「メンティー」の成長をサポートする教育制度を意味する。●「メンター制度」とOJT(チューター制度)の違い
OJT(On the JOB Training)とは、新人や若手社員が配属された部署で、上司や先輩社員と実務を一緒に行い、必要な知識やノウハウをその都度指導してもらう教育方法だ。OJTの指導を行う社員は「チューター」と呼ばれる。そのため、OJTは「チューター制度」と呼称するケースもある。OJTやチューター制度は、サポート対象が新人や若手社員である点は、「メンター制度」と変わらない。ただし、「メンタル面のサポートはしない」、「サポート期間が短い」のが特徴だ。一方、「メンター制度」は対話を重ねていく中で、「メンティー」自身が気づきを得て、解決策を見出していく指導方法だ。相談内容が多岐に渡るし、サポート期間も長くなる。
「OJT」の定義や目的、デメリット、問題点についての解説はこちら
●「メンタリング」とコーチングの違い
コーチングとは、業務経験者や経営者の目標達成に向けてサポートすることを言う。そのため、サポート期間も比較的短く、サポート内容もかなり専門的な分野に限定される。一方、「メンタリング」はサポートする対象者や内容が広範囲で、長期的なケースがある。「メンター」の役割
次に、「メンター」の役割について取り上げたい。●目標設定とビジョンの明確化
「メンター」には、「メンティー」が今後中長期的に目指していきたいキャリアビジョンを明確化させ、目標を設定する役割がある。ただし、注意しなければいけないのは、「メンター」が目標を押し付けないことだ。あくまでも、「メンティー」自身で考えていく必要がある。そのためにも、「メンティー」にとって、数年後の自分の姿をイメージしやすい「メンター」を任命するようにしたい。●進捗確認と行動改善
目標設定ができたら、目標に対する進捗状況の確認を行う。達成に至るのが、困難な場合は「メンター」が「メンティー」に対して助言と指導を行い、改善を図るようにする。場合によっては、目標自体を見直すことも「メンター」の役割となってくる。●悩みや不安の解決支援
業務上の悩みや不安、人間関係のトラブルは、同じ部署の上司に相談しにくい場合がある。その点、他部署の先輩が「メンター」だと気まずさが和らぎ、相談がしやすくなる。「メンター」として注意しなければいけないのは、問題の解決に向けて一方的に指導・助言をすることだ。また、「メンティー」の相談を何でも受け入れて良いというわけでもない。内容によっては、「職場の上司に相談した方が良い」と諭すことも大切だ。●メンタル面のサポート
「メンター」は「メンティー」に対してメンタル面のサポートを行いながら、継続的に支えていく役割も担う。特に、新人社員はまだまだ仕事環境や職場の人間関係に慣れていないことが多いので、業務やプライベートで悩み事が発生しがちだ。それらを誰にも相談できず、一人で抱えてしまうと、精神状況に支障をきたし、仕事に対するモチベーションの低下、最悪の場合には早期退職に繋がってしまうこともある。「メンター」が必要とされる背景
現代のビジネス環境は、終身雇用制度の崩壊や人手不足、労働時間の短縮、早期離職の増加など多くの課題に直面している。新人の迅速かつ効率的な戦力化が求められる一方で、教育コストは縮小傾向にある。若手社員も、キャリアの展望を描きにくい状況に置かれている。こうした背景から、「メンター」の重要性が高まっている。メンターは、日常業務から離れた立場で新人・若手をきめ細やかにサポートし、組織文化の伝承やモチベーション向上、メンタルケアなどによって新人・若手の成長を促すものだ。メンティーにとって、メンターは社内ネットワークの拡大や組織への帰属意識強化につながる存在であり、キャリア形成のロールモデルにもなってくれる。また、多様性が重視される現代社会では、異なる視点や経験を持つメンターとの対話が、イノベーションや創造性の源泉となることも期待されている。
「メンター制度」のメリット
「メンター制度」には、どうようなメリットがあるのか。企業、「メンター」、「メンティー」それぞれの立場から説明しよう。【企業のメリット】
●離職防止
企業が「メンター制度」を導入するメリットとして、まずは離職防止が挙げられる。入社したばかりの若手社員は職場環境や仕事にすぐには慣れることができない。そのため、業務に関する悩みを抱えがちだ。ストレスや不安を抱え込んだままでいると、早期離職に至る可能性も出てくる。その点、「メンター制度」を導入すると、若手社員はいつでも相談ができるという安心感が得られ、不安を和らげることができる。●主体的な人材の育成
「メンター制度」を導入することで、若手社員の主体的を育み、能動的な人材の育成を図ることができる。「メンター」との対話によって若手社員(メンター)は自身の課題に気づいて改善していけるからだ。それと同時に、「メンター」も相談に応じたり、アドバイスを行ったりすることで責任感を養うことができる。●社内コミュニケーションの活性化
会社全体に「メンター」と「メンティー」という関係が定着していくと、社内のコミュニケーションが活性化し、職場の雰囲気もより良くなっていく。自ずと、働きやすさを感じやすくなるので、社員のエンゲージメントスコアも高まると期待できる。【メンティーのメリット】
●精神面の支えになる
「メンティー」からすれば、相談する相手がいるのは心強い。特に、新入社員はさまざまな不安を抱えているはずだ。それらが少しでも軽減できれば、早く職場に慣れることができる。自ずと、「メンティー」も自身が持っている良さをスムーズに発揮しやすくなる。●モチベーション向上
「メンティー」は、「メンター」に自分の悩みを相談できるだけで安心感を持てる。また、「どうしたらより良いキャリアを得られるか」という気づきを得ることもできる。それらを踏まえ、「メンティー」なりに考え行動していければ、仕事に対するモチベーションも高まるに違いない。【メンターのメリット】
●キャリア形成を考えるきっかけになる
日々仕事に追われていると、自身の中長期的なキャリアを考える余裕がなかったりする。「メンタリング」を行っていく中で、自身の職歴やスキル、成功体験・失敗体験を振り返ることで、今どんなキャリアステージに立っているのか、今後どのような方向に向かっていけば良いのかを思い描くきっかけを得られるはずだ。●責任感やマネジメントスキルの向上
常に「メンティー」の見本でなければいけないという意識を持つことで、仕事への取り組み方や言動に対する責任感が強くなる。また、「メンティー」の悩みや相談に耳を傾け、どうしたら本人の成長につながるかと考えていくことで、後輩をマネジメントするスキルや育成するスキルも高めていける。「メンター」に求められるスキルや資質
ここでは、「メンター」には、どのようなスキルや資質が必要となるのかを解説したい。●コミュニケーションスキル
「メンター」には、コミュニケーションスキルが不可欠だ。具体的には、相手の話をしっかりと受け止める傾聴スキル、相手に対する共感力、その上で自身の経験に基づいて相手に気づきを促すスキルが必要となってくる。●人材育成への意欲
「メンター」は、若手社員を育成するという重要な役割を担っている。当然ながら、若手社員のキャリア形成にも多大な影響を及ぼすことになる。そうした「メンター」の重要性を認識し、人材育成に強い意欲を持って取り組める人が望まれる。●仕事の経験値や実績
「メンター」は「メンティー」の指導者、教育者となる。自身が仕事やキャリアの手本を示すとともに有益なアドバイスやサポートを行う必要がある。それだけに、「メンター」には仕事における経験値や実績がなければ務まらない。「メンティー」にとっても、「メンター」に経験値や実績があると安心感を覚え、信頼度も高まると言える。「メンター」の育成方法
次は、企業として「メンター」を育成する方法を紹介したい。●メンター研修の実施
「メンター」には、コミュニケーションスキルやコーチング力、信頼関係を構築するスキルなどが必要となる。それらを習得してもらうためにも「メンター」研修を実施したい。参加者自身も新たな気づきが得られるし、人材育成のノウハウ・知識も深められるはずだ。●定期的な効果測定
「メンター」と「メンティー」が、それぞれどのような効果を感じているのか、定期的に測定することも有効だ。ただし、その結果をフィードバックする際には、「メンター制度」の内容だけに留めるようにしたい。●メンターのケア
「メンター」自身のケアも重要となる。例えば、何かの事情で「メンティー」のモチベーションが低下したり、退職したりしてしまうと、「メンター」は責任を感じてしまい、従来通りのパフォーマンスを発揮できなくなってしまうかもしれない。「メンター」同士が情報交換しあえる機会を用意する、人事部門が面談するなど、幾つかの施策を講じる必要があるだろう。「メンタリング」のポイント
「メンタリング」を行う際には、押さえておくべきポイントが幾つかある。それらを取り上げたい。●命令や強制をしない
「メンタリング」では、対話を通じて「メンティー」に新たな気づきを与え、自律的な行動につなげていく必要がある。なかなかすぐには反応してくれないかもしれない。そうした場合には、つい気が短くなり、注意や命令口調になったり、無理強いをしたりしてしまうかもしれない。しかし、これでは意味がない。あくまでも、「メンティー」自身が答えを見つけ出せるよう粘り強く質問を投げかけていくことが重要だ。●価値観の違いや成長スピードの差を意識する
一人ひとりによって、価値観も捉え方も異なるものだ、また、同じことを理解したとしても、それをすぐに実践できる人もいれば、時間がかかる人もいる。成長のスピード感には差がつきものだということだ。それだけに、「メンティー」をじっくり見守っていく姿勢が大事になってくる。●守秘義務を守る
「メンタリング」の場で交わされた内容は、絶対に他言してはいけない。万が一、口を滑らせてしまい、職場に広がってしまうと「メンティー」からの信頼が一気に崩れてしまう。内容次第では、職場における人間関係、特に上司との関係が悪くなり、「メンティー」が疎外感を覚え、退職を選ぶ可能性もある。●評価と関連付けない
「メンタリング」と評価を結びつけてはいけない。もし、「メンティー」が話した内容が所属先の上司に漏れてしまい、評価に結びつけられることがあれば、「メンター」と「メンティー」との関係だけでなく、上司や組織との関係にも悪い影響を及ぼしてしまうからだ。「メンター制度」活用の企業事例
「メンター制度」の目的や効果はさまざまだ。実際に「メンター制度」を活用している企業事例を紹介していこう。●シフト制勤務の課題解決(高島屋)
百貨店業態の高島屋では、シフト制勤務のため、OJTの運用が難しく、社内コミュニケーションが希薄になっていた。そこで、入社4年目の社員を「メンティー」、10年目前後の社員を「メンター」として、メンター制度を実施。能力開発や主体的なキャリア形成を図り、組織内の連携強化やマネジメント力向上を促進している。●女性活躍推進(ネスレ日本、キリン)
女性は、結婚、出産・育児、介護といったライフイベントと仕事との関係が大きな問題となりやすい。そのため、女性社員のキャリア形成を「メンター制度」で支援する企業が増えている。ネスレ日本は、女性社員向けの『メンタリングプログラム』に取り組んでいる。さまざまなライフイベントや仕事を経験してきた役員・管理職が「メンター」となって女性社員に助言する取り組みだ。さらに出産・育児休業制度の拡充などで女性社員を手厚くサポートした結果、同社ではマネージャー職の女性比率を40%以上にまで高めることに成功している。
またキリンホールディングスでは“メンティーが次のメンターとなる”『メンタリング・チェイン』によって、女性総合職の継続就業や女性経営職のキャリアアップを促進させている。この取り組みの結果、同社では総合職女性社員の5年目離職率が大幅に低下、女性経営職比率の上昇も実現させた。
●若手が上司を教育する「リバースメンター」(GEジャパン、P&Gジャパン、資生堂、アクサ生命保険など)
現代社会での子育ての難しさ、スマートフォンやSNS活用などのITスキル、最新の流行といった“いま現場で起こっていること”は、経営判断において重要な意味を持つ。しかし、役員や上級管理職がこれらを肌で感じ取ることは難しい。そこで、「メンター」と「メンティー」の年齢関係を逆転させた「リバースメンター(逆メンター)」と呼ばれる施策が広まりつつある。若手・部下が「メンター」となり、役職者・上司の「メンティー」に“いま現場で起こっていること”や“現代社会での常識”を教授するもので、GEジャパン、P&Gジャパン、資生堂、アクサ生命保険などが実践している。厳密な意味での「メンタリング」とは言えないが、役職者・上司、若手・部下、双方の成長を促すとともに世代間ギャップを埋めるための取り組みとして注目を集めている。
まとめ
「メンター」は、さまざまな役割を担うことになるだけに、求められるスキルも多い。任命された側からすると、ハードルが高いと思ってしまうかもしれない。「できれば、そうした責任は負いたくない」と考える先輩社員も少なくないだろう。そうならないためにも、人事担当者やマネージャーは「メンター」として任命する際には、「なぜ依頼するのか」「メンターとなることで何を得られるか」「メンターとして何に気を付けてもらいたいか」などを、一つひとつ丁寧に説明する必要があるだろう。●厚生労働省:メンター制度導入・ロールモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル・事例集(PDF)
【HRプロ関連記事】
●「1on1」の目的やメリット、部下との接し方、企業事例についての解説はこちら
■「メンター」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新情報はこちら
よくある質問
●「メンター」に適任な人は?
「メンター」には、相手の話をしっかりと受け止める傾聴スキル、相手に対する共感力、その上で自身の経験に基づいて相手に気づきを促すスキルなどのコミュニケーションスキルが不可欠だ。また人材育成への意欲があり、仕事の経験値や実績があることが望ましい。●「メンター」がやってはいけないことは?
「メンター」には、「命令や強制をしない」、「人によって価値観の違いや成長スピードの差を意識する」、「守秘義務を守る」、「評価と関連付けない」といった点に注意が求められる。- 1