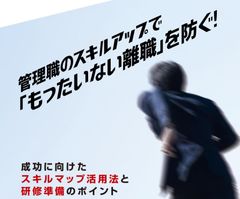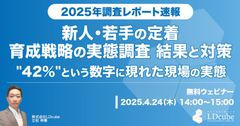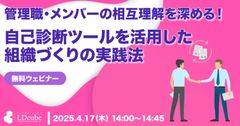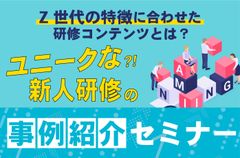「チームビルディング」とは?
「チームビルディング」とは、各メンバーのスキルや能力、経験を最大限に発揮し、目標を達成できるチームを作り上げていくための取り組みを指す。「チームビルディング(team building)」は日本語に訳すと、「チームを作る」という意味になる。チームを作りあげていくうえでは、目標に向けてメンバーぞれぞれのスキルや能力を活かしていくことがポイントになる。また、チームを作るために行うワークやプログラム、今よりも優れたチームを構築するための研修、業務のコミュニケーションといった具体的な方法も含めて「チームビルディング」と呼ぶことがある。
●チームワークとの違い
「チームビルディング」とチームワークは、大きく二つの違いがある。一つ目は能力の活かし方だ。チームビルディングは個々のメンバーの能力を最大限引き出すことに重点を置くが、チームワークはメンバー同士が互いの弱みを補い合うことに主眼が置かれる。二つ目は時間軸の違いだ。チームビルディングは組織の経営ビジョン達成という長期的な視点で取り組むのに対し、チームワークは目の前の課題解決という短期的な成果を目指している。
「チームビルディング」の目的とメリット
「チームビルディング」を実施する目的とメリットについて紹介したい。●内定者や若手社員への主体性のインプット
能動的に仕事をする姿勢といった、内定者や新卒社員の主体性を促すために実施することがある。上司や先輩とのコミュニケーション方法や業務に対する姿勢など、社会人の基本をインプットさせるにも効果的だ。●中堅社員のリーダースキルや変革力の育成
入社3年目以降のいわゆる中堅社員は、マネジメント層と現場の間に立つ機会が多くなってくるため、橋渡し役としてうまくチームを機能させる必要がある。また、マネジメント層の目指すビジョンと現場の実態を把握し、目標達成に向けて組織を動かしていかなければならない。チームビルディングによって、指導力や変革力など、将来のマネジメント層に向けた必要な能力を育成することができる。●責任者・管理者への体制づくり
組織の責任者や管理者は、経営層の考えを部下に伝えることが求められる。チームビルディングを実施することで、マネジメントする部門や部署内の目線を合わせ、目標達成に向けた体制を構築することができる。盤石な体制づくりは、部下の育成にもつなげられる。●経営層のビジョン発信
経営層は経営方針の策定が重要な任務となる。チームビルディングによって、各社員のフェーズに合わせたビジョン共有が行え、社内への浸透にもつなげることができる。●チームパフォーマンスの向上
チームの目標設定やメンバー各自の役割の明確化を手助けするチームビルディング。実施することによって、業務プロセスの可視化や相互理解が進み、メンバー内の結束を高めることができる。チームワークが発揮されることで、組織のパフォーマンスは向上するだろう。●チームメンバーの関係強化
メンバー同士の関係構築のためにチームビルディングを実施することがある。気さくにコミュニケーションが取れるチームは、業務効率が上がるだけでなく、新たなアイデアも生まれやすい。●適切な人材配置
チームビルディングを行うことで、メンバー同士の価値観や考え方を把握することができる。各メンバーの理解が進むことで、リーダーは最適な人材配置を実現できる。●マインドセットの形成
例えば、ゲーム性を持たせた取り組みを行うことで、楽しさが生まれ、メンバー同士は能動的にコミュニケーションを取るようになる。チームの結束力は高まり、目標達成に向けて前向きに動こうとするマインドセットが形成できる。●チームビジョンの浸透
新入社員の入社時や新プロジェクトのキックオフなどにチームビルディングを行うことで、役職者から社歴の浅い社員までチームビジョンの浸透が進むほか、チームの一体感を生むことができる。●コミュニケーション量の増加
チームの目標という共通認識を持つことができるため、メンバー同士の会話が増えていく。コミュニケーションの量が増加することによって、チーム内や上司・部下間の報告・連絡・相談の漏れはなくなる。また、ナレッジやノウハウの共有も増え、チーム内の課題解決がこれまで以上に多く生まれる。●モチベーションの上昇
メンバーぞれぞれのモチベーションが高いチームは、成果が高い傾向にある。メンバー間が高い原動力を持っていれば、能動的にチームに貢献しようというアクションが生まれる。組織内で結果が出れば、さらに各自のモチベーションが上昇する。そして、生産性や品質が上がるという好循環を生み出せる。●新しいアイデアの誕生
チームには、様々な価値観や考え方を持った社員が所属している。チームビルディングでは、メンバーの異なったそれぞれの意見をまとめていく。自分では考えもしないアイデアに触れられ、各自の創造力を磨くことができる。その結果、組織や社内でイノベーションが生まれることもある。「チームビルディング」における5段階プロセス(タックマンモデル)
「タックマンモデル」とは、チームの状態を5段階に分け、次の段階を目指すにはチームビルディングで何が必要かを表したモデルだ。アメリカの心理学者ブルース・W・タックマンが1965年に提唱した。「タックマンモデル」を活用することによって、チームの現状や今後の方向性を把握でき、今よりもチームを機能させるには今後何が必要かが明らかになる。また、目標達成を実現するための施策を考えるうえでも非常に役に立つモデルと言える。ここでは、「タックマンモデル」の5段階プロセスを詳しく紹介したい。
【1】形成期(Forming)
チームができ、まだ間もない状態の形成期。メンバー間の相互理解はなく、チーム目標も明確でない。メンバー同士は、様子を見ながらお互いのことを遠慮気味に知ろうとはしている。次の第2段階では、メンバー間の相互理解が必要となる。【2】混乱期(Storming)
メンバー間で対立が生まれている段階の混乱期。チームが誕生し、少し時間が経つと、メンバー間の考え方の違いによって、組織内で混乱が生まれやすい。次の第3段階では、対立を越えたディスカッションを行い、お互いの考えを認めることが求められる。【3】統一期(Norming)
メンバー同士の価値観や考え方をお互いが理解し、チームの安定期に入ろうとする統一期。チームの目標やメンバーぞれぞれの役割が組織内で共有されており、団結力が見られる。第4段階では、メンバーの特徴に基づいた役割分担、組織内の全員が納得感を持った目標設定などが必要となる。【4】機能期(Performing)
メンバーがそれぞれの役割を果たし、お互いフォローし合う体制ができているのが機能期。各自が同じ目的意識を持って能動的に動いており、チームの団結力はこれまでで最も高い。また、機能期はチーム目標の結果が生まれ始める段階でもある。チームのパフォーマンスを保つためには、リーダーによるメンバーへのケアや団結力を高めるための取り組みが日々欠かせない。【5】散会期(Adjourning)
プロジェクトが終わったり、メンバーが異動したりすることで、チームの活動が終了する散会期。解散を惜しんだり、メンバー間で称賛し合ったりする光景が見られれば、チームビルディングは成功したと言える。「チームビルディング」の手法例
「チームビルディング」には様々な方法がある。代表的な手法を紹介していこう。●心理的安全性を意識した制度策定
チーム内で自由に意見を言える、心理的安全性に配慮した環境づくりは重要だ。互いの発言を否定しないルールや失敗を責めない文化の醸成、新しいアイデアや挑戦を積極的に評価する制度を導入することで、メンバーが互いを信頼して協力し合う風土が生まれる。●1on1の実施
定期的に1on1ミーティングを実施し、メンバーの本音を引き出したり、悩みを受け止めたりすることで、信頼関係を構築できる。また意見を吸い上げることにより、チームや個々の課題や成長機会を発見しやすくなり、キャリアプランの相談や業務上の困りごとの解決など、きめ細かなサポートが可能となる。●チームミーティング
チームミーティングを定期的に開催し、メンバー全員が顔を合わせて情報共有や課題解決を図ることで、目的意識を共有しやすくなる。重要なのは、全員参加・全員発言のルールを設けて全員参加でのコミュニケーションの場とすることだ。人数が多い場合は、いくつかのチームに分けるなどして工夫をしたい。●研修やワークショップ
チームビルディングに特化した研修やワークショップも効果的だ。実践型の研修や体験型のワークショップをチームで行うことで、意見交換をしながら目標を達成する経験を積むことができる。これにより、チームの一体感が育まれる。●ゲームやアクティビティなどのイベント
業務から離れた場所での共同体験は、メンバー間の距離を縮める絶好の機会だ。チームスポーツや料理教室、今流行りの脱出ゲームなど、共通の目標に向かって協力する体験を通じて、自然な形で信頼関係を築くことができる。運動会や社員旅行、バーベキューなどを開催するのも社員同士の価値観の理解が深まるのに有効だ。「チームビルディング」の効果を高めるポイント
「チームビルディング」を行う上で、より効果を高めるためのポイントを3つ紹介しよう。●明確なチーム目標の設定
チームの目標が明確に定まっていれば、各メンバーがモチベーションを保ちながら目標達成に向けて動くことができる。目標が抽象的だったり、メンバー間に浸透していなかったりすれば、チームワークを発揮することは難しい。●メンバーの役割の明確化
チームで成果を出すうえで分かれ目になるのが、各メンバーの役割が具体的になっているかどうかだ。メンバーをまとめるうえでは、異なるスキルや経験を見極め、各自の役割を明確化しなければならない。そうすることで、それぞれが目標に向けて動きやすく、適切な役割を果たすことで、チームの目標が達成しやすくなる。●多様な価値観の容認
それぞれ異なる価値観を持ったメンバーがチームに所属しており、各自の考え方をまずはリーダー、そしてメンバー同士が理解しなければならない。相互理解が進まないチームは、団結力が低下し、やがて業務にも支障が出るだろう。●対立を恐れない議論
異なる意見や視点をぶつけ合うことで、より良いアイデアが生まれ、問題の本質に迫ることができるものだ。そのため対立を恐れてはいけない。ただし、相手の人格を否定したり感情的になったりすることは避け、常に課題解決を目的とした議論を心がける必要がある。「チームビルディング」を推進する際の注意点
「チームビルディング」を進めるうえでの注意点も3つ解説しておきたい。●強制的な目標にしない
やらされ仕事と感じるメンバーが多ければ、それだけチームのパフォーマンスも低下する。目標設定の際は強制せず、メンバー各自が能動的に取り組める目標にしなければならない。チームビルディングを実際に行う時は、メンバーに取り組みたいことをヒアリングしてみるのがいいだろう。そこから目標につながる要素を抽出できる可能性は高い。●メンバーに丸投げしない
メンバーの仕事に対して自由を与えるのも大事だが、ただ丸投げで業務を渡せば、やらされ仕事になる可能性が高い。ミッションや業務の意味を丁寧に説明する取り組みが求められる。●チーム編成の適性を意識する
チームを編成するうえで、単に人数が足りていればいいというわけではない。重要なのは、メンバーぞれぞれのスキルや能力、関係性を考えたチームづくりだ。適性を誤った配置によって、メンバー同士の対立やチーム内のパフォーマンス低下を生むことになりかねない。「チームビルディング」の具体的な企業事例
最後に代表的な3社による「チームビルディング」の事例を紹介しよう。●オリエンタルランド
東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、年に1回アトラクションを利用したカヌーレースを開催している。数千人もの社員が参加し、職場の垣根を越えて自由にチームを組むことができるため、普段接点のない部署の人々との交流を通じて、会社全体の一体感や企業への愛着を育む機会となっている。●メルカリ
メルカリは、レゴブロックを活用したユニークなチームビルディングを実施している。参加者それぞれがレゴでタワーを制作し、なぜその色やパーツを選んだのかなど、こだわりを発表し合う。業務では見えない個人の思考や価値観を共有することで、相互理解が深まり、職場でのコミュニケーション活性化につながっているそうだ。●ぐるなび
ぐるなびでは、「ウォーキング・ミーティング」というチームビルディング手法を実践している。経営陣が社員と歩きながら仕事の話をしていたことから、オフィシャルな会議として定着したそうだ。このウォーキング・ミーティングによって、健康増進だけでなく、オープンな空間での対話による会議室とは違うコミュニケーションが生まれている。まとめ
近年、働き方の多様化やダイバーシティの推進によって、様々な価値観を持った従業員が集まっており、チームのあり方は変化を遂げている。チームで仕事を進めていくにあたって、マネジメント層だけでなく、チームメンバーもこれまでになかった新たな課題に直面しているのではないだろうか。本記事で紹介した「タックマンモデル」の5段階のプロセスを参考にしながら、チームの状況に合わせた最適な「チームビルディング」を実践してみてはいかがだろうか。●「マネジメント」の意味や方法とは? 4つのスキルや階層、業務別マネジメントの種類も徹底解説!
●チームビルディングに役立つミーティングの方法とは~毎日の「報・連・相」でコミュニケーションを~
よくある質問
●「チームビルディング」の5段階とは?
アメリカの心理学者ブルース・W・タックマンが1965年に提唱した「タックマンモデル」では、チームの状態を5段階に分けることで「チームビルディング」を体系化している。【1】形成期:チームができ、まだ間もない状態
【2】混乱期:メンバー間で対立が生まれている段階
【3】統一期:価値観や考え方をお互いが理解し、チームの安定期に入ろうとする
【4】機能期:メンバーがそれぞれの役割を果たし、結果が生まれ始める段階
【5】散会期:プロジェクトやチームの活動が終了する
- 1