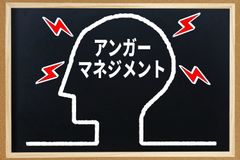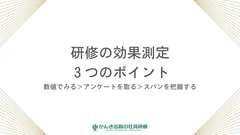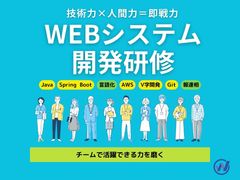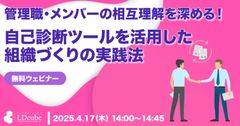Q1:これまでのキャリアは?
【人事リレーの輪11人目】
株式会社indi 取締役 Co-Founder
宮崎 拓海氏
私のファーストキャリアは、株式会社リクルートからスタートしました。新卒で最初に配属されたのが、求人情報誌「タウンワーク」の広告営業です。2年ほど経験して、今度は「タウンワーク」を制作している編集部に異動となりました。そこでは、どういう広告商品をつくるのか、どう販売を促進していくかなど営業推進のような仕事に2年ほど携わりました。リクルートには4年ほど在籍したのですが、次は友人と一緒にチャレンジに近い形で、株式会社nanapiというハウツーメディアをつくる会社を始めました。私のロールは、COOです。メディア、インターネットプロダクトをつくっていく形の会社でしたので、技術的な側面以外の記事コンテンツの量産や広告営業の推進、組織の整理など幅広く統括しました。
その後、同社はKDDIグループに入ることになり、Supership株式会社という社名に変わりました。そこからまたキャリアが大きく変わっていきます。nanapiでは経営者として何かの役割に特化してやっていたというよりも、目の前のことに全部取り組むような形でした。それゆえ、雇用されて働く、会社員という立場になった時、ふと思ったのです。自分は一体何ができて、どんな専門性を発揮できるのか。そこで、今で言うところのリスキリングに向き合い、HRのインプットに努めました。例えば、「ヤフーの1on1」著者の本間さんの塾や南山大学の中村先生の組織開発の講座に通うなど、アカデミックなHRの知識習得に励みました。そこから、本格的に私の人事のキャリアがスタートします。
Supershipでは、人事として採用や組織開発をミッションとして業務に取り組んでいたのですが、グループ会社である株式会社コネヒトから人事責任者が必要ということで、声をかけていただいて転籍しました。そこでは5年ほど在籍することになるのですが、最初は人事の責任者から入って、コーポレートの責任者、執行役員、取締役という形でどんどん役割が変化していきました。そしてその後、 友人と共同創業したindi社に本格ジョインしたというのが、私のこれまでのキャリアです。
Q2:今の人事としての役割・ミッションは?
一言で言うと、「職種の発明」に近いことをやっていると思います。私たちの会社は、エンタテインメントにマーケティングの概念を注入すれば、もっとビジネスが広がるということを基本思想として懸命に取り組んでいます。一見、当たり前の話ではありますが、エンタテイメント業界は特殊です。例えば生活消費財、シャンプーであれば年間の消費量がある程度決まっており、全体のマーケットからどれだけシェアをとるかというブランドマーケティングの戦いがあります。一方でエンタテイメントはシェアという概念が強くありません。人々はコンテンツに対峙した時に、気持ちが高まれば購入に至り、高まりきらなければ購入に至らないわけです。そのため、消費者をときめかせる魅力的なクリエイティブ、プロダクトが重要とされてきました。
また、TVを中心としたマスメディアの存在も大きく、大きな資本を注入されたエンタテイメントコンテンツはマスメディアと共にありました。消費者を細かく捕捉する必然性がなかったわけです。つい十数年前までは、TVを通じて皆が同じ音楽を聴き、同じドラマで涙を流していましたよね。
しかし、近年は大SNS時代となり、消費者とコンテンツの関係性が一変しました。好きなコンテンツは自ら探しにいけますし、SNSのタイムラインもパーソナライズされていて、消費者にとっては、すごくいい時代です。一方でコンテンツ事業者にとってはどうでしょうか。ニーズが細分化されているので、消費者と関係を構築することが非常に難しくなってきています。
それ故、マーケティングという概念が急速に必要とされてきています。しかし、マーケティングだけを強く掲げてもうまくいきません。作り手へのリスペクトを前提として、プロダクトアウトとマーケットインをどうバランスよくデザインしていくかが肝になります。この塩梅調整は前例が存在しないため、自分たちで開発していかなければなりません。今の時代におけるエンタメコンテンツのプロデューサーとは、一体どのような仕事なのか。必要なスキルや考え方は一体どういうものなのか。「マーケティングの力を駆使し、文化性と経済性を両立するエンタテインメントコンテンツを生み出す」そのような職種を発明して、未経験の人材を採用し、育んでいくこと。それが私のメインミッションだと思っています。
本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。
Q3~Q10の続きは、下部よりログイン、または会員登録の上、ご覧ください。