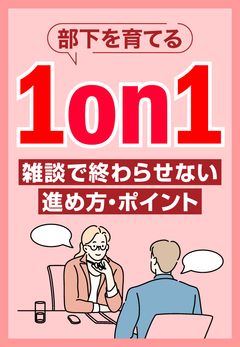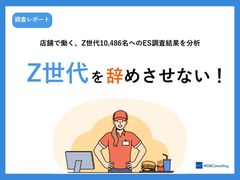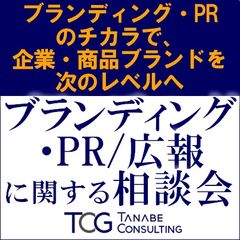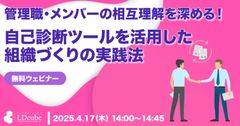「ワークショップ」とは?
「ワークショップ」とは、参加者が主体的に参加し、実践的なスキルや知識を習得したり、課題解決に向けたアイデアを出し合ったりするための体験型の講座のことである。一般的に、複数人の参加者がグループとなり、与えられたテーマや課題に対して積極的な意見交換をしながら共同で作業を行っていく。主な目的は参加者のスキル向上や知識習得、アイデア創出、問題解決、ビジネス戦略の構築、コミュニケーションの活発化などで、人材育成や組織開発に有効な施策と言える。
●「セミナー」との違い
セミナーは主に専門家や有識者が講師となって、ほとんど一方通行の情報発信をし、参加者は受動的に知識を受け取る形式である。一方で「ワークショップ」はグループでの行動やコミュニケーションによって共同作業をするため、参加者の自発的・能動的な参加が求められ、より実践的なスキルや知識の習得や定着を目的としている。「ワークショップ」の種類
ビジネスにおける「ワークショップ」には主に4つの種類がある。それぞれを解説していこう。●研修型ワークショップ
研修型ワークショップとは、文字通り社員のスキル向上や知識習得などの研修を目的としたワークショップである。業務に直結するテーマや実務に役立つ技術や知識の定着を課題とする。例えば、新しいソフトウェアの活用方法を学ぶ技術研修や、営業スキルを高めるセールス研修などだ。●問題解決型ワークショップ
問題解決型ワークショップは、社内でなんらかの問題を抱えている時に、それを解決するために実施する。ワークショップでの意見交換によって、多くのアイデアや解決方法を見出し、解決のヒントを得るために有効である。●採用型ワークショップ
採用型ワークショップは、新卒採用の選考やインターンシップの取り組みの一環として開かれるワークショップを言う。ワークショップを通じて採用候補者の行動を見ることができるほか、会社のミッションやビジョンを共有するために活用することもできる。●イベント型ワークショップ
イベント型ワークショップは、社内レクリエーションとして開催されることが多く、社員同士のコミュニケーションを深めて職場の雰囲気や一体感を醸成することや、リフレッシュを目的としている。例えば、アウトドアでのアクティビティや、ものづくりやアート体験などが挙がる。「ワークショップ」のメリット
次に「ワークショップ」を実施するメリットについて解説していく。●当事者意識が生まれる
参加者が主体的に活動するため、自分事として捉えやすくなるのが、「ワークショップ」の最大の特徴と言える。参加者が自らの意見を述べ、当事者意識を持って問題解決に取り組むことで、責任感を育むことができる。●実践的な知識やスキルを習得できる
「ワークショップ」では、理論だけでなく実際の業務に役立つ実践的な知識やスキルを学ぶことができ、学んだ知識やスキルをすぐに体験を通して自らの行動に落とし込むため、より理解を深めることにもつながる。●さまざまな価値観や新たな視点を学べる
複数の参加者が意見を交換する「ワークショップ」では、さまざまな価値観や新たな視点を学ぶことができる。そうした多様な意見や考え方に触れる環境では、参加者の視野が広がり、イノベーションを生み出しやすいと言える。●モチベーションが上がりやすい
参加型の講座である「ワークショップ」では、社員が自発的に行動するため、受動的な講義形式よりもモチベーションが上がりやすい。またグループ内で意見が尊重される場面が作られることで、自己肯定感が増し、ワーク終了後には達成感を得やすいというのも大きなメリットだ。●コミュニケーション能力向上につながる
グループでの共同作業や意見交換を通じて、参加者は他人の意見を聞く力や自分の意見を正確に伝える力が養われ、自然とコミュニケーションスキルが磨かれる。そのため社員が日常業務で円滑にコミュニケーションを取れるようになる。●疑問や要望にすぐ対応できる
講義形式の場合は、講義の途中に講師に質問を投げかけることはなかなかできない。しかし「ワークショップ」の場合は、作業中に参加者やファシリテーターに質問や要望を投げかけやすく、疑問点をすぐに解決できる。開催者としても参加者が抱える疑問や課題に迅速に対応しやすい。「ワークショップ」のデメリット
「ワークショップ」には一部のデメリットもある。実施する際には、事前に以下の事項に留意しておきたい。●雰囲気の違いによって質の差が生まれる
「ワークショップ」は参加者の積極性やその場の雰囲気によって、成果にばらつきが出やすい。ファシリテーターが不慣れだったり、参加者が消極的だったりする場合は、全体の進行に差が出て、均一の効果を得られない恐れがある。●幅広い知識を得るには不向き
「ワークショップ」は特定のテーマにフォーカスするための講座であるため、幅広い知識を得るには向いていない。知識を広げたり、多分野に渡る情報を網羅したりするには、講義形式のように体系的に情報を得られるほうが良いだろう。●細かいタイムスケジュールが必要
効果的に「ワークショップ」を進行するためには、緻密なスケジュール管理が求められる。時間配分を誤ると、内容を十分にカバーできなかったり、参加者の集中力が途切れたりすることがある。「ワークショップ」の進め方
「ワークショップ」を開催するとき、どのように進行すればいいのか。順を追って説明していく。(1)目的とスケジュールの説明
まず冒頭でワークショップの目的や全体の流れを明確に伝えることで、参加者の理解を深めることができる。具体的な目標を共有して、参加者全員が同じ方向を向いて取り組めるようにすると良い。(2)グランドルールの共有
実際のワークに移る前に、参加者に基本的なルールを共有する。例えば、「他人の意見を否定しない」、「時間を守る」、「役割をあらかじめ決める」などのルールを明確にすることで、円滑に進行でき、また参加者により理解を深めてもらいやすくなる。(3)ワークの実施
実際に計画に沿った作業を実施する。実践を重視し、参加者全員が積極的かつ能動的に取り組めるよう、あらかじめシミュレーションをしておくと良い。一般的には以下の流れで行うことが多い。・個人ワークでアイデアの創出と整理
・グループ内でアイデア共有
・グループ内で議論
・グループでまとめたアイデアを全体で発表
(4)フィードバックや振り返り
ワークの最後にはフィードバックや振り返りの時間を設け、学びを定着させることも重要だ。また参加者からの意見や感想を収集し、新たなワークショップのアイデアや次回の改善点を見つけることができる。「ワークショップ」成功のポイント
「ワークショップ」の成果を高めるために、気を付けたいポイントを7つ紹介しよう。●明確なゴールの設定
最終的に何を達成したいのかを明確にし、参加者全員で共有することは、なにより重要だと言える。具体的な目標を設定して共有することによって、参加者のモチベーションを高め、方向性を統一できるからだ。●個人ワークを含める
グループでの共同作業を始める前に個人ワークの時間を設けることで、参加者は自分の考えや意見を整理することができる。いきなりグループワークをすると、参加者の主張がまとまらないままで建設的な話し合いができない恐れがある。●アイスブレイクを取り入れる
ワークに入る前にアイスブレイクを取り入れ、参加者の心理的安全性を高めることも、効果を高めるために大切だ。参加者がリラックスして臨むことで、雰囲気が良くなり意見交換が活性化する。●ファシリテーターの選定
ファシリテーターは参加者の意見を引き出したり、雰囲気を作ったり、進行をスムーズにしたり、ワークショップにおいて非常に重要な役割である。不慣れな人ではなく経験豊富な人を選ぶことで、設定したゴールに向かって効果的に進めることができる。●適切なグループ人数の設定
適切な人数を設定して、全員が発言しやすい環境を整えたい。多過ぎれば発言する機会が減り、少な過ぎれば意見交換が活発化しない可能性がある。テーマにもよるが、一般的には1グループあたり4〜6人が適切と言える。●作業環境の整備
快適な作業環境を用意することで、参加者の集中力を高めることができる。例えば、十分なスペースや適切な照明、輪になって話せるような丸形の机を用意したり、緊張をほぐすためのBGMを用意したり、そうした事前準備をしておくことで生産性が挙がる。●役割の設定
参加者それぞれに役割を設定することで、責任感と主体性を持ってもらい、積極的にワークに取り組んでもらいやすくなる。例えば、進行役、タイムキーパー、記録係などだ。また役割分担は、チームの協力関係を構築するのにも役立つ。「ワークショップ」の具体例
では、最後に4つの分野に分けて「ワークショップ」の具体的な例を紹介していこう。●ビジネス系
ビジネス分野では、マーケティングやリーダーシップといったスキルを高めるための「ワークショップ」が一般的だ。例えば、リーダーシップ研修、新人研修。そのほか、新製品のアイデアを出し合うブレインストーミングや、顧客に対してサービスを利用してもらって意見を聞くことを目的としたイベント型のマーケティングなどもある。●芸術
アートや音楽などの創作活動やダンスによって、文化や表現方法を学ぶ「ワークショップ」は多い。絵画教室や音楽制作、手芸や料理などのものづくりを通して、参加者の親睦が深まり、新たな趣味の発見につながる。企業としてはリラックスやチームワークの向上に活用できる。●学術分野
さまざまな学術分野において「ワークショップ」は実施されている。研究者を中心としたグループディスカッションなどの集まりや、最新の研究成果や技術を発表する場として開催されることもある。学会やシンポジウムの一環として行われるワークショップもある。●社会教育
自然環境などの地域の問題解決や行政に関する「ワークショップ」は、市民活動やまちづくりの一環として実施される。例えば、環境保護に関するワークショップや、地域の安全対策に関するディスカッションなどが挙がる。まとめ
「ワークショップ」を効果的に取り入れることで、社員に実践的なスキルや知識を身につけさせ、また組織としてのチームワークを向上させることができる。人材育成や組織開発に悩む人事担当者としては、社内での実施を検討してみてもいいだろう。ただし効果を最大化できるよう、明確なゴール設定や、適切なファシリテーターの選定など、記事の中で紹介した進め方のポイントにぜひ気を付けていただきたい。よくある質問
●「講義」と「ワークショップ」の違いは?
「講義」や「セミナー」は主に専門家や有識者が講師となって、ほとんど一方通行の情報発信をし、参加者が受動的に知識を受け取る形式である。一方で「ワークショップ」は数人程度のグループとなり、参加者は積極的に意見交換や共同作業をしながら進める体験型の講座である。●「ワークショップ」の利点と欠点は何?
「ワークショップ」のメリットとデメリットは主に以下がある。【メリット】
・当事者意識が生まれる
・実践的な知識やスキルを習得できる
・さまざまな価値観や新たな視点を学べる
・モチベーションが上がりやすい
・コミュニケーション能力向上につながる
・疑問や要望にすぐ対応できる
【デメリット】
・雰囲気の違いによって質の差が生まれる
・幅広い知識を得るには不向き
・細かいタイムスケジュールが必要
- 1