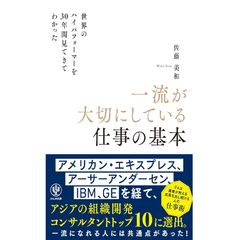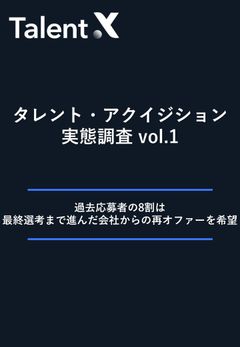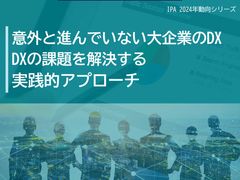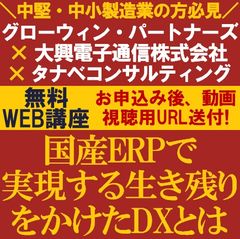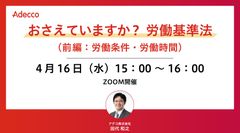「アウトソーシング」とは
「アウトソーシング」とは、「外部委託」のことで、業務の一部を外部の専門家や企業に委託することである。主に業務の効率化やコスト削減、内部のリソースを社内業務に集中させることを目的とする時に使う。●「アウトソーシング」の歴史
「アウトソーシング」が生まれた年代は諸説あるが、その有効性が広く知られるようになったきっかけは、1989年にコダック社がIT部門をIBM社に委託した事例だと言われている。それまでのITのアウトソーシングと言えば、技術力の低い企業が行うものだと思われていたところ、当時高い技術力を持つ大手企業であるコダック社がアウトソーシングによって、社内のコア業務にリソースを集中させてコスト削減、株価上昇につなげることに成功した手法が高く評価され、注目された。その後、1990年代に日本企業でもアウトソーシングが急速に推進され、IT業務から、総務、人事、財務・経理など多様な範囲で行われるようになった。
●「アウトソーシング」の需要が増えた背景
近年、「アウトソーシング」の需要が増加している背景には、「人材不足」と「IT技術の急速な発達」がある。日本では少子高齢化に伴う生産年齢人口(15歳~65歳未満)の減少により、多くの企業が人材不足の課題を抱えている。限られたリソースで生産性を向上するには、自社の従業員がコア業務に集中させる必要があるため、ノンコア業務を外部に委託する企業が増えている。またIT技術が急速に発達していることで、企業の競争力を高めるには、最新技術を活用せざるを得ない状況となっている。そのためIT専門企業へのアウトソーシングが増えているのだ。
「アウトソーシング」と人材派遣の違い
「人材派遣」とは、派遣会社と雇用関係にある人材を派遣してもらい、業務に就いてもらうサービスである。「アウトソーシング」と人材派遣は、外部のリソースを活用するという点では共通しているが、その目的や範囲には大きな違いがある。「アウトソーシング」は、特定の業務を一括あるいは大部分を外部に委託する。つまり業務管理や人員配置などに関しても委託先に委ねることになる。一方で「人材派遣」は、一般的に企業が一時的な労働力を必要とする場合に、人材派遣会社から業務に適した人材を調達する。派遣社員は、派遣先企業の指揮命令の下で行うため、業務管理や配置は自社で行うことになる。
また、「アウトソーシング」は納品された成果物やサービスに対して対価が発生する。したがって、委託先企業の社員の労働には対価は支払わない。一方で「人材派遣」の場合、派遣社員の労働に対して対価を支払う。働いた日数や時間、残業代などの手当なども発生する。
●人材派遣より「アウトソーシング」が向いているケース
人材派遣より「アウトソーシング」が向いているケースとしては、速やかに業務体制を構築したい場合や定型業務を任せる場合などが挙がる。自社で担当人材をいちから育成しなければならない業務を、専門的な技術や知識をすでに持っている企業にアウトソーシングすることで、スピーディーに業務体制を構築できる。また定期的に発生したり、自社でノウハウを蓄積する必要がなかったりする定型業務においてもアウトソーシングすることで工数を減らすことができる。「アウトソーシング」の業務内容における分類
「アウトソーシング」には、BPO、ITO、KPOという代表的な分類がある。特定の業務領域を対象としているため、違いを知っておくと良いだろう。●BPO
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、業務プロセスを一括で外部に委託する形態を言う。人事や総務、経理に関する業務が代表的で、これらの業務やまとめて外部に委託することで、企業は経営のコア業務に集中することができる。●ITO
ITO(ITアウトソーシング)は、IT分野の業務を外部に委託する形態を言う。現代ではIT技術の発展が急速に進んでいるため、自社での知識や技術で対応できないときに、IT開発やデータ管理などのIT関連業務を外部の専門企業に委託することで、専門性の高い技術を活用することができる。●KPO
KPO(ナレッジ・プロセス・アウトソーシング)は、「知的業務委託」とも言われ、情報収集や高度な分析、レポーティングなどの知的処理業務を外部に委託する形態を言う。委託業務の例としては、医療開発・医薬開発のための治験データの収集、株式調査やビジネスにおける市場調査など、高度な知識や専門的なスキルを必要とする業務などが挙がる。ビジネスにおける重要度の高いデータの分析を外部に委託することで、イノベーションの創出や高度な意思決定につながる。「アウトソーシング」の契約形態における分類
「アウトソーシング」の契約形態には、「コソーシング」、「マルチソーシング」、「クラウドソーシング」、「オフショアアウトソーシング」といった種類がある。企業のニーズや戦略に合わせて選択できるよう、理解しておきたい。●コソーシング
コソーシング(co-sourcing)」の「co-」は英語で「共に」を表す接頭語である。つまりコソーシングとは、委託元企業と受託企業が対等な立場となって共同で業務にあたる契約形態のことを指す。コソーシングは、受託企業の専門知識や技術をいち早く活用できるというアウトソーシングのメリットを生かしながら、共同で業務にあたることで、ノウハウや知識を社内に蓄積することができる。
●マルチソーシング
マルチソーシングとは、業務ごとに最適な受託企業を選び、複数の企業と契約する形態を指す。一般的なアウトソーシングは、特定の1社に業務を丸投げする状態が多く、管理能力の低下やコスト削減の意識低下などの問題が発生しやすい。しかし業務ごとに最適な委託先を変えるマルチソーシングは、コストや進行を管理しやすいという特徴がある。●クラウドソーシング
クラウドソーシングとは、インターネットを通じて不特定多数の人に業務を委託する契約形態のことである。一般的に企業がプラットフォーム上で業務内容を開示して受注希望者を募る。そして集まった希望者の中から委託する人を決める。委託先はフリーランスが多く、依頼内容はシステム開発や記事作成、デザイン・イラスト作成、翻訳・通訳、写真撮影など多岐に渡る。●オフショアアウトソーシング
オフショアアウトソーシングは、国内ではなく海外の企業に業務を委託する契約形態を指す。日本よりも人件費の安い外国の企業や人材に業務を行ってもらうことで、人件費などのコストを削減できるのが最大のメリットと言える。「アウトソーシング」を活用するメリット
「アウトソーシング」を活用することで、企業はさまざまなメリットを受けられる。ここで主な5つを紹介する。●コア業務に集中できる
アウトソーシングによって、ノンコア業務を外部に委託することで、社内の従業員は本来注力すべき内部のコア業務に集中することができる。これにより企業の生産性や競争力の向上が図れる。●コスト削減につながる
社内で人材を採用したり育成したりするのには小さくないコストがかかるものだが、業務をアウトソーシングすることによって、人材の採用・育成のコストや設備投資・運用の費用を削減することができる。●対応速度・品質が高まる
専門的な知見や長年培ってきたノウハウを持つ企業にアウトソーシングすることで、自社で行うよりもスピーディーかつ正確に業務を遂行でき、高い品質も期待できる。●自社では対応できない業務の対応ができる
高度なスキルや専門的な知識が必要で、自社で対応するのが難しい業務もあるだろう。そんなときにアウトソーシングを利用することで、自社では対応できない業務でも効率的に対応することができる。「アウトソーシング」を活用するデメリット
「アウトソーシング」を活用する際には、いくつかのデメリットがあることも考慮しなければいけない。主な4つを解説していこう。●業務の把握が大変
外部に業務を委託する場合、当然ながら自社で行うよりも、どのように業務が進められているかの把握が難しくなる。委託先で業務管理がきちんとしていなければ、進行の遅延や品質の低下などの問題が発生しかねない。委託先企業の業務を把握するには、密なコミュニケーションが欠かせない。●ノウハウが蓄積されない
業務を一括して外部に委託することで、社内にノウハウや経験が蓄積されないという弊害もある。そのため将来的に内製化に切り替える可能性があるような業務は、すべてをアウトソーシングするのを避けたほうが良いだろう。●情報漏えいリスクがある
アウトソーシングによって、外部の人に機密情報や個人情報が渡ることによって情報漏えいのリスクが高まるのは言うまでもない。委託先の企業が信頼に足るか、セキュリティレベルが十分かどうかを判断する必要がある。●かえってコストや手間がかかることもある
アウトソーシングが必ずしもコスト削減につながるとは限らない。外部に業務を委託するには契約の手間や準備などに時間や労力が必要となる。そうした時間や労力を考慮しないと、かえってコストや手間がかかることもある。業務委託の適正コストを知っておくことも重要だ。「アウトソーシング」する業務の判断ポイント
「アウトソーシング」を導入する際には、委託する業務を適正に判断する必要がある。効果的なアウトソーシングを実行するために、以下のポイントに注意したい。●現状の課題と目的は明確になっているか
まずは何のためにアウトソーシングするのかを明確にしなくてはいけない。自社が抱える現状の課題と目的をはっきりさせ、それに基づいて外部に委託する業務を選定する必要がある。●コア業務とノンコア業務を整理できているか
コア業務とノンコア業務を整理できていないと、何を委託すべきかの判断ができない。コア業務は企業の中核を担う業務であるため、社内で管理・進行すべきだ。一方でノンコア業務は利益に直結しない補助的な業務であり、定型化できるためアウトソーシングに適している。●業務の総コストが算出できているか
業務の総コストを正確に算出し、社内で遂行する場合とアウトソーシングする場合で比較することが重要だ。その際、業務の委託費用だけでなく、契約管理や設計構築にかかるコストなど多角的に見る必要がある。●設計構築に時間的な余裕がとれるか
アウトソーシングを検討した時には、設計構築に十分な時間的な余裕があるかどうかを確認しておきたい。外部に業務を委託するための計画を立てたり、引継いだりするには時間がかかることがあるため、事前に適切なスケジュールを立てると良い。●導入後の体制イメージがあるか
闇雲にアウトソーシングするのではなく、導入後にどんな体制で管理していくか、どう業務進行を把握するか、誰が担当となってコミュニケーションを図るかをあらかじめイメージしておかなくてはいけない。効果的なアウトソーシングをするためには、適切な進行管理と委託先とのコミュニケーションが不可欠である。●「アウトソーシング」に適した業務か
前述したとおりアウトソーシングに向かない業務は、企業のコア業務や機密性の高い業務だ。一方でアウトソーシングに適しているのはノンコア業務である。ただし、社内で効率化できる業務であれば、アウトソーシングする必要はない。業務を委託する前に今一度、その業務が本当にアウトソーシングに適しているかどうかを判断しておきたい。「アウトソーシング」に適した業務内容
「アウトソーシング」に適した業務内容は具体的にどんなものがあるのか。6つの業務に分けて説明していこう。●人事・採用業務
人事部門は経験が求められるうえ、採用戦略に結びつく重要なセクションである。ただし、すべてを自社で完結する必要はなく、アウトソーシングに適している業務は多い。代表的な例に給与計算や勤怠管理、社会保険業務などがある。給与計算や勤怠管理は工数がかかるうえに保険料や税金の計算には専門的な知識を要す。さらに社会保険業務も各種手当金の申請や保険に関する給付申請書の届出、確定申告の届け出、年末調整なども負担の大きな業務である。ただし、それらはあらかじめ申請する時期が決まっているため、定型化しやすい業務内容であると言える。その他、社員研修もアウトソーシングに適しているだろう。社内で講師となる人材がいない場合は、外部に委託することで講師の確保ができ、また専門の研修サービスは独自の成果測定方法を持っているためことが多いため、成果が可視化しやすいメリットがある。
また、採用業務のアウトソーシングはRPO(リクルート・プロセス・アウトソーシング)とも呼ばれる。採用手法の多様化や採用活動の長期化・通年化により、業務の一部あるいはすべてを外部に委託するのは業務の効率化に有効で、近年導入する企業が増えている。
●経理業務
経理業務は社会的に共通したルールに沿って行う業務が多く、定型化しやすいため、外部委託しやすい分野だと言える。特に「アウトソーシング」が有効な経理業務は、記帳業務や決算業務などがある。記帳業務や決算書の作成は、細かな作業なうえ膨大な手間と時間を要するため、アウトソーシングすることで業務の負担軽減につながる。●総務・事務業務
総務・事務業務は、社員の業務を支える重要な業務であり、その業務は多岐に渡る。そのためデータ入力などの単純作業も多く、そうした単純な業務をアウトソーシングすることで、業務の効率化が図れる。また福利厚生を外部に委託することでコストを抑えながら、従業員に充実したサービスを提供することもできる。●営業業務
営業業務は、企業の収益拡大には不可欠で、営業リソースの確保は多くの企業が抱える課題だ。テレアポやインサイドセールス、市場調査などはアウトソーシングしやすい業務と言え、営業代行やSPO(セールス・プロセス・アウトソーシング)を活用することで部門拡大を図ることができる。●コールセンター業務
コールセンターには設備への投資や人材確保のコストがかかる一方で、繁忙期と閑散期の差が激しい。そのためアウトソーシングして、コストを削減している企業は多い。●IT関連業務
IT技術の発展は急速で、IT人材の確保に追われている企業は多い。社内でIT人材を育成するのは手間とコストがかかるため、IT関連業務を一括でアウトソーシングするのは有効と言える。社内にITスキルを持った人材がいても、開発の規模が大きく社内のリソースだけで対応できない場合は、部分的にアウトソーシングしてリソースを確保するケースも多い。「アウトソーシング」の導入事例
●すかいらーくホールディングス
約10万人の従業員を抱える飲食業界大手のすかいらーくは、パート・アルバイト採用の応募受付体制をアウトソーシングすることで、採用活動の円滑化している。月間で1万~2万件に及ぶパート・アルバイトの応募があり、以前は面接日程の調整をするだけでもひと苦労だったが、パーソルグループと共同で採用管理システムを活用し、電話やWebからの応募受付、面接設定の調整、応募者情報の管理などを一括で委託したことで、応募から採用までの期間を大幅に短縮することに成功した。これにより応募者に辞退されるような機会損失を防げるようになった。●全日空商事
全日空商事では、バックオフィス業務において定期的な処理業務の時間をとられ、従業員が企画・立案・調整などのコア業務に集中できていないという課題を抱えていた。そこで、社内で行うべき業務とアウトソーシングできる業務の整理を行い、給与振り込みや住民税納付の業務を芙蓉アウトソーシング&コンサルティングに委託したことで、これまでの業務対応人数を3分の1に短縮し、従業員を担当のコア業務に集中させることに成功した。●メルカリ
メルカリの人事部門は、アウトソーシングによりITシステムを有効活用し、業務効率化を果たしている。アウトソーシング導入以前は採用管理に表計算ソフトを使って運用していたが、多大な工数が割かれ、企画などに手が回らないなどの課題があったという。そこで採用管理の業務をトライアンフに委託したところ、質の高い管理が可能となり、またサーベイ運用の効率化と標準化を進めることができた。グループ会社のメルペイでは、月に40時間かかっていたサーベイの運用業務の時間を、約5時間に短縮することにも成功したという。まとめ
「アウトソーシング」を活用することで、業務効率化やコスト削減、社内リソースのコア業務への集中を図ることができるだけでなく、専門知識や高度な技術の提供を受けることができる。人事部門においても給与計算や勤怠管理など定型化した業務を外部に委託することで、より高度な採用戦略の計画や社員育成に注力できるだろう。ただしアウトソーシングを導入する際には、課題の明確化、コア業務とノンコア業務の整理、コストの比較などが重要となってくる。メリットとデメリットをしっかりと理解したうえで検討したい。よくある質問
●「アウトソーシング」を活用するメリットは?
「アウトソーシング」を活用することで、社員がコア業務に集中でき、企業の生産性や競争力の向上が図れ、またコスト削減や品質の向上にもつながる。さらに自社では対応できないような高度なスキルや専門的な知識が必要な業務でも効率的に対応することができる。●「アウトソーシング」を活用するデメリットは?
「アウトソーシング」を活用することによるデメリットとして、委託先の業務把握が大変なことや自社にはノウハウが蓄積されないこと、情報漏えいのリスクがあること、時間や労力を考慮しないとかえってコストや手間がかかるケースもある点などが挙がる。- 1