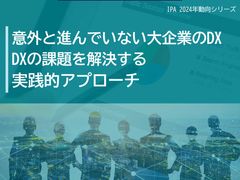いま求められている「DX人材」に必要なスキルやマインドセットとは?
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、ITを用いて日常の業務を効率化することだけを指す言葉ではない。デジタル技術の活用によってビジネス全般の変革を組織的に進め、競争力の向上を目指すことがDX本来の意味合いといえる。たとえば独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、各種レポートの中で、「DX人材」を以下のように分類している。
(1)プロデューサー……DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー格の人材
(2)ビジネスデザイナー……DXやデジタルビジネスの企画・立案・推進などを担う人材
(3)アーキテクト……DXやデジタルビジネスに関するシステムを設計できる人材
(4)データサイエンティスト/AIエンジニア……DXに関するデジタル技術(AI・IoTなど)やデータ解析に精通した人材
(5)UXデザイナー……DXやデジタルビジネスに関するシステムのユーザー向けデザインを担当する人材
(6)エンジニア/プログラマー……デジタルシステムの実装やインフラ構築などを担う人材
以上6つの職種がチームとして機能することで、はじめてDXは実現する、というわけである。
当然、これら「DX人材」には、IT関連の基礎知識、AIやIoTなど新しいデジタル技術に対する情報収集力、統計学の素養、データ分析力などが求められることになる。また現在と将来のビジネス環境や自社の事業ノウハウを総合的・俯瞰的に把握し、DXを計画的に推進していくマネジメント能力も重要だ。ユーザーが満足あるいはワクワクするような、ユーザーエクスペリエンスを意識したシステムやサービスを考案・構築できるセンスも持っていたい。
こうしたスキルに加えて、下記のような常に考えを巡らせる柔軟な発想力、探求心と好奇心を持ち、挑戦を続けていくマインドセットも重要となる。
・現代社会において解決すべき課題は何か
・その課題は自社のビジネスを発展させることで解決できないか
・そのためにはどのような技術やシステムが必要となるか、あるいは他業種・他社と協働できる可能性はないか など
「DX人材」を社内で育成するメリットとは?
現在、「DX人材」を外部から獲得する難しさゆえ、社内で育成する必要性が生じている。長期的な取り組みが必要となるが、「DX人材」の社内育成には下記のように多くのメリットもある。●自社の事業内容や業務にとって最適なシステムを構築可能
自社の事業内容や既存システムの問題点を熟知しているのは社員だ。DXによる機能改善策、付加価値をプラスして新たな事業へと発展させられる可能性なども、自社の社員だからこそ迅速に判断できる。●システムの一貫性を保つことが可能
システム開発をはじめとするDXの推進を外部ベンダーに委託した場合、意思疎通に時間がかかったり、勘違いや齟齬が生じたりする可能性もある。その結果、不十分なシステムとなってしまったり、複数のシステム同士の互換性に問題が発生したりすることも考えられる。一方、自社内の「DX人材」が企画・開発から実際の運用まで手がけることができれば、社内システムすべてについて一貫性を保つことが可能だ。機能の改善やトラブルへの対応も迅速に進めることができる。コストの面でも外部委託と比べて有利といえるだろう。
「DX人材」を育成するうえでのポイント
「DX人材」を育成する際には、以下のような各点を考慮することが重要となる。●対象者の選定
「DX人材」に必要となる知識やスキルに加え、自社の業務や問題点に対する意識の高さ、探求心、柔軟な発想力を持っている者であることが育成対象の条件となるだろう。組織的なDX推進のためには、リーダーシップやコミュニケーション能力も必須だ。さらに、特定の部門・部署・階級だけに限らず、社内から幅広く人材を集めることが望ましい。それぞれ異なる経験・知見を持つ者がDXに取り組むことで、シナジーが生まれ、新たなビジネスモデルの創出や課題解決につながることが期待できるからだ。
●DX専任の配置・配属
組織的・計画的・長期的にDXを推進しようと思えば、通常業務との兼任では困難を極める。担当者はDX専任とすべきだろう。“DXのための専任チーム”を作ることで、取り組みの本気度を社内外にアピールすることもできる。●知識・技術を習得するための環境整備
「DX人材」を育成していくうえでは、IT関連の基礎知識や先端デジタル技術について系統だって学べる各種研修・講義、eラーニング、学習管理システム、資格取得のサポート体制などの整備が不可欠となる。●アジャイル開発
はじめから大きなDXプロジェクトを動かすのではなく、「アジャイル開発」を採用することがベターだ。大雑把にいえば「システムを小さな機能単位に分け、短い間隔でアジャイル(素早い)に一つずつリリースしていく」という手法である。仕様変更・機能改善・軌道修正に対応しやすいのが「アジャイル開発」の利点。また小さな機能を完成させるサイクルを繰り返すことで、「DX人材」が成功体験を積み重ねやすいメリットもある。
●「DX人材」育成過程の可視化と成功体験・失敗体験の共有
社内で「DX人材」がどのように育ち、どのような成果をあげているのか、その進捗状況は全従業員が確認できるようにしておくべきである。「DX人材」の充実と体制の強化、成功体験の積み重ねが可視化されれば、DX推進にかける全社的なモチベーションやリテラシーは向上し、次のイノベーションにもつながるだろう。仮に一つの試みが失敗したとしても、その経験と反省からより良いアイディアが生まれることも多い。「新しい挑戦だから失敗もありうる」ことを前提に、失敗体験もまた全社的に許容・共有できる風土作りに取り組みたい。
●OJTの機会確保
DX推進が軌道に乗った後は、新人をチームに配属したい。研修・講義などの座学も重要だが、現場での経験を通じてのみ得られる知見やマインドセットもあるからだ。当然、採用の段階から「DX人材」育成を意識した選考が必要となる。「DX人材」育成に取り組む企業事例
ここでは「DX人材」の育成について、積極的に取り組んでいる企業をいくつか見ていこう。●日清食品ホールディングス
同社ではまず、改修・機能追加の繰り返しによって複雑化した既存システムを8割以上も削減し、メインフレームも撤廃。結果、システム運用・保守経費の削減、担当部門の負荷軽減、新たに創出した時間を利用してのIT戦略立案・技術活用、残業時間削減や有給休暇の取得増加などを実現した。そのうえで新たなデジタル技術の活用に取り組み、ワークフローのペーパーレス化、オンライン会議の導入、問い合わせに対応するチャットbotの導入などを進めている。また、これまで人の手で行っていた検査や資材の移動をロボットによって自動化した「次世代型スマートファクトリー」の運用、食事・医療・運動のデータを連携させた「スマートシティ」構想など、より大きな規模でのDXも推進中だ。
同社がDXにおいて特に注力したのがシステム開発の内製化だ。コードを書かずにアプリケーションを開発できる「ローコード開発ツール」を採用し、情報システム部門だけでなく事業部門が必要なアプリケーションを自ら開発できる環境を構築。すでに多くのアプリケーションが実用化され、現在も日々追加されているという。「小さな機能の開発を繰り返して成功体験を積む」ことが実践されており、「DX人材」の育成と現場レベルでのDX推進が両立されているといえる。
●ソフトバンク
同社ではDXの目的として社会課題の解決やSDGsの達成を掲げている。実際の取り組みは社外との協働で進められることが多く、福岡市で導入されたオンライン健康医療相談サービス『HELPO』、日本通運との協力で生まれたデジタル化配送システムなどをリリースしてきた。東急不動産とともに手がける『スマートシティ竹芝』では、AIカメラやセンサーによる混雑状況の検知・分析、ロボットによる商品配送などを実現している。こうした取り組みの中核を担うのが、2017年に発足したDX本部である。DX本部に集められたのは、主に営業や企画分野で活躍していた人材、120名。市場ニーズの察知力、外部との交渉スキル、売上やコストへの意識、柔軟な思考力といったスキルとマインドセットの持ち主たちである。もちろん、DXに必要な知識について検討し、研修も実施。現在も「DX人材」像の再整理とさらなる研修などに取り組んでいる。
●ダイキン工業
付加価値の高い製品作り・サービスの創造にはAIやIoTの活用が不可欠。そう考えた同社は、2017年、大阪大学の協力を得て社内講座『ダイキン情報技術大学(DICT)』を創設した。AIの導入で社内課題解決への筋道を描く「AI技術開発人材」、実際にAIのシステムを開発する「システム開発人材」、AIを活用した新たな事業展開を企画できる「AI活用人材」の育成がDICTの目的。選抜された社員を対象とする「AI活用講座(管理職対象)」、「AI技術開発講座」、「システム開発講座」、新入社員を対象とする「AI・IoT人材育成講座」、全従業員のAIリテラシー向上を図る「AI活用講座」が実施されている。
新入社員については、毎年100人が2年間DICTでの研修に専念(1年目は専門知識の習得と自社のコア技術学習、2年目は実際の現場で演習)するという、中期的・本格的な体制で進められている。
●みずほフィナンシャルグループ
同社では社員個々のデジタルリテラシー向上を全社的な課題として位置づけ、デジタルイノベーション部を設立、各種施策に取り組んでいる。ユニークなのは、社員のデジタルリテラシーを3段階に分けた点だ。すなわち、環境変化に対する危機意識やデジタル化の必要性・重要性を認識する「覚醒段階」、IT・デジタルの基礎用語や適用事例などを学びツール利用の前提知識を獲得する「基礎知識習得段階」、RPAの活用やデータ分析、機械学習の利用など、職場課題の解決に貢献する「実践段階」である。
オンライン学習やOJTなどのプログラムは、各段階に応じて提供している。デジタルリテラシーは個人差が大きい。そのため、それぞれのレベルに応じて幅広い学習コンテンツから選択できる大規模公開型オンライン講座『Udemy』を活用している。130,000ものオンラインビデオコースを選ぶことができ、効果的な学習が可能だ。
また外部企業との協働によって最先端の知見を得る取り組みにも積極的で、日本IBMとともに「〈みずほ〉×IBMデジタルカンファレンス」を開催。紙書類の入力業務をAIやOCR(文字認識技術)によって自動化するシステム『The AOR』をベンチャーキャピタルと共同で開発している。
「DX人材」の育成は、学習と実践の両輪で進めたい
企業事例として紹介した各社の取り組みからもわかる通り、DXの先進企業は、研修などによって「DX人材」を育成しているだけではない。実際に新規事業を動かす、あるいは社内での課題解決を進めるなど、成長途上の人材やスキルを身につけた社員が実際に能力を発揮できる場も同時に整備している。学習と実践の双方によって「DX人材」を育てる手法を採っているわけだ。経済産業省では、デジタル技術を活用してビジネスモデルや経営の変革に取り組む上場会社を『DX銘柄』、『DX注目企業』として選定している。ここで紹介した企業以外にも、DXそのものの推進と「DX人材」の育成を同時に推進している企業が数多く紹介されているので、参考にしていただきたい。
- 1