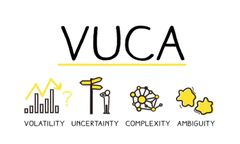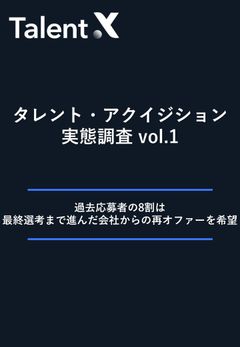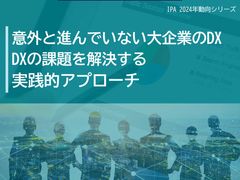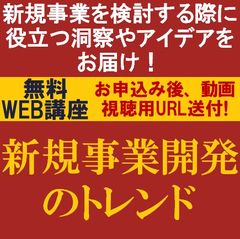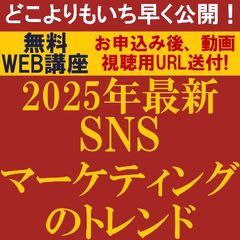▶本シリーズのバックナンバーはこちらからスタートアップ人事向け指南書――“大企業出身者”の活躍支援【連載】

転職者が最初の仕事としてシステム導入・移管を先導したい理由とは
以前はどのようなシステムやソフトウェアでも、導入時の初期費用に最低でも数十万はかかるのが普通でした。システムを導入するとなれば決裁がすぐ下りるものではありませんでした。しかし、昨今の導入時の初期費用が抑えられているクラウドサービスやソフトウェアでは社内決裁も下りやすくなりました。そういった変化もあり、転職者の中には最初の実績作りとして、業務効率化や社内DXを提案する人もいます。俗っぽく言ってしまうと、DXやシステム更改に関わることで「手早く実績を作りたい」という思惑もあるように見受けます。転職者はまず社内の人間関係を築きながら、その会社特有のルールや業務の進め方に慣れることから始め、ようやく実績を作るための準備が整います。しかし、転職者には新しい風を吹き入れてもらいたいと社内の期待が大きい場合など、AIやデジタル技術を活用した業務効率化に転職者が始めから関わることもあります。外部ベンダーと協力することで、短期間での成果も作りやすく、転職者の実績作りとしては人気の業務でしょう。また、大企業出身者にとっては「自分がリーダーシップを取りやすい」業務でもあります。
スタートアップ企業でシステム導入、システム移管が失敗するケース
ところが、同時に多くの会社で悲劇を生んでいる原因にもなっています。実際にどのような悲劇が起きているのでしょうか。1.システム導入・システム移管中に退職してしまう
勢い勇んで入社後すぐにシステム業者を呼んで見積・発注検討と順調に進めば、入社して1~2か月後にはプロジェクトがスタートします。先述したように、クラウドサービスは初期コストが低く、導入にかかる時間も短いのが一般的です。企業規模が小さく、標準的な仕様なら運用面のランニングコストも低く設定されているため、システム導入のハードルが下がるように感じられるものです。社長も「今度入社した大企業出身者は仕事が早い」と喜ぶことでしょう。
ところが私が見たケースでは、その転職者が社内の人間関係でトラブルを起こし、試用期間の3カ月で辞めてしまったということがありました。会社としては「あなたがシステムを発注したのだから、せめて導入が終わって稼働を確かめてから辞めて欲しい」とお願いしても「試用期間中なのですみません」と、あっさり辞めてしまったようです。仕方なく既存の社員で引き継いで導入をしたようですが、もし引継ぐことができなければ、違約金を払ってキャンセルするということになってしまいます。
2.会社が将来行う事業を想定せずにシステムを導入してしまう
スタートアップ企業のビジネスは常に流動的ですので、3年後、5年後に、今とは違う形態の新規事業を数多く始めている可能性があります。そのため、システム導入の際は、そこまで考えて、できるだけどのような事業を今後初めても網羅できるシステム導入を考えるのが一般的です。ところがスタートアップ企業に慣れていないとそのような発想に至らず、既存の事業だけをベースにシステム導入をしてしまうということがあります。1年後に全く新しい事業を始めることになった際、その事業にシステムが対応できない場合、また新たなシステムを導入しなければならず、お金もかかり、システム導入のための対応も手間になります。その繰り返しで4つも5つも違う会社のクラウドのソフトウェアが乱立することになり、逆に業務が非効率になります。
3.大幅な予算オーバー
大企業はシステム導入の予算がある程度確保されていますが、スタートアップ企業は、そこまで予算がふんだんに使えません。「あの機能もこの機能もないよりあったほうがいい」と大企業のような体制を構築しようとして大幅に予算オーバーをしてしまい、社長が困惑しているケースがあります。
4.システムを実際に操作する人達への配慮の問題
スタートアップ企業は、さまざまなバックボーンの方が在籍しています。「専門分野のプロ」の人も多いので、その分野の業務に関しては一流ですが、社員研修を受けたことがない、WordやExcelも使ったことがないという人も一定数います。そのため「あらゆるバックボーンの人達でも直感的に操作できる」ことを前提にしてソフトウェアを選定するのが一般的です。それを配慮せず「自分はわかるから」「自分は操作しやすいから」という自分だけの視点で導入してしまえば、稼働後に「操作が難し過ぎてわかりにくい」といったクレームが現場から届くことがあります。
スタートアップ企業のソフトウェア選定で気を付けるポイント
私がスタートアップ企業をお手伝いする時、ソフトウェアの選定では必ず以下の3つを気を付けて確認します。【1】ソフトウェア会社自体の経営状態
経営が順調でない場合、投資家などからの促しで定額利用料が後に爆上がりするリスクもあります
【2】ソフトウェア会社がアフターサービスをきちんと提供できる体制にあるか
スタートアップ企業は社内人材がまだ潤沢でないため、外部からのサポートがあるほうが助かります。
【3】現場担当者が直感的に入力しやすい操作性か
候補選定時や無料トライアル時に現場社員の率直な意見を聞きます
これらのことを確認した上で、その会社が求めていることができるソフトウェアかをチェックします。
大企業はお金も潤沢にあり、人材もたくさんいますが、スタートアップ企業はお金も人材も限りがあります。大企業出身者の方がシステムを導入しかけたまま辞めてしまい、後任で入社をした人が混線したコードの絡まりをほどくように、乱立するシステムを整理するのにご苦労されているケースを何回も見てきました。
人事担当者の方は、システム導入やシステム移管に関しては、このようなリスクがあることを経営陣や各部門の管理職に伝え、このような悲劇が起こらないように啓蒙していただきたいと思います。
- 1