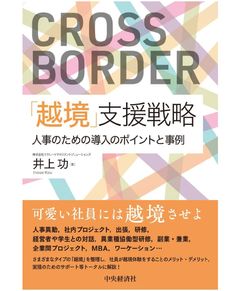ジョブ型や成果主義人事へのメタファーなき誤った理解、歪んだ解釈
「日本型雇用の限界とジョブ型雇用への転換」といった記事が、メディアで連日のように取り上げられている。しかし、残念ながら人的資源管理を十分に理解していない記者などが、ジョブ型や成果主義人事への移行機運に乗ったカタチで論じているケースが散見される。取り上げるとキリがないが、象徴的な記事がある。たとえば「トヨタ自動車が定昇ゼロへ。成果主義が強まりジョブ型雇用が加速する」という主旨内容の記事。確かに年功型が取り払われ、成果重視の評価制度や報酬制度へと、より加速するのは間違いないが、トヨタ自動車はこれまで成果主義でなかったといえばそんなことはなく、評価面では成果主義であった。報酬面ではそこまで反映されていなかったというのが正解である。それよりも大きな誤謬は、定期昇給ゼロがジョブ型を促進するかどうかは別の話である。実際に、トヨタ自動車はジョブ型ではなく、これまで典型的なメンバーシップ型であった。
トヨタ自動車は、人材マネジメントの理念として「モノづくりは人づくり」を掲げている。業務を通じたOJTや人事異動を人材育成の有効な機会ととらえ、人間性の尊重を重視した中長期的な視点で人材を育てるマネジメントを徹底して貫いてきた、象徴的な「メンバーシップ型企業」であり、時価総額が国内トップのグローバル企業である。豊田章男社長は自社におけるジョブ型雇用転換の必要性に関して、これまで一度も触れていない。
しかし今、日本企業は、これまでの日本型雇用からの脱却が求められている。その理由や背景を歴史的に考察することで、欧米型ジョブ型雇用とは異なる「新しい日本型雇用」の姿が見えてくる(下図)。
図:歴史的に考察する人的資源管理

「職務定義書」で仕事を明確に定義し、それにひもづけて報酬を決めるというジョブ型は、確かに客観的で明示的でわかりやすい。しかし、いざ運用ベースとなると、環境変化で仕事の中身も刻々と変化するため、定義書をいちいち書き換えなければならない。細かく規定しているので修正は煩雑となる。そのうち、メンテナスしなくなり形骸化する。結果的に、評価や処遇への納得感が落ちていく。つまり、つくりとしての「明瞭性」と、運用における「納得性」とはまったく別物であり、盲信的にジョブ型に走るとかつての成果主義人事の二の舞を演じる結果となる。
話を戻すと、「ジョブ型雇用」への転換は、実は戦後から沸き起こっていたことで、今回の動きが経団連からの発信を契機ににわかにザワツキはじめた第4フェーズにあることを知れば、論点は自ずと異なり、誤った記事を書くこともないはずである。
なぜ、これまでジョブ型が定着しなかったか。本当にメンバーシップ型はグローバルで通用しなくなり、日本企業がジョブ型に移行するのか。このことを推察するためにも、やはり「縦横2軸(※)のメタファー」で読み解く必要がある。まずは、「時間軸(横軸)」である歴史的変遷から見てみよう。
※「縦横2軸」:コラム【第1回】「地殻変動をメタファーでとらえる」参照
ジョブ起点の科学的管理法
今起きている現象について、「古典理論」をひもとくことで見えてくることがある。たとえば、100年前に立ち戻って系譜を見てみると、ジョブ型とメンバーシップ型に関する原点を垣間見るような源流がある。1900年代初頭に行われた実験を語る上で欠かすことのできない功績を残した、テイラーの「科学的管理法」と、メイヨーの「ホーソン実験」である。なお、この2つの対比による考察には、やや論理的飛躍が認められるものの、構造を理解するためには明快であるため、あえて引用することとする。まず、テイラーの「科学的管理法」について説明しよう。19世紀の英国の産業革命から遅れること100年、当時の米国では、成り行き経営や組織的怠業などから、労使対立や相互不信感などが発生し、問題となっていた。そこでテイラーは、効率的な作業方法を決めて教え、どれだけできれば評価に値するかを測定し、その上で作業効率に応じて賃金を決めるといった体系をつくりあげた。のちに「テイラーイズム」といわれ、現代の経営管理論・生産管理論の基礎のひとつにもなっている。
具体的には、課業(タスク)をベースに労働者が1日に達成すべき「標準作業量」を決め、この課業を客観的に設定するため、作業工程を細分化。各動作にかかる時間をストップウォッチで計測し、標準的な時間を割り出す「時間研究」という技法を考案し、課業管理をおこなった。そして、それまで現場に任せていた指揮・監督を、計画と執行に分離して新たに計画管理の部署をつくり、「職種別組織」を構築した。これが今日に至るまで、課業を起点としたジョブ型の原型となっている。
しかしこの技法は、労働者を、命令を受けて作業するだけの機械のように扱っているとされ、心理学や社会学の見地からの考察もなく、人権侵害につながるとして、多くの人から批判を受けてしまった。その後、メイヨーが組織で働く労働者の心理的側面の重要性を証明し、経営における「人の発見」を遂げる。これが「ホーソン実験」である。
ヒト起点の「ホーソン実験」
ハーバード大学とMITの研究チームを率いるメイヨーが、ウェスタンエレクトリック社の工場生産性の向上のために行った実験では、ネジを巻いたり、ボルトを締めたりする動作の効率性や、照明を明るくしたり暗くしたり、室温を上げたり下げたり、といった労働環境に目を向けていたテイラー型の合理的な生産管理法ではなく、選抜された人(6人のエース級の女工)は選ばれたことに誇りを持ち、作業者同士で協力し合い、自由裁量をもって時間を忘れて取り組むことで生産性が大きく変わることが実証された。テイラーがタスクベースで「生産プロセスの合理化」を図り、ファヨールが「経営の機能」を体系化。メイヨーが組織で働く労働者の「心理的側面の重要性」を証明し、経営における「ヒトの発見」を遂げたことで、バーナードの「組織論」に発展。こうして、近代的な経営学の土台が築かれ、人的資源管理に欠かすことのできない「古典理論」となった。
人的資源管理の観点から上述の話を眺めてみると、テイラーの科学的管理法は生産性向上という課題に対し、タスクやジョブの分析というアプローチから解を導き出した。現在取り上げられているジョブ型の前提は職務の定義が起点となり、その職務において個々人が最大成果を上げることが求められ、その結果によって報酬が決まってくる。
そういった意味では「成果主義的ジョブ型」である。一方で、メイヨーのホーソン実験から得られた示唆は、細かな仕事や職場環境分析だけで生産性を上げることの限界を知り、タスクやジョブを担う「ヒト」そのものを起点に、生産性の向上を図るべきだという点にある。欧米型に見られる「仕事にヒトが就くか」と、日本型に見られる「ヒトに仕事が就くか」との対比と、構造は同じである。どちらが起点でも、生産性向上はプロセスにおけるマネジメントの問題であるとも言えるが、100年前にも現在と同様の二元論が存在していたことは興味深い。
Google「アリストテレス」研究の源流にも古典理論がある
なお、古典理論研究に源流を見る現象は、他にも多数ある。Googleが、生産性の高いチームがもつ共通点を発見するために、2012年に調査を開始した「プロジェクト・アリストテレス」。何百万ドルもの資金と約4年の歳月を費やした結果、「心理的安全性」が労働生産性を高める重要な要素であると結論づけた。これも、1980年代にさかのぼると、米国の集団凝集性の研究に詳しいスタンリー・シーショアの実験によって、「凝集性の高い集団」は「低い集団」よりも仕事における不安や緊張感が少ない、と結論づけられていた。テイラー、メイヨー、シーショアらのいずれの研究でも、当時、用いていたのはストップウォッチなどのアナログなツールであったのが、現代では、統計解析ツールといった最新のデジタルツールに置き換わっただけで、その源流には、変わらない研究目的がある。こうした点も、人的資源管理の不変性が高いゆえんである。
ジョブ型導入の判断基準となる「戦略」、「組織」、「人材」の3要素
以上、これまで、主に「時間軸(横軸)」である歴史的変遷から日本型雇用の特徴を見てきた。メンバーシップ型に馴染んできた日本企業が、すべからくジョブ型転換の道に進むことは、必然的なのだろうか。最近、当社にも企業人事から、「ジョブ型雇用に自社も転換するべきかどうか」、あるいは「すでにジョブ型にしているが、どこまでをゴールとすべきか」という相談を頻繁にいただくようになった。そこで、導入可否の検証のために整理したマトリクスも用意しているのだが、相談を受けるたび、いつも懸念されることが、「企業人事側が、自社の事業戦略実現に向けた人材戦略・人事戦略というものを描ききれていないのでは……」ということである。戦略的人的資源管理論に立脚するなら、ジョブ型が自社に適しているか否かは前述の「戦略」、「組織」、「人材」という3つの要素で判断する。まずはじめに、自社の事業戦略の方向性との適合性を見る。たとえば、売上の多くが海外のもので、海外拠点も多くローカルスタッフを抱えており、マネジメントする上で日本型人事制度では評価や報酬の仕組みが理解されない。そこで、次に海外事業を推進させるために人事制度を改定するといった組織の仕組みや構造を変える。そして最後に、その事業戦略や組織を動かす人材の採用、育成、適正配置に取り組む……という具合だ。
最終回である第3回目は、このような戦略、組織、人材を構成要素とする「空間軸(縦軸)」で、ジョブ型雇用移行に関する考察をしていく。
※本記事は、パーソル総合研究所が2021年01月15日に掲載したコラムの転載です。
- 1