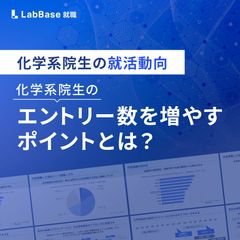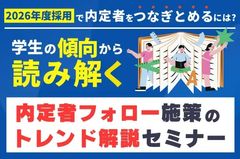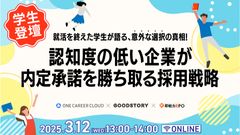圧倒的に「対面型」インターンシップを望む学生
学生が最も望ましいと考えているインターンシップについても尋ねました。まず、期間タイプ別では、最も多かったのは文系・理系ともに「2~3日程度」タイプで、それぞれ47%、38%となっています[図表15]。次いで、「1日」タイプ(文系28%、理系25%)が続きます。その次は文系と理系で異なっており、文系は「半日」タイプが20%で、「1週間程度」タイプはわずか4%、“2週間以上”タイプ(「2週間程度」「3週間~1カ月程度」「1カ月以上」の合計)はゼロでした。「1週間程度」以上のタイプばかりだと、より多くの企業のインターンシップに参加しづらいという思いがあるのでしょう。一方、理系は「半日」タイプ(9%)は1割に満たないのに対して、「1週間程度」タイプ(21%)が2割を超え、“2週間以上”タイプも6%あるなど、短期間の簡易的なものよりも日数をかけて実務を体験できるじっくりタイプのプログラムを求めている学生も多いようです。
![[図表15]最も望ましいインターンシップの期間タイプ](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4268_16_91VLZ6.png)
![[図表16]最も望ましいインターンシップの実施方法](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4268_17_P52VR1.png)
【対面型】
・社風が感じられる、一緒に取り組む就活生と関わりを持てるなど、オンラインより得られるものが多い(理系、東京都立大学大学院)
・社風を肌で体験できる(文系、立正大学)
・オンラインではできる活動が限られており、対面のほうが職業体験に効率的であると考える(文系、ソウル市立大学)
・実際に企業のスタッフと会って実施するほうがやりやすいし、交流も活発にできる(文系、早稲田大学)
・会社の雰囲気をより知ることができるし、集中しやすい(文系、慶應義塾大学)
・オンラインより雰囲気が分かりやすい(文系、名城大学)
・実際に赴いてみないと分からないことばかりだから(理系、九州大学)
・対面のほうが人事の方の人柄なども感じ取れる(文系、神奈川大学)
・採用面での優遇がありそう(理系、東京都市大学)
・実際に現場を見てみないとその会社の雰囲気が自分に合うかどうか分からない(理系、明治大学)
・空気感がよく分かる(理系、電気通信大学大学院)
・オンラインでは、会話の際に間の取り方などがかみ合わず、対面よりも余計な時間を費やすことが多い(文系、九州大学)
・社員の人柄を知りやすい(理系、新潟食料農業大学)
・コミュニケーションを活発に行うことができる(理系、同志社大学)
・オンラインでは入社後の想像ができない(文系、会津大学)
・現場の熱量は対面でしか味わえない(理系、九州工業大学)
【オンライン型】
・気軽に受けられる(理系、立命館大学)
・研究活動との両立がしやすい(理系、関西学院大学)
・気軽に参加できて交通費もかからない(理系、福島大学)
・移動やきちんとした身支度の必要がない(文系、一橋大学)
・事前準備が少なくて済む(会場の下調べや電車などの交通利用準備、感染対策など)(文系、帝塚山学院大学)
・自宅が遠方にあり,本社が都内にあると対面参加しづらい(理系、新潟大学)
・対面でしかできないことは少ない(文系、茨城大学)
・応募への心理的負担が減る(文系、金沢大学)
・地方在住なので、費用のかからない形がよい(文系、鹿児島大学)
【対面型とオンライン型の組み合わせ】
・対面だとその企業の雰囲気を知ることができ、オンラインは本社に行く時間を省ける(文系、帝京大学)
・なるべく対面で参加して直接お話を聞きたいが、遠いことが理由で参加できない場合があるため、オンラインも活用したい(理系、東京科学大学大学院)
・オンラインで手軽に参加しつつ、対面で職場の雰囲気をつかみたい(文系、中央大学)
・対面のみだと学業やアルバイトとの両立が難しい(文系、新潟大学)
・社内の雰囲気も知りたいが、遠方になると、交通費や時間がかなりかかるため、1日程度の対面があるとうれしい(理系、関西大学)
・忙しいので基本オンラインでよいが、現地の雰囲気も感じたい(理系、東京大学大学院)
・オンライン型では効率的に企業について知ることができつつ、対面型も直接出向いて雰囲気を肌で感じられるのがよい(理系、東京薬科大学)
・対面で雰囲気を、オンラインでは事業内容を知ればよいと思う(文系、立命館大学)
・状況に応じて参加しやすい方法で参加できる(文系、鳴門教育大学大学院)
次回は、「2026年新卒学生の就職活動動向調査(12月)」の結果から、面接や内々定の取得状況を取り上げます。