▼探す
▼情報収集する&学ぶ
- 人事ポータルサイト【HRpro】
- 連載・対談
- 連載・コラム一覧
- テーマ別研修
テーマ別研修の連載・コラム一覧
| フリーワード | 指定なし |
|---|---|
| ジャンル |
テーマ別研修
|
-
.png?w=500) “人が動く”コミュニケーション術
“人が動く”コミュニケーション術「苦手な部下」との接し方
あなたには「苦手な部下」がいるだろうか。「苦手な部下」と上手く仕事を進めるにはどうしたらよいだろうか。
2017/03/17
テーマ別研修 人事・労務全般・その他 -
.png?w=500) “人が動く”コミュニケーション術
“人が動く”コミュニケーション術「気が利く社員」の育て方
「ウチの若い社員は気が利かなくて困る」と悩んでいるリーダーは少なくない。それでは気が利く社員を育成するにはどうしたらよいのだろうか。
2017/01/11
テーマ別研修 人事・労務全般・その他 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「対人対応力が身につく」会議 (後編)
会議でケチツケ型が発言すると、一気に場の空気が悪くなったり、テンションが下がってしまいがちです。ケチツケ型が多い会議なら、批判の応酬合戦になり、議論は盛り上がっても中身は非生産的になります。
2017/01/11
テーマ別研修 組織風土 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「対人対応力が身につく」会議 (前編)
会議を『コミュニケーション能力を鍛える場』と考えましょう。会議の参加者をよく観察し、その対応策を学ぶことで、対人対応力を格段にアップさせることができるようになります。
2016/12/21
テーマ別研修 組織風土 -
 言葉がけの改善で、部下と組織を強くする
言葉がけの改善で、部下と組織を強くするポジティブな言葉がけで、能力を発揮しやすい状態を作る
最近、教育研修の分野で「リソースフル」という言葉が注目を集めています。リソースとは『資源』であり、人間について語る場合は、誰もが内に秘めている『能力』を『資源』に例えます。
2016/12/15
テーマ別研修 -
 NRIJ交渉ワンポイント
NRIJ交渉ワンポイント交渉で成果をあげるためには、絶対にしてはいけないこと!
ビジネス交渉は、相手と喧嘩するために行うものではありません。正論を言えば相手が必ず動いて協力してくれるのなら誰も苦労はしません。仲違(なかたがい)や喧嘩、係争、紛争もなくなります。私どもでは「交渉の成...
2016/12/14
テーマ別研修 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「実行力が高まる」会議
会議でいい感じで話がまとまると、それだけで満足してしまう人は案外多いようです。しかし、会議は新しいプロジェクトの始動や、日常業務の問題解決のためにするもので、会議をすること自体が目的ではないはずです。...
2016/12/07
テーマ別研修 組織風土 -
 理念浸透で成果があがる組織と低迷する組織の違い
理念浸透で成果があがる組織と低迷する組織の違い「物語」でチームにエネルギーをチャージする
やってもやっても求められ続ける業績。働く以上成果を出さなければならないことはわかっていても、時には「疲れた」と感じることもあるのではないでしょうか。経営者や管理職は、そのような気持ちをなかなか吐露しに...
2016/12/01
テーマ別研修 組織風土 -
 メンタリングで人や組織の可能性を引き出す
メンタリングで人や組織の可能性を引き出すしなやかで強い社員の輩出法~意識改革ではない。いまこそ“在り方改革”
10年後、あなたはどんな自分であり、どんな会社にいるのでしょう。わたしは高校1年生向けにキャリア授業も行っています。テーマは「25歳の自分創り」。彼らは10年後の自分を今描き始めています。ひとが成長し...
2016/11/18
テーマ別研修 -
 言葉がけの改善で、部下と組織を強くする
言葉がけの改善で、部下と組織を強くするシナリオを共有化し、組織の財産にする
上司が部下のモチベーションをアップするためには、ポジティブな発想で具体的にどうしたら良いのかを明確にして告げることが大切です。なぜなら、部下は成果に向けた行動が頭の中で明確になり、やる気が増すからであ...
2016/11/17
テーマ別研修 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「時間管理能力を高める」会議
会議になると、必ずと言っていいほど時間が不足してしまう……という経験をされている方は多いのでは?会議は、時間通り始まり、時間通り終わるのが基本です。
2016/11/16
テーマ別研修 組織風土 -
 NRIJ交渉ワンポイント
NRIJ交渉ワンポイントどんな相手も説得できる!交渉相手の「タイプ別」対応法
人間にはタイプがあります。それらの「特性」を理解し、相手のタイプに「対応」した話し方や説得をしないと、良い交渉成果は得られません。あなたの話し方は、あるタイプの人には好まれても、あるタイプの人には嫌わ...
2016/11/11
テーマ別研修 -
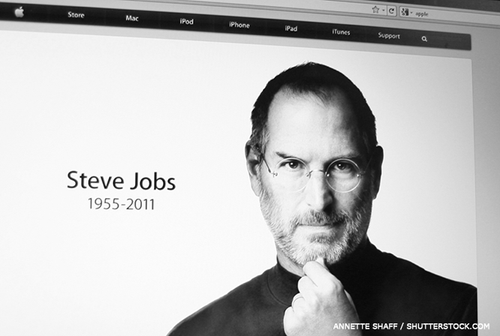 理念浸透で成果があがる組織と低迷する組織の違い
理念浸透で成果があがる組織と低迷する組織の違い瞬時に人を動かすリーダーに学ぶメッセージの伝え方
今回は、「コミュニケーション・ハンドブック」を制作した場合はより成果につながりやすくなり、ない場合でも意識的に取り組むことで、メンバーの意識や行動の変化を促す上で効果的な、リーダーの「伝え方」について...
2016/11/08
テーマ別研修 組織風土 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「プレゼンテーション力が向上される」会議
会議のやり方を工夫すれば、人数が多くても全員の意見をもれなく吸い上げることは可能です。『チーム分け』をするのです。1チーム5名以下が理想です。20名の参加者なら、5名×4チームができます。
2016/11/02
テーマ別研修 組織風土 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「決断力を向上させる」会議
会議で決定事項をまとめるとき、事例のように多数決をとる企業は多いでしょう。多数決はメンバーの意見をもっとも反映できるやり方ではありますが、「挙手」となると、内容を十分に吟味できなかったり、周りの目が気...
2016/10/19
テーマ別研修 組織風土 -
 NRIJ交渉ワンポイント
NRIJ交渉ワンポイント交渉相手は「敵」ではなく「パートナー」です
ビジネス交渉では、相手を「敵」と考えるのではなく「パートナー」として考えることが肝要です。それは「パートナー」であれば、お互いの利益をクレイム(奪い合う)のではなく、クリエイト(創造)するからです。お...
2016/10/17
テーマ別研修 -
 メンタリングで人や組織の可能性を引き出す
メンタリングで人や組織の可能性を引き出す社員だってやる気をもちたい! 真のやる気の源泉にアクセスするメンタリングとは
「わたしは一生懸命指導している。なぜ社員はやる気を出さないんだ。」仕事に情熱が感じられない。仕事や会社に無関心で淡々とした社員が多い。自ら仕事を創る社員少ない……。そんなとき、叱咤激励することもあるで...
2016/10/14
テーマ別研修 -
 言葉がけの改善で、部下と組織を強くする
言葉がけの改善で、部下と組織を強くする“して欲しい変換”を習慣づける
成果に結びつく言動や行動をしたいと望む場合、「できる」「そうなりたい」とポジティブな言葉で考えると、言葉が潜在意識に働きかけて発想が前向きになり、結果として上手くいく可能性が高まることを述べてきました...
2016/10/13
テーマ別研修 -
 会議の時間を有効活用する、“人財育成”
会議の時間を有効活用する、“人財育成”「リスク管理・危機管理力を向上させる」会議
物事には、2つの面が存在します。それは、メリットとデメリット。このデメリットが、“障害(マイナス)になりうる事項”です。なにかが起こってから対処していては、よけいに被害は大きくなります。何事も想定内に...
2016/10/05
テーマ別研修 組織風土 -
.png?w=500) “人が動く”コミュニケーション術
“人が動く”コミュニケーション術「年上の部下」との接し方
現在、リーダーの下に配属される部下は、必ずしも自分より年齢が若いとは限らなくなっている。「年上の部下」が増えてきている昨今、リーダーのコミュニケーションにはどのような注意が必要になるのだろうか。
2016/09/29
テーマ別研修 人事・労務全般・その他





