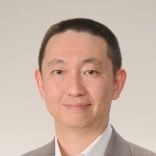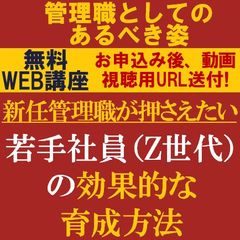土方歳三といえば司馬遼太郎氏の『燃えよ剣』。そう思われる方も多いだろう。昭和三十七年からおよそ二年かけて『週刊文春』に連載された作品は、それまで「悪役集団」とされていた新撰組のイメージをガラリと変え、幕末に志高く生きた一人の青年の人生をイキイキと描き切った。
今回は、半世紀もの間、人々に憧憬を抱かせ続けている同小説から見る「土方歳三」像から、行動理論を考察していきたい。
土方は、自らの信念に基づいて、徹底的に時流に抗い続けた。高度に目的的な機能集団「新撰組」を組織し、さまざまな戦術を駆使し、「己の羽」で飛び続けた。
滅びゆく幕藩体制と共に生き、共に去った「武士」の行動理論とは何だったのだろう。
農民から武士へ
豊玉(ほうぎょく)という雅号を持つ彼は、新選組「鬼の副長」として世に恐れられ、戊辰戦争では指揮官として軍才を発揮する。が、彼は武家の出ではない。
武蔵国多摩郡石田村(現在の東京都日野市)の「お大尽」とよばれる豪農の家に生まれた土方は、実家秘伝の「石田散薬」を売り歩きながら、各地の道場と他流試合を重ね、天然理心流剣術道場の試衛館で近藤勇と出会う。
この出会いをきっかけに新撰組「鬼の副長」としての激しい人生が始まるのである。
会津藩主京都守護職松平容保の配下として、京都の治安維持を担う新撰組を真の意味で「組織化」し、「壬生浪(みぶろ)」と呼ばれる鉄の統制集団を創り上げたのは土方の力によると言われている。
新撰組は、長州・薩摩と言った敵方のみならず、世のすべての人々から恐れられたが、その新撰組隊士は、土方を恐れ、そして憧れた。
慶応三(一八六七)年、幕臣に取り立てられるものの、同年大政奉還、王政復古の大号令が発せられるに至り、幕府は事実上崩壊するが、土方は軍備の洋式化を進める。
戊辰戦争では幕軍が官軍に追い詰められるなか、海軍副総裁だった榎本武揚を総裁とする「蝦夷共和国」が函館を拠点として成立すると、土方は陸軍奉行並、箱館市中取締、陸海軍裁判局頭取を兼ねた。
明治二(一八六九)年、新政府軍の箱館総攻撃が開始される。土方は長年死生を共にした新撰組と、出陣前夜酒を酌み交わした後、配置換えを行って、すべての隊士を己の配下からはずすのである。生き残らせるための措置であった。
その土方は、わずかな兵を率いて出陣するが、隊士全員が「新撰組として死ぬんだ」と付き従い、最後の戦いに参加する。
乱戦の中、銃弾に腹部を貫かれて絶命。享年三十五。
土方の人生において彼を評する言葉は「鬼」「冷酷」「戦上手」「喧嘩屋」など様々あるが、聡明、戦略的であり、学ぶ力の優れた人間であことは、西洋式軍備の基礎を書いた「歩兵心得」を一日で体得したことなどからも、間違いない。
蒸気船を自らの力で建造するだけでも大変な難行、ましてや海軍としての軍略構築についてはあまりにも稚拙であった当事の日本で、土方は自らアボルダージュ(接舷攻撃)を考案し、フランス海軍将校を驚かせたというエピソードは、土方の戦闘指揮官としての能力の高さをうかがわせる。
その土方ならば、時代の趨勢はわからないはずはない。仮に始めは見えていなかったとしても、鳥羽伏見の戦いにおいて大阪城から徳川慶喜、松平容保が味方を置いて逃げた時には、すべてが読めたはずである。
にも関わらず、なぜ彼は滅びに向かって戦い続けたのか?