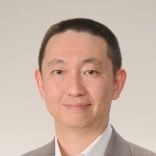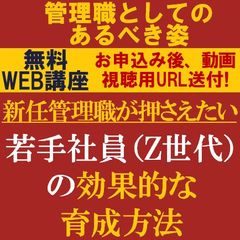武田勝頼は、信玄と諏訪御料人の間に生まれた。諏訪家は信玄がまだ晴信の名で呼ばれていたころ攻略した家であり、武田家家中では、諏訪御料人を側室に迎えることに強い反対があったといわれる。
高遠城城主に任じられ、諏訪四郎勝頼と名乗る彼は、諏訪氏を継ぐ人生のはずであった。

強すぎる武将
勝頼の武将としての技量は父である信玄から愛されていた。ただし、武田の当主としては別である。正確には信玄に認められていないのではなく、武田家家臣たちに認められていない。信玄自身は勝頼に武田を継がせることを考えていたが、それには時間がかかるとも見ていた。
しかし信玄の死は、信玄が考えていたよりも早い。長子義信が廃嫡され、1573年信玄の死により勝頼は家督を相続する。
武田家を継いだ勝頼は、その旧い体質に疑問を持っていた。武田家は信玄がその父から受け継ぎ、長い年月をかけて領地を広げ、その強さを創りだしてきた。当然家臣たちは皆、信玄と共に死地をくぐり抜け、その度に信玄との信頼関係をより堅固なものとしてきている。
しかし時代は常に流転する。世には新しい力が生まれ、戦の仕方も国の治め方も変化していく。勝頼が継いだとき、長い歴史があるがゆえに武田家は、すでに時代の流れから後れ始めていた。織田家の驚異的な勢力拡大を知る勝頼は、今の武田軍のままでは勝てないと見ている。
悲運を生んだ行動理論
勝頼には「強い武田家を存続させ、天下を治める。そのためにはすべての在り方を変えていかなければならない」というビジョンともいえる強い想いがある。そんな勝頼の言動に対し、信玄公の家臣達は「これまで培ってきたことを軽々しく破るなどあってはならない」「信玄公ならばそのようなことはしない」と従おうとしないのである。
勝頼の胸中には「彼らは父の家臣であり自分の家臣ではない(観)。ゆえに自分が何を言ったところで(因)耳を傾けることはないのであろう(因)。しょせん期待するだけ無駄である(心得モデル)」という行動理論が澱のように積もっていったことであろう。
この行動理論が彼の悲運の源となる。
人間の常として、家臣は主君の言動を見て自分たちの出方を決める。
勝頼が古参の家臣を信じ、武田家存続への強い想いと戦略を、あきらめることなく説き続けていれば、その知略と想いを理解し心の底から協力をする者が生まれてきたはずである。そしてそれは他の者へ波及し、「信玄公の家臣」は「勝頼の家臣」へと変わっていくのである。
が、世の変化の速さを知っていたがゆえに勝頼は焦燥する。「古参の家臣たちを納得させるには、結局信玄公以上の大きな戦果を出すしかない、そのためには今すぐに自分の言に耳を傾ける者が必要だ」と考え、次第に聴く耳を持っているかのような態度をとる者だけを近くに置くようになる。
勝頼は織田領美濃明智城陥落に成功する。さらに徳川領遠江へ侵攻、高天神城を落とし東遠江を制圧する。家康の拠点浜松城に迫る勢いであった。
だがその躍進は、結果として古参をさらに遠ざける方向に作用してしまった。
古参の家臣から見れば、「やはり勝頼はわれらを信頼しておらぬ。信玄公とはそこが違う。そのような将には忠義を尽くせない」という論理が成り立ってしまうからである。
連勝をいくら重ねても武田軍の信頼のほころびは止まらない。
しかしだからこそ勝頼は猛進する。一度でも立ち止まれば、織田・徳川へと中心を移しつつある時流に飲みこまれるからである。
1575年、長篠城へ向かう勝頼はすぐ落ちると考えていた。が、長篠城兵は予想以上の粘りを見せる。その粘りは信長が動く時間を創りだし、信長自らが出陣する。勝頼の目にはこれが千載一遇のチャンスと映った。ここで時代の寵児である信長を打てば、古参の自分への見方は変わるはずである。が、古参の重臣達は反対した。戦略的観点に立てば、長篠城を攻めるための陣営と戦力しか持たぬ以上、彼らの見解は正しい。重臣達の中には、勝頼と武田家を想い言葉を発している者達も多数いたのである。
しかし「彼らは父の家臣であり自分の家臣ではない(観)。ゆえに自分が何を言ったところで(因)耳を傾けることはないのであろう(因)。所詮期待するだけ無駄である(心得モデル)」という行動理論が勝頼の判断を間違わせた。
この戦いにおいて勝頼は織田・徳川連合軍に敗退。和平、同盟、新府城への府中移転など次々と手を打とうとするも、織田信長の侵攻の速さに勝ることかなわず、1582年天目山で自害した。
『甲陽軍鑑』には「強すぎる大将」と記されている。
- 1