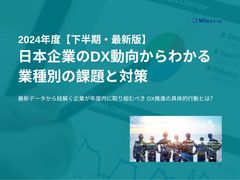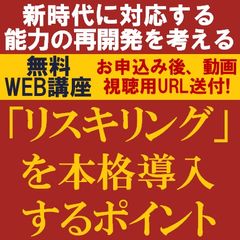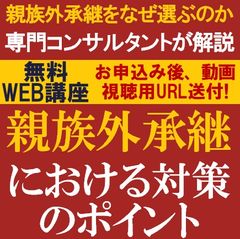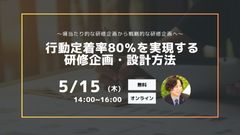「裁量」とは
まずは「裁量」の意味や権限との違い、また企業において「裁量」がどれだけ重要であるかなどを解説していこう。●「裁量」の意味
「裁量」とは、自分の考えに基づいて物事を判断し、決定・処理することを意味する。「裁量がある」というのは、上司からの細かい指示や命令を待つことなく、自分自身の判断で業務を進めたり、問題解決に取り組んだりする状態のことだ。「裁量」は立場に伴い大きくなるのが一般的で、責任範囲が広い役職者の方が、より大きな「裁量」を持つことになる。●「裁量」と権限の違い
権限は、“何かを行うための権力や権利の範囲”を指す言葉であるのに対し、「裁量」は“与えられた権限の中での判断や行動の自由度”を表す。言い換えると、権限は「何ができるか」の範囲を、裁量は「どのように行うか」の自由度を示すものである。●「裁量」の重要性
ビジネスにおける「裁量」は、意思決定のスピードに直結すると言える。現場の従業員に大きな「裁量」を与えることで、意思決定のプロセスが省略され、業務効率が向上するからだ。それだけでなく、従業員が自ら考えて決断する機会が増えることで、成長やモチベーション向上にもつながる。特に成果主義を採用している企業では、個人の「裁量」が大きい傾向があり、それが組織の競争力強化につながっているのだ。●ビジネスにおける「裁量」の使い方
ビジネスの場面では、意思決定の自由度を示す言葉として「裁量」が様々な形で使われている。具体的な例文を紹介していこう。・「このプロジェクトは君の裁量に任せるよ」(上司から部下に業務を任せる時)
・「部下に裁量を委ねることで成長を促す」(マネジメントの方針)
・「自分には裁量がないので、この件は上司に確認します」(交渉の場面)
・「管理職になれば裁量が広がる」(キャリアパスの説明)
・「経営判断は社長の裁量に委ねられている」(意思決定プロセスの説明)
「裁量権」の意味やメリットとデメリット
「裁量権」とは、自分の考えに基づいて物事を判断し、意思決定できる権利のことを指す。ビジネスシーンでは、人事の判断を下せる権利や、予算を自由に使うことができる権利を意味する。つまり「裁量権が大きい」ということは、自分で自由に決められる範囲が広いことを意味する。ただし「裁量権」が大きいことには、いくつかのメリットとデメリットがある。それぞれ詳しく見ていこう。
【裁量権が大きいメリット】
●決断の機会を積めて成長につながる
「裁量権」が大きい環境では、自分自身の判断で課題を解決し、プロジェクトを推進する責任を担うことになる。必然的に決断の機会は増えるため、判断力や意思決定力が養われ、若いうちから成長しやすい。多くの成功体験を積むことで自信を育むこともでき、仮に失敗したとしても、その経験から多くの学びを得て、ビジネスセンスを磨くことができる。●幅広い業務を経験できる
「裁量権」が大きいと、一つのプロジェクトの中でも、自分の判断で業務の進め方や取り組む課題を選択していくことになり、さまざまな業務に携わることができる。若手のうちから責任のある仕事を任せてもらい、幅広い業務を経験することで、キャリアパスの基盤が作れる。●やりがいを実感しやすい
自分の考えを直接仕事に反映させることができるため、やりがいを感じやすくなるのも、「裁量権」が大きいことのメリットだ。上司や周囲から行動を制限されることが少なくなるため、「自分の力で成し遂げた」という実感を得やすいのだ。また、自分の意見を上司や上層部に反映できる機会も増え、組織への貢献を実感しやすくもなる。【裁量権が大きいデメリット】
●責任が大きくストレスを感じやすい
「裁量権」が大きくなれば、それに比例して責任も大きくなる。自らの判断ミスが組織や他人に大きな影響をもたらしかねないシビアな状況にも直面するだろう。そのため、精神的な負担が大きくなり、重圧からストレスを感じることも増える。●業務量が増える
「裁量権」が大きいと、自分で判断して業務を進める必要があるため、意思決定のための情報収集や分析など、通常の業務に加えて行わなければならないタスクが増える。しかも、成果を出そうとして長時間労働になりがちなので、心身の疲労を貯めてしまいやすい。●待遇との整合性が取れない場合がある
「裁量権」が大きくなることで、給与や手当といった待遇面でも優遇されることが望ましい。しかし、仕事内容に見合った適切な給与形態が整っていない場合、「やっていることに対して、給与が低い」といった不満を感じ、仕事への意欲が下がってしまう恐れがある。「裁量」を持つために求められる能力
ビジネスにおいて「裁量」を持つためには、一定の能力が必要になってくる。具体的にどんな能力が求められるかを紹介していこう。●判断力
「裁量」を持つには、まずは上司の指示や命令がなくても目の前の業務を期待以上にこなすことができなければならない。つまり自分で状況を正確に把握し、迅速かつ最適な選択をする判断力が必要だ。素早く正確に判断を下すには、必要な情報を事前に準備しておくことが大切となる。●実績・経験
結果を出せない人には大きな「裁量」は与えられない。安定して結果を出せていたり、期待以上の結果を出せていたりすることで、「裁量」は広がっていくものだ。まず与えられた業務で確実に成果を上げて実績を作り、また失敗からも多くを学び、その経験を次の判断に活かすことで、より大きな裁量を任せてもらえるようになる。●主体性
「裁量」を持つには、主体性がなければならない。主体性とは自ら考え、責任を持って行動する姿勢のことである。上司からの指示を待たず自発的に業務改善や課題解決に取り組み、新しいアイデアを提案することで、組織に貢献する必要がある。●自己管理能力
「裁量」が大きければ大きいほど、自己管理能力が重要になってくる。自らの判断と責任で業務を進めるためには、自分自身の時間管理ができ、優先順位を付けて効率的に行動できなければならないからだ。特にテレワークなど自由度の高い環境では、周りの目がない中でも集中力を保つことが求められる。●リスク管理能力
意思決定には常にリスクが伴う。そのため「裁量」が大きくなるほど、リスク管理能力も問われる。組織全体への影響や起こり得る問題を想定しながら、物事を進めていかなければならない。万が一アクシデントが発生した場合に備えて、対応策を検討しておくことで、上司や周囲の人間に安心感を与え、より大きな「裁量」を与えてもらえるようになる。「裁量労働制」とは
「裁量労働制」は、実労働時間に関係なく、事前に決められた一定の時間を労働時間とみなし、その分の給与が支払われる雇用形態だ。例えば、8時間と定められていれば、実際の労働時間が短くても長くても8時間分の給与が支給される。裁量労働制では、労働者が自分で出退勤や残業、休日出勤などの勤務時間や業務の方法を決めることができる。「裁量労働制」とは? 残業代と労働時間の仕組みやメリット・デメリットを解説【24年4月改正】
●「裁量労働制」が適用される仕事
「裁量労働制」は「専門業務型裁量労働制」と「企業業務型裁量労働制」に分けられる。「専門業務型裁量労働制」とは、1988年に施行された制度で、研究・開発職やクリエイティブな職種、士業などの高度な専門性が要求される職種に対して適用される。厚生労働省が指定する業務としては、下記の19種である。■新商品や新技術の研究開発、人文科学または自然科学に関する研究業務
■情報処理システムの分析・設計業務
■編集の業務
■デザインの考案業務
■放送番組、映画等のプロデューサー、ディレクターの業務
■コピーライターの業務
■システムコンサルタントの業務
■インテリアコーディネーターの業務
■ゲーム用ソフトウェアの制作業務
■証券アナリストの業務
■金融商品の開発業務
■大学における教授研究の業務
■企業の合併・買収(M&A)の助言に携わる業務(2024年4月に追加)
■公認会計士の業務
■弁護士の業務
■建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
■不動産鑑定士の業務
■弁理士の業務
■税理士の業務
■中小企業診断士の業務
一方、「企業業務型裁量労働制」とは、2000年に施行された制度で、事業運営の企画や調査などの業務に従事する労働者に適用される。厚生労働省では下記のような8業務を挙げられている。
■経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
■経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
■人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
■人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
■財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務
■広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務
■営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
■生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務
「裁量労働制」の労働時間や残業代
「裁量労働制」では、労働者自身がすべての労働時間を決めることができる。出退勤、始業や終業時刻だけでなく、フレックスタイム制度におけるコアタイムもない。また、「裁量労働制」は、あらかじめ決められた労働時間分での給与が設定されている。そのため、時間外労働をしたとしても残業代が支給されることはないのが基本だ。ただし、労働基準法に基づく法定労働時間である「1日8時間、週40時間」を超えるみなし労働時間が設定されている場合、超過分については、基礎賃金の1.25倍に相当する賃金を含め、給与として支払われる必要がある。さらに、深夜や休日出勤の場合は手当の対象となる。深夜22時以降から翌日朝5時までの時間帯や法定休日の労働に対しては、深夜手当として基礎賃金の1.25倍、休日手当として基礎賃金の1.35倍の割増賃金がそれぞれ支払われることになる。
まとめ
「裁量」が大きい仕事では、多岐にわたる業務を自らの判断で進めることができるため、やりがいや働きやすさを感じやすい。ただし、責任も大きくなるので、プレッシャーやストレスも相応にかかり、成果を出すために自分に無理を強いる可能性もある。それが結果的に長時間労働につながることも多いだろう。メリット、デメリットがあること、さらには今、会社がどのようなステージにあるのかも踏まえ、効果的に「裁量」を付与するようにしたい。「マネジメント」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
よくある質問
●「裁量をもって」とはどういう意味?
「裁量をもって」とは、わかりやすく言うと「自分の判断や考えを使って」という意味になる。例えば、「担当者は裁量をもって予算配分を決定する」、「現場責任者は裁量をもって緊急時の対応を行う」などと使う。つまり、物事に対する決定権を持ち、自らの判断で行動する権限が与えられていることを意味する。●「自分の裁量で」の言い換えは?
「自分の裁量で」の言い換えとしては、「自分の判断で」、「自己の決定権で」、「自分の責任で」、「自らの権限で」、「自分の采配で」などが挙げられる。●「裁量が大きい」の使い方は?
「裁量が大きい」の使い方としては、以下のような例がある。・この役職は裁量が大きいため、自分のアイデアを形にしやすい
・新規プロジェクトでは裁量が大きいので、戦略から実行まで自由に決められる
- 1