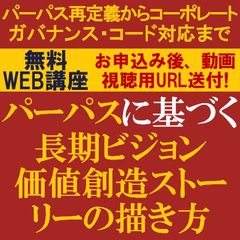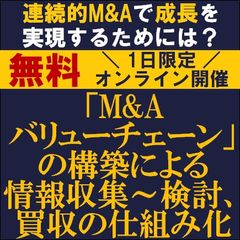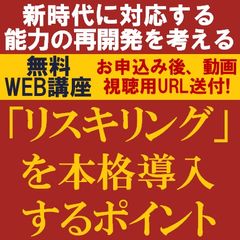かくいう私も、前職の大和ハウス工業でリーダーになって数年は、「自分でやった方が早い病」にかかっており、仕事を人に任せられない状態が続きました。しかし、そんな状態も長くは続かず、あるとき私はオーバーワークから倒れてしまったのです。病院でふと思いました。「自分1人で成果を上げ続けるのには限界がある。1人で大きな成果を求めるのではなく、チームで大きな成果を求める思考にならなければ」と改めて思い至ったのです。その経験は積水ハウスで伝説とされる業績を残したタカマツハウス代表の藤原から教わった「チームマネジメント」の大切さでもありました。
「落ちこぼれをつくらない組織」に向けて重要な考え方とは何か
落ちこぼれをつくらない組織のために導入しているのが「成約人率」という指標です。この「成約人率」とは、藤原が前職で実践し、当社にも導入したものです。成約人率とは、「全営業社員のうち、何人が成約できたか」を把握する指標です。一見すると「組織にいる人間がどの程度成果が上げられたか」すなわち「落ちこぼれを洗い出す」指標と思われるかもしれません。しかし、私達が導入した成約人率とはその指標ではありません。「全体の成約達成度を測るためのもの」です。すなわち、優秀な社員が何件も獲得したからと言って、成約人率は上がりません。成約人率を上げるためには、「成約できていない社員に案件を獲得してもらう」必要があるのです。全体の底上げをしなければ、成約人率は上がらない。言うなれば、「1人の100歩よりも100人の1歩、2歩を重視する考え方」なのです。
もちろん、できない営業社員を追い込むためのものではありません。落ちこぼれそうな営業社員がどうすれば成果が上げられるのか? みんなで考え、応援することで成果をつかみ取るのがこの成約人率の先にあるひとつのゴールです。実際、成約人率の向上を日頃から意識づけていったことで、社員の中に「大きな成果はチームや組織全体で上げるものだ」ということが全社員の共通認識になり、助け合うことが当たり前の組織になっていきました。こうしてみんなが活躍できる「落ちこぼれをつくらない組織」の土台ができあがっていったのです。
月初ではなく、月の半ばで振り返る場を設けると何が良いのか
もうひとつ、全体レベルの底上げをはかるため、当社では月次よりも更に短い月の半ばに成果を集計する中締めがあります。一般企業では、月次、四半期、半期、通期というように業績を数ヵ月単位で集計することが多いでしょう。しかし、これには大きな欠点があります。例えば1ヵ月単位で成果を捉えてしまうと、焦り出すのは20日あたり。そうなると残り稼働日数は1週間もなく、どんな施策も「手遅れ」状態になってしまいます。振り返る期間が短いことで、細かな軌道修正ができないのです。一方、月の半ばで中締めを行えば、月の前半の営業活動を振り返り、「何ができて、何ができなかったのか」を徹底的に検証することができます。また、後半の戦略戦術が練られていない社員には役員や本部長からアドバイスをもらうなど、早め早めの課題解決の施策を打つことができます。実際、アドバイスだけでは足りない場合は、上司や先輩が部下の営業に同行するといった具体的な行動をとることもあります。
上司や先輩社員は成果が上げられていない社員とコミュニケーションをとり、今、すべきことは何なのか、成果の上がっていないメンバーの立場になって考え、共に行動することでより適切なアドバイスも部下や後輩社員、同僚にできるでしょう。チームの総力をあげて応援し、月初めに定めた目標を必ずやりきるよう後半戦の戦い方を変えることが、中締めの目的なのです。
繰り返し述べていますが、落ちこぼれる社員は自ら落ちこぼれようとしているのではありません。自分一人の力ではどうしようもなくなって、落ちこぼれていくのです。成果が上げられていない社員は、何らかの問題を抱えて、悩んだり、困ったりして助けを必要としていると思います。組織としてできること、それは「助けが必要な社員の存在にいち早く気づき、手を差し伸べること」です。そうやって全体最適を目指していくことで、不幸な社員をなくすことができるのです。
- 1