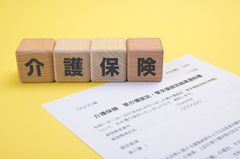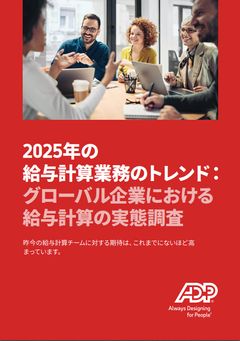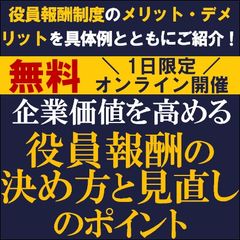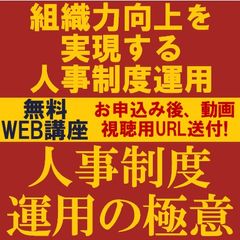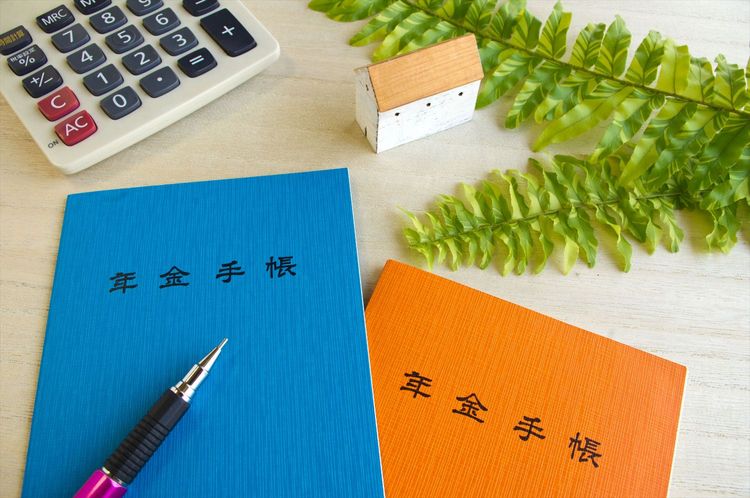
5年ごとに見直される年金制度
わが国の年金制度は将来的な継続可能性を確認するため、少なくとも5年ごとに財政状況をチェックする財政検証が行われる。国民年金や厚生年金のルールを規定する年金法の改正は、その結果を受けて実施されることになる。前回は2019年に財政検証が実施され、翌2020年に法改正が行われた。今回は昨年2024年7月3日に、財政検証の結果が厚生労働省から発表されている。そのため、本年2025年は年金法の新たな改正が見込まれているものだ。
今回の改正内容については、2022年10月から厚生労働省の社会保障審議会年金部会で、複数の有識者により繰り返し議論が行われてきた。その中ではさまざまな論点が検討対象に挙げられたが、そのうちのひとつに社会保険の適用拡大を一層進めるという案がある。
社会保険の加入対象者については、短時間労働者に対する適用範囲を2024年10月に被保険者数51人以上の企業にまで拡大するなどの施策が実施されたばかりである。それを更に見直そうという議論が行われてきたのである。
企業規模要件と賃金要件が見直し対象に
短時間労働者が厚生年金などに加入を義務付けられる条件にはいくつかの分類方法が考えられるが、一例を挙げると次の5要件が揃った場合とされている。●労働時間要件 … 週の所定労働時間が20時間以上であること
●賃金要件 … 賃金の月額が8.8万円以上であること
●雇用期間要件 … 2カ月を超える雇用の見込みがあること
●学生除外要件 … 学生でないこと
上記のうち企業規模要件と賃金要件の2要件については、社会保障審議会年金部会での議論の末、最終的に見直しの対象として指摘されるに至っている。
「被保険者数51人以上」は撤廃か
それでは、企業規模要件の見直し案から見ていこう。「被保険者数51人以上の企業に勤務すること」を求める短時間労働者の現状の適用要件は、撤廃をすることが改正案として有力なようである。つまり、被保険者数50人以下の企業で勤務するパートタイマーなども、他の要件を充足すれば社会保険への加入を義務付けるとする案である。
一定の短時間労働者に厚生年金などへの加入を義務付ける制度は、2016年10月に「被保険者数501 人以上の企業に勤務すること」という企業規模要件で開始された。ところが、企業規模要件は当初より当分の間の経過措置と位置付けられており、中・小規模事業所の負担を考慮して段階的に拡大を進めることとされてきた。そのため、「勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する」という観点から、今回の法改正では撤廃することが有力な案とされた経緯がある。
本要件が撤廃されると、厚生年金の被保険者数が50人以下の企業および同企業に勤務する短時間労働者の双方に対し、新たな保険料負担が発生することになる。そのため、現在の「51人以上」という要件を直ちに撤廃するのではなく、20人で区切るなどして段階的に撤廃に向かうべきなどの意見も出ているようである。
「賃金の月額が8.8万円以上」も将来的になくなる?
次に賃金要件である。「賃金の月額が8.8万円以上であること」を求める短時間労働者の適用要件についても、撤廃をする案が示されている。理由は、近年の最低賃金の引上げに伴い、労働時間要件を満たせば自動的に賃金要件を満たす地域が増加している点が挙げられている。ただし、現状では最低賃金で週20時間以上勤務したとしても、賃金の月額が8.8万円に満たない地域は多数存在する。そのため、賃金要件の早急な撤廃に踏み切った場合には、賃金月額が8.8万円未満の労働者が社会保険加入を強制されるケースも生じてしまう。そこで、「今後の最低賃金の動向を踏まえ、撤廃の時期に配慮すべきこと」などが示されている。
また、賃金要件にある「8.8万円」は、いわゆる「106 万円の壁」の根拠数値であり、多くの国民から就業調整の基準額と認識されている現状がある。そのような認識が生じている具体的金額を要件から除外し、賃金額に依拠した就業調整の発生を回避したいとの思惑もあるようである。
他にも、従業員数5人以上の個人事業所について、現状では社会保険の対象外とされている業種の事業を営んでいても適用対象とする案などが示されている。
対象となる事業所に一定の配慮措置も
上記法改正が実施された場合、新たに社会保険の対象とされた事業所が被る負担は、決して小さくない。経営資源の脆弱な中・小規模事業所にとり、事務負担や社会保険料コストの増大は経営上の致命傷にもなりかねないであろう。そこで、今回の法改正では企業経営に与えるマイナスの影響を踏まえ、経過措置や支援策による配慮を実施することも検討されているようである。具体的には、「準備期間を十分に確保すること」「積極的な周知・広報を行うこと」「事務手続きや経営に関する支援に総合的に取り組むこと」などが示されている。
最終的にどのような法案が国会に提出され、審議を経て成立をすることになるのか。中・小規模事業所の経営者および人事部門担当者はもちろん、そのような事業所と取引関係にある事業所にとっても注視すべき問題といえよう。
- 1