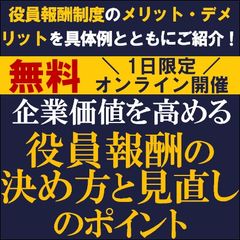労働時間の「適正な把握」からスタートしましょう
まず、使用者には従業員の労働時間を適正に把握する義務があります。具体的には、勤務日ごとの始業と終業の時刻をタイムカードなどで確認して記録することです。しかし、労務管理が出勤簿にハンコを押すだけといった制度の場合、それぞれの従業員がどれだけ働いたのか分からないことがあります。まして残業が発生した場合、その時間の把握が困難になる可能性が高くなってしまいます。もし、従業員が残業時間を自己申告する場合は、「自己申告による労働時間」と「実際の労働時間」が合っているかを適正に確認できる運用にすることが必要です。また、現実的な問題としてよく出てくるのが、「制服への着替え」や「職場の掃除」が労働時間に含まれるか、ということです。ポイントとなるのは、着替えや清掃が上司の指揮命令下にあるかどうかです。仕事をする上で制服に着替えることが必須であるとしても、たとえば着替えの時間に自由にスマートフォンを触ることができたり、掃除を従業員の自由意志で行っていたりする場合は、労働時間とならない可能性が高くなります。
逆に、着替えの時間に一切の私語を禁じられていたり、職場の暗黙下のルールで掃除をしなければならなかったりと、労働者の行動の自由が認められないケースでは、労働時間としてカウントされることも否定できません。
さらに、タイムカードに打刻された時刻と実際の労働時間に差があることも、よく問題視されます。たとえば、タイムカードに打刻された終業時刻よりも遅い時間にパソコンの使用履歴が残っているようなケースです。労働基準監督署の調査次第では、賃金不払残業と認定され、指導を受けることにもなりかねません。
対策としては、「タイムカードなどの勤怠記録」と「従業員が使用するパソコンの記録」を定期的に照合することが必要となります。かなり手間がかかる作業ではありますが、後になってまとまった金額が出ていくことを考えると、リスク回避策として検討しておきたいところです。もし、それが困難であるという場合は、従業員の退社時間をタイムカードに打刻される時刻とし、それに基づいて残業代を計算する運用方法を取り入れることをお勧めします。
「残業の抑制」と「生産性の向上」で考えて、適正な残業代の支払いを
本来、残業時間は1分単位で算定されるものであり、会社の都合で調整できるものではありません。たとえば、1日の残業時間を15分単位で計算し、それに満たない時間は切り捨てるようなケースです。従業員が労働時間を細かく記録をしたメモを労働基準監督署に持ち込んだ場合、有力な資料と認められれば、指導の対象となることもありますので、面倒でも残業時間は1分単位で計算するようにしましょう。ただし、1ヵ月分の残業時間を合計した時に、合計時間に30分未満の端数があるときはその端数を切り捨て、30分以上の端数については1時間に切り上げることは認められています。
また、残業自体を許可制にすることも有効です。就業時間が終わる時刻までに、上司に対して「残業許可申請書」を提出することを従業員に義務付け、上司が許可した場合に限って残業をするというものです。従業員が残業できる時間数については「36協定」で決められていますので、限度時間を超えないよう管理することも可能となります。
企業としては、残業時間を抑えることで人件費を抑制し、併せて働き方改革も推進することが課題となっています。トップダウンで残業抑制を指示するのは大切なことですが、業務量の調整や効率化に目を向けないまま残業だけを抑制しても、現場が疲弊する可能性がありますので気をつけなければいけません。「残業の抑制」と「生産性の向上」をセットで考えた上で、適正に残業代を支払うことが重要です。労務管理でご不安がある場合は、社会保険労務士の力を借りることをお勧めします。
- 1