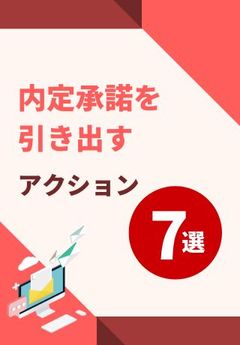多様化する学生の就職サイト利用
就職活動の早期に学生が活用している就職サイト(就活関連サイト)を文系・理系別に比べてみましょう。主な15サイトから複数選択で尋ねたところ、文系では、「マイナビ」が61%でトップ、次いで「就活会議」(51%)、「リクナビ」(50%)、「ONE CAREER」(49%)が2番手グループを形成しています[図表7]。かつて就職ナビ全盛時代には、「マイナビ」「リクナビ」は9割以上の学生に活用されていたことを考えると、従来型の就職ナビの活用度が大きく低下するとともに、就活口コミサイト(「就活会議」「ONE CAREER」など)の存在感が増していることが分かります。逆求人サイトの「OfferBox」が35%、社会人向け口コミサイトの「OpenWork」も33%と3割以上の学生に活用されるなど、学生が活用している就職サイトが多様化している様子がうかがえます。一方、理系学生が活用している就職サイトを見ると、多様化傾向はさらに進んでいます。「ONE CAREER」が64%で最多となり、「就活会議」(59%)が2位、「マイナビ」(57%)がようやく3位に食い込み、4位には「OfferBox」(40%)がランクインしています。また、「TECH OFFER」(33%)、「LabBase」(31%)など、理系に特化した就職サイトも3割以上の学生から支持されています。
![[図表7]活用している就職サイトTOP15(複数回答)](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4268_8_NZ271O.png)
実質的には、インターンシップが就職活動の一環として位置づけられている今、企業のインターシップへの応募も、3月以降公開の採用情報へのプレエントリーも一括で受け付けてもらえるのであれば、学生にとって就職ナビは極めて便利なツールであるはずです。にもかかわらず、[図表7]で見たように、活用度において他のサービスに対し決して優位なポジションは取れていないようです。学生はインターンシップへ応募する際、それほど就職ナビを活用していないのでしょうか。
インターンシップへの応募ルートを聞いたところ、「すべて企業のHPから」が最も多く、文系で36%、理系では43%と4割前後が直接応募すると回答しています[図表8]。「企業のHPがメイン、就職ナビがサブ」を合わせた“企業HP派”は文系で58%、理系では61%と約6割に達します。一方、「すべて就職ナビから」と「就職ナビがメイン、企業のHPがサブ」を合わせた“就職ナビ派”は文系で30%、理系では25%となり、“企業HP派”が“就職ナビ派”を大きく上回っています。また、理系学生のほうが文系学生よりも、企業HPを活用する割合が高い傾向が見られます。これは、自身の専攻に関連する業界を志望する傾向が強い理系学生のほうが、具体的に志望企業を絞り込めている割合が高いことが影響しているものと推測されます。
本連載「2025年2月」で、採用担当者向けに実施したHR総研「2025年&2026年新卒採用動向調査」(2024年12月)の結果として、企業側のインターンシップの募集方法を取り上げましたが、1001名以上の大企業では「自社HP」の利用が「就職ナビ」を上回っていたものの、1000名以下の中堅・中小企業では「就職ナビ」が「自社HP」を上回っていました。特に中小企業では、「自社HP」の利用が3割を下回るなど、「就職ナビ」頼りになっている状況です。リソース等の関係から、なかなか自前での管理・運営が難しい面があると思いますが、中堅・中小企業も、もっと「自社HP」の活用を考えたほうがよさそうです。
![[図表8]インターンシップへの応募ルート](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4268_9_1AA28D.png)
ほとんどの学生が対面型インターンシップに応募
ここからは、インターンシップ(オープン・カンパニーを含む)への参加・取り組み状況を見ていきます。まずは、インターンシップに参加した社数です。文系では「0社(応募をしていない)」が10%と、理系の2%を大きく上回ります[図表9]。事前選考で漏れてしまい、結果的にインターンシップに参加できた社数がゼロということはあり得るとしても、そもそも応募すらしていない学生が1割いるというのには少々驚かされます。文系で最も多かったのは「6~10社」の28%で、次に多いのは「21社以上」の13%です。「11~15社」(12%)や「3社」「4~5社」(ともに11%)もそれぞれ1割以上となっています。「6~10社」から「21社以上」までを合計した“6社以上”が59%と6割近くに上ります。理系で最も多かったのは「4~5社」の25%で、次いで「6~10社」が15%で続き、「11~15社」も13%となっています。「21社以上」は文系ほどではないものの5%あるほか、“6社以上”は42%と4割を超え、「4~5社」まで含めると67%と約3分の2を占めます。「1社」「2社」が2割を超えるなど、文系より参加社数が少ない傾向にあるものの、理系学生も積極的にインターンシップに参加していることが分かります。
![[図表9]インターンシップ参加社数](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4268_10_5B9DY6.png)
1社以上の参加社数を見ると、文系では「4~5社」が26%で最も多く、「2社」(17%)、「3社」(15%)、「1社」(13%)と続きます。理系では「3社」「4~5社」がともに22%で最も多く、次いで「2社」(20%)、「1社」(16%)となっています。対面型は日数が複数日にわたる例がほとんどで、“6社以上”(「6~10社」と「11社以上」の合計)は文系で10%、理系で9%と、ともに1割程度にとどまります。応募の段階から企業を絞り込んでいることもありますが、募集枠がオンライン型よりも限られるため、結果的に事前選考を通過しづらいことも影響しているものと推測されます。
![[図表10]対面型インターンシップ参加社数](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4268_11_0QK6E3.png)