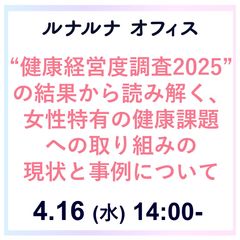重要なのは「周知」と「優先事項を決めること」
具体的事項に関する検討を進めるに際して、まず、重要な点を押さえておきたいと思います。ひとつは、「基本方針を明確化することと、その方針を社員全員に周知徹底すること」。あとひとつは、「会社の法的な義務を知ることは勿論のこと、人生の多くを会社に賭けてくれている社員に対する福利厚生面の配慮をどこまで考えるか」、この2つです。「災害対策」の基本方針の明確化と徹底
災害発生時の対策を考える場合、考慮すべき事柄は以下の点です。(b)業務遂行の継続性の確保
(c)対顧客への製品、商品、サービス提供の中断の回避
上記3点はすべて大事ですが、実際には相矛盾する場合がしばしば発生します。その際に、この3点の間の優先順位が揺らぐと大きな混乱が生じます。ですから、何を最優先とするかの基本方針を予め明確にして、それを社内に徹底することが極めて重要です。
仮に「継続的な業務遂行の確保」や、「製品、商品、サービス提供の中断回避」を優先すると、社員への安全配慮義務が疎かになることがあります。かつては、「雨が降ろうが槍が降ろうが」仕事、顧客が最優先。そのために、多少の危険や不便を社員が感じるのは当然、と一般的に考えられてきました。公共交通機関も、災害の現実化のぎりぎりまで運行するのが当たり前。災害時にいち早く運行がストップするような交通機関は、いざというとき頼りにならない交通機関として低い評価がなされたものでした。
ところが、昨今はJRはじめ多くの公共交通機関が、災害発生の予想に基づき早々に「計画運休」することは何ら不思議とは思われなくなりました。即ち、世間一般の常識が社員の安全確保第一に大きく舵が切られたのです。にもかかわらず、「リスクを冒して出社する社員を褒めたたえる」意識、仕事、顧客第一主義を経営者や管理職が引きずっていると、とっさの判断、明確な判断が求められるときに、社員の安全上危険な判断をしてしまう可能性があります。ですから、まず「安全第一」を災害対策の最優先とすることを、社員全員に徹底することからスタートしなければなりません。
また、(b)と(c)は、個別の会社によって対応が大きく異なります。今回は、(a)の安全配慮義務遂行のため、「労務管理上、検討すべき事項」に絞って検討を進めます。
災害対策を「法的義務」と「福利厚生」の視点から考える
次に、災害時の労務管理について考えるにあたってよく論じられるのは、「会社としてどこまで法的に義務があるか」という点です。そもそも、災害によって損害が発生しても、それ自体に会社にも社員にも法的な賠償責任はありません。「会社に責任はないのだから、災害による損害に対し社員に一定の補償を予め約束するのは経営上避けたい」との考えから、どうしても関心が法的に最低限どこまでやらないといけないかを知りたい、ということに向きます。
しかし、社員という会社の大事な構成員が、災害によって心身や財産上の被害を受けた際、黙って見過ごすことはできないという、法的義務を超えた福利厚生的な観点も無視する訳にはいきません。従って、今回の検討の対象としては、ギリギリ最低限の法的義務の有無だけでなく、福利厚生的な面でどう対応すべきか、という観点も入れたい。また、「それをどこまで社内規程として織り込むか」も検討したいと思います。
社員の安全を第一に考えた場合に「検討すべき事項」とは
社員の安全を第一として以下の点を整理して行きます。但し、その結果として前述の(b)、(c)が疎かになって良いわけではありません。むしろ、「安全第一を前提として顧客ニーズにどう応えるか」を検討することが重要と言えます。(1)出社させるか、または退社させるかの判断基準
以前は普通に、翌日の台風襲来に備え泊まり込みさせる、台風や地震発生した朝に多少の危険を省みず出社させる、などして来ました。それを奨励する雰囲気が世の中に強くありました。しかし、今回検討すべきは、「社員がそれを望んでも、会社の安全配慮義務の観点からブレーキをかけるにはどうするか」です。(2)出社しない場合、有給の休暇とするか、休業補償するか、欠勤とするか、あるいは「自宅などでのテレワーク」とするか
出社できない、あるいはさせない場合、その日は「ノーワークノーペイ」で一切を割り切るのかどうか。法的観点、福利厚生面でどう考えるか。(3)会社や自宅での待機時間の労働時間性の判断
災害の襲来に備えるため、あるいは現実の災害発生時、「会社での待機」と「自宅での待機」ではどう違うか、また、その時間に何をすることを求めるか。(4)賃金支払い等の義務
会社にも社員に責任のない事態に対する負担を、会社がどこまで負うか。「法的面」と「業務遂行」との兼ね合いで、どうするかを決める必要があります。(5)36協定上の労働時間規制
これは、むしろ純粋に「労働基準法」上、災害時の特例に当たるかどうかの判断基準に添わなければなりません。(6)労働災害
「通常とは異なる経路での通勤途上」を含めた労働災害をどのように考えるか。これも、労災保険の基準に添う必要があります。(7)労務管理規定
以上を踏まえて、「法的観点からの定め」と、「福利厚生的な定め」をどのように規定するか。(8)災害時の緊急連絡先の登録と個人情報の保護
緊急連絡網を作成しようとしたとき、個人の携帯電話や電子メールアドレス等を会社に告知することを拒否する社員が出た場合どうするか。*
次回以降、上記の8項目にわたり検討を深めていきます。
- 1