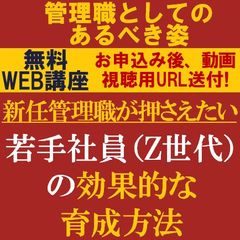内閣と大蔵省の大喧嘩
内閣の要人たちは、大蔵大臣・井上馨と大蔵少輔・渋沢栄一と、司法卿江藤新平の対立をどのように眺めていたのであろうか。「白豆」こと三条実美は、前話で触れたようにおどおどしていてリーダーシップなし。参議の西郷隆盛は、鹿児島へ帰国中。おなじく大隈重信は関西へ出張中で、もうひとりの参議板垣退助もこの問題に関心を示さなかった。井上が明治5年(1872)11月5日から自宅に引きこもると、渋沢栄一も江藤らの攻撃の矢面に立つのを嫌ってか、同月28日から大蔵省へ出勤するのを取り止めた。すると政府は井上・渋沢コンビの動きをサボタージュの一種とみなしたのであろうか、「各省の政費増給を拒絶する」という大蔵省の具申書面を却下してしまった。
そこで勝手に休職していた井上が太政官に出向き、大蔵省の考えを委曲を尽くして説明したが、各参議は聞く耳を持たない。これは在京の参議たちも、江藤が井上を批判する際に用いる「三井の番頭」「私欲の権化」といった悪口にいつの間にか影響を受けていたためかもしれない。
内閣と井上の仲がついに決裂したのは、明治6年(1873)5月3日のこと。この日、井上が大蔵省にもどってからの行動について、『世外井上公伝』1は栄一の談話を根拠として下のように書いている。
「各省では大蔵省の主張を容(い)れず、なに公(井上)の反対なんか構ふものかといふ風で、盛んに濫費(らんぴ)したので、真実の喧嘩と為(な)つて了(しま)ひ、公も最早我慢が出来ず、【略】内閣から省へ帰つて来て、『もう乃公(おれ)も辞職の外(ほか)は無い。』と渋沢等の昼餐中の席に来て述懐し、『さあ辞表を書いて呉(く)れろ。』と無造作に秘書官に吩咐(いいつ)けた」
このとき、栄一は口をはさんだ。「貴卿が辞任をなさるなら、私も罷(や)めます。」(同)
しかし、井上は、「国家の為(ため)だから後任者の為尽くしてくれ。」(同)といって聴き入れようとしない。そこで栄一は、こう言い返した。「それは貴卿の勝手が過ぎると存ずる。以前私が辞職を志した際御慰(ぎょい/慰留)があつて罷める時は一所にやめると仰(おつ)しやつたでは有りませんか。」(同)
これによって井上・渋沢コンビは、この日をもって大蔵省に辞表を提出することになった。文字通りの「連袂(れんべい)辞職」である。静岡藩で商法会所や常平倉を経営していた栄一が、太政官から呼ばれて出頭したのは明治2年(1869)11月4日のこと。栄一はその場で民部省の租税司正に補せられたのだから、都合三年半の役人生活であった。
数え34歳の栄一に、連袂辞職に踏み切らせることにためらいなど一切なかったように見えるのは、かれらが今日のサラリーマンより武士に近い感覚で生きてきたことによるのだろう。
「君(きみ)辱(はずかし)めらるれば臣(しん)死す」とは、主君が人から恥辱を受けたならば臣下たる者は命を賭してその恥をすすがなければならない、という感覚のこと。
あきらかに井上・渋沢コンビは、内閣が大蔵省の「入るを量って出だすをなす」の原則を理解しようとしないで井上の顔をつぶしたことを怒り、役人として生きてゆくという人生のコースを擲(なげう)ったのである。
超大作となった「建議書」の中身
ただし栄一は、明治6年度の大蔵省予算案が通り難いと感じた時点で、内閣に敗政意見書を提出しようと考え、名文家として知られた部下の那珂通高(なかみちたか)に草稿を見せて文飾を整えさせていた。栄一の辞表提出から2日、5月5日に井上にこれを見せると、「これはよく出来た。併(しか)しも少し数字を入れて確(たしか)なことを書き足さねばならぬ。吾輩が手を入れるから、一つ連名で政府へ出さう」(同)といって加筆にとりかかった。
栄一がそれを持って帰ってふたたび那珂通高に手を加えさせ、決定稿の出来たのは6日のこと。内閣に提出されたのは7日のことであったが、400字詰めの原稿用紙に換算して14枚以上に達するこの「建議書」は、全文が『世外井上公伝』1に紹介されているので、そのポイントとなる部分を頭に入れておこう(原文は漢字片仮名混じり文)。
まず明治維新によって文明開化の時代がきたことを称(たた)えた筆者は、中央官庁と府県の役所に勤務する役人が増加する一方となって俸給額が嵩(かさ)み、歳出が歳入を上回る事態となっているため増税がおこなわれ、市民を苦しめつつあることに言及。政府の負債額をあきらかにした上で、その無策ぶりを下のように批判してみせた。
「今全国歳入の総額を概算すれば四千万円を得るに過ぎずして、予(あらか)じめ本年の経費を推計するに一変故(へんこ/非常の事態)なからしむるも、尚五千万円に及ぶべし。然(しか)らば則ち一歳の出入(でいり)を比較して、既に一千万円の不足を生ず。加之(しかのみならず)、維新以来国用の急なるを以て、毎歳負ふ所の用途も亦(また)将(まさ)に一千万円に超えんとす。其他官省旧藩の楮幣(ちょへい/紙幣)及(および)中外の負債を挙ぐるに、殆んど一億二千万円の巨額に近(ち)かからんとす。故に之を通算すれば、政府現今の負債実に一億四千万円にして、償却の道未だ立(たた)ざる者となす。然(しからば)則速く其制を設けて、遂次之を支消(ししょう)せざるべからず(負債を消してゆかねばならない)。【略】然り而して政府未だ意を此(これ)に注せず」
井上・渋沢コンビ連名のこの「建議書」は、国家の負債を無視して放漫財政に走ろうとする政府への弾劾文でもあったのだ。後段には、渋沢栄一の持論が次にように展開されている。
「夫(そ)れ出るを量りて入(いる)を制するは、欧米諸国の政(まつりごと)を為す所為(しょい/目安)にして今我国力(こくりょく)民情未だ此に出る能(あた)はざる者、人々能(よ)く知る所なれば、方今ノ策は且(しば)らく入(いる)ヲ量りて出(いず)るを制するの旧を守り、務(つとめ)て経費を節減し、予め其歳入をが概算して歳出をして決して之に超ゆるを得ざらしめ、院省使寮司(正院・各省・開拓使・諸寮・諸司)より府県に至るまで、其施設の順序を考量し、之れが額を確定し、分毫(ぶんごう/わずかの量)をも其限度を出るを許さず。【略】是(これ)今日の時勢にして我が国力民税の適(てき)とする所、未だ此に愈(かわ)る者あらざるなり」
最後に井上・渋沢コンビは、なにゆえこのような建議書を差し出す気になったのかを堂々と述べ立てた。
「夫(それ)知(しり)て言はざるは不忠なり。知らずして言(いう)は不智なり。臣等た縦(たと)ひ不智の譴(けん/とがめ)を受(うく)るとも、決して不忠の臣たるを欲せず。是(ここ)に於て乎(か)既に其職務に堪へざるを以て骸骨を乞(こう)と雖(いえど)も、区々の心今日恝然(かいぜん)たるに忍びず(不安を禁じ得ない)。故に敢(あえ)て其愚衷(ぐちゅう)を留めて、以て政府の少しく回顧する所あらんと望む耳(のみ)」
この建議書について『世外井上公伝』1は、「文意頗(すこぶ)る暢達し、遺憾なく時弊を論じ、国家百年の大計を説いてゐる」と高く評価している。政府側から見れば、このような建議書まで出すからには井上・渋沢コンビに意志を翻す気はない、と判断せざるを得ない。そこで5月9日、参議大隈重信に大蔵省事務総裁を兼務させることにし、14日に井上・渋沢コンビの辞職を聞き届けた。
渋沢・井上の辞職は新聞にも報じられる
ところが、その間にまた一波乱が起こった。井上は建議書を政府に差し出した後、栄一の意見に従ってこの論文を新聞に投書するつもりでいた。投書は予定通りおこなわれ、筆者個人も『新聞集成 明治編年史』第2巻により、『新聞雑誌』の付録第98号に建議書が全文掲載されたのを確認することができた。同様に『日要新聞』第75号、『日新真実誌』5月9日号、横浜で発行されている外字新聞(外国語の新聞)にも建議書は掲載された、と『世外井上公伝』一にあるが、外字新聞でも報道されたことは、スコットランド人ジョン・レディ・ブラックが明治9年(1876)から翌年までの間に書いた『ヤング・ジャパン』の記述からも裏付けられる。
ブラックは文久元年(1861)ごろ来日し、イギリス人ハンサードが横浜で発行していた『ジャパン・ヘラルド』に迎えられて新聞記者として出発。その後独立して日刊紙『ジャパン・ガゼット』や『ファー・イースト』を刊行し、明治五年には前述の邦字紙『日新真実誌』をも創刊した(『ヤング・ジャパン』1、ねず・まさし「解説」)。
『ヤング・ジャパン』はブラックが関与して作成した新聞記事を寄せ集めて作られた二冊本(訳書は3冊本)だが、「第三十七章(一八七三年)」(訳書3所収)に「井上聞多と財政」と小見出しをつけた項目があるので、これを見ておきたい。
「井上聞多と財政 国の歳入歳出問題が、政府の大きな悩みの種になっていた。ちょうどこの頃、大蔵卿(ママ)井上馨(かおる/聞多・原注)と次官渋沢(栄一・同)が辞職した。辞職にあたって、二人は太政官に建議書を提出した。それによると、国家の財政状態が警戒を要するようであった。すなわち内外の負債は累積し、年々二百万ドルの赤字があるということだ。この建議書の公表は世間に動揺を引き起した」(ねず・まさし他訳)
この記事にいう「動揺」した「世間」には、大隈重信や司法卿江藤新平もふくまれていた。次に、かれがどのように反応したかを眺めよう。
ブラック『ヤング・ジャパン』の「井上聞多と財政」という小見出しを立てた記事の次には、左の記事がある。
「大隈重信卿 そして(明治六年〈一八七三〉五月十日、大隈重信に)、大蔵省の責任を負い、調査を行なうように命令が出された。大隈は(井上・渋沢合作の「建議書」を)精細に研究した結果、完全な予算を発表し、全く別の説明を行なった。彼は(建議書の)米の算定価格(歳入の大部分は、米で成り立っている・原注)があまりに低過ぎ、他の種目の算定も不正確であることを示した。一言でいえば、(歳入は)不足ではなく、余剰であることを示した。その結果は正しかった」(傍点筆者)
傍点部分は舌足らずの上、誤訳の可能性もあるので、真実をもう少し深く掘り下げてみる。政府は明治6年5月18日、すなわち井上馨・渋沢栄一連名の建議書が提出されてから11日目にその書面を差しもどすと宣言。次のような「弁解」をこころみた(原文、漢字片仮名混じりの和風漢文、読み下し筆者)。
「建言の主意、その立論適当のことに候へども【略】現実と相違ひ候儀少なからず。【略】歳出入を概算し、一千万余の不足を生じ候等の儀書き載せ候へども、右は米価一石二円七十五銭を以て算当(さんとう/計算)候積(つもり/結果)にて、且(かつ)此内には逐年繰り戻しに相成り候分、又は廃藩置県の如き非常の入費、或(あるい)は一時の費(ついえ)のみにて年々例算すべからざる者もこれあり。その上政府現今の負債を論じ、実に一億四千万円に下らずとこれあり。【略】かれこれ実事に徴し勘合候へば、必ずしも毎年一千万円の不足を生じ、又一億四千万円の巨債を負ひ候訳にこれなく、かたがた右等申し出の儀不都合の次第につき、書面そのまま差しもどし候事」(『世外井上公伝』1より)
「臭いものに蓋をする」とは、醜悪な事実を他に知られないように、一時的な間に合わせの手段で隠すことをいう。大隈重信大蔵省事務総裁と井上・渋沢コンビよりランクの低かった同省の役人たちとは、この表現を地で行って建議書の受け取りを拒否したのである。
辞職騒動への世間の反応
このような政府の反応を第三者はどう感じたのか。「政府の弁解はとにかくも、元来が(大蔵省)主管者(中心人物)の上書であつたからして、中外は政府の弁明を信ぜす、頗(すこぶ)る物議に渉(わた)った」と『世外井上公伝』1 は既述し、政府は大隈に大蔵省の簿記を精査させて歳入歳出の実額を計算し直させた。その結果、大隈は6月9日、「白豆」三条実美に対し「明治六年歳入歳出見込(みこみ)会計表」を提出するに至った。
この「会計表」は「我国歳計(さいけい)予算の濫觴(らんしょう/はじまり)」とされているから、「あらかじめ歳入を概算して歳出を歳入以下に抑えるべきだ」とする渋沢栄一の年末の主張は、ようやくここに生かされたわけであった。
ちなみに「明治六年歳入歳出見込会計表」には、以下のような数字が並んでいる。
歳出 金4,659万6,518円46銭4厘
歳入の歳出より多き高 金214万1,264円81銭9厘
内外国債 3,122万4,701円
(『新聞雑誌』106号より)
井上・渋沢コンビが政府に建議書を届け、かつ新聞各紙にその写しを送らなければ、このような数字が公表されることなどはあり得なかった。上の数字の正不正はしばらく措くとしても、この建議書が国家予算の明朗化に役立ったことだけは確かであった。
『論語』による商業によって国家繁栄となる
このような大隈の動きに対し、大蔵省にとってより厄介だったのは司法卿江藤新平が井上・渋沢コンビを弾劾し、「政府の秘事を故(ことさら)に世に泄(もら)したのであるから、彼等を捕縛すべし」(『世外井上公伝』1) と主張したことであった。以来、井上・渋沢コンビの身辺には司法省の探偵数人がつきまといはじめ、「建議書」をブラックの『日新真実誌』に載せるのに協力した大蔵省の書記官兼子(かねこ)謙、佐伯惟馨(これか)、稲垣某の3人は投獄の憂目を見たほど。憤激した井上馨は、5月27日、初代陸軍卿となっていた長州藩の先輩・山県有朋(やまがたありとも)に窮状を訴えたりした。
江藤はさらに、井上・渋沢コンビの罪に問うべく画策。明治6年7月20日、司法省臨時裁判所から井上には禁錮40日のところ特命により贖罪金3円、栄一にはおなじく「四円幾銭の罰金に処せられた」(同)
強面(こわもて)の江藤の動きもここまでだったが、栄一の辞職を知った役人仲間のうちには、かれを翻意させようとして神田小川町の渋沢邸を訪ねてきた者もあった。のちに「今大岡」と渾名(あだな)される名判事・玉乃世履(たまのせいり)や松本暢ら有為の人物と評判の高い友人たちが、栄一が民間に下るのを惜しんでやってきたのだ。対して栄一は、かねがね考えていたところを率直に述べた。
「国家の基礎は商工業にあり、政府の官吏は凡庸にても可なり。商人は賢才ならざる可(べか)らず。商人賢なれば、国家の繁栄保つべし。古来日本人は武士を尊び、政府の官吏となるを無上の光栄と心得、商人となるを恥辱と考(かんがえ)るは抑(そもそ)も本来誤りたるものにして、我国今日の急務は一般人心をして力(つと)めて此の謬見(びゅうけん)を去り、商人の品位を高(たこ)ふし、人才を駆りて商業界に向かはしめ、商業社会をして最も社会の上流に位せしめ、商人は即ち徳義の標本、徳義の標本は即ち商人たるの域に達せしめざる可らず予れ従来商業に於て経験しに乏しと雖も、胸中(に)一部の論語あるあり。論語を以て商業を経営し、両君の観に供せんとす」(『六十年史』第1巻)
栄一は初めて孔子の説いた『論語』の精神によって商業界へ進み、国家の繁栄に貢献する、との独得の人生観を披歴してみせたのである。
【編集部よりお知らせ】
本連載が書籍になりました! 書下ろし7話分を加えた決定版『むさぼらなかった男 渋沢栄一「士魂商才」の人生秘録』(文藝春秋)は好評発売中です。お近くの書店、通販サイトよりお買い求めください。
※書名をクリックするとamazonのサイトにジャンプします。
- 1