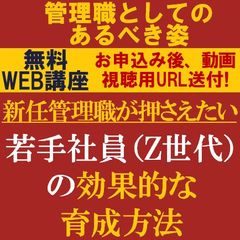日本の資本主義の礎を築いた渋沢栄一。2022年に日本最高額紙幣の“顔”となる「日本資本主義の父」がどのように生まれたかを、史実第一主義の直木賞作家・中村彰彦氏が紹介する(編集部)。

株式会社制度を取り入れ「商法会所」を作る
明治政府の広報誌『太政官日誌』第16所載の「金札御貨下ノ事」は、漢字片仮名混じりでの候文で書かれており、おまでは使われなくなった表現もあるため読みにくい。そこで本稿では、塚本豊次郎『改訂 本邦通貨の事歴』からうまくまとめられているその「要旨」を引用することにする。「奥政更新の折柄(おりがら)富国の基礎を建つる為(た)め金札を製造発行し、庶民の困窮を救助させるゝ思召(おぼしめし)を以って、本年より13年の間国内1円に通用せしむる其(そ)の方法は左の通り心得べし。
1、金札は列藩石高に応じ、1万石につき1万両の借用を許す。
1、其の返納方法は必ず其の金札を用ひ、毎年末借用高の1割宛(ずつ)を返納し13ヵ年に皆済(かいさい)すべし。
1、列藩諸侯借用の金札は全く富国の基礎を建てさせられんとする聖旨(天皇の趣旨)を奉体(ほうたい)して、専(もっぱ)ら之(これ)を興産事業に売用し、猥(みだり)に藩庁の費用に用うべからず。
1、京摂(京都、摂津)及び其の近郷の商人にして、金札借入を望む者は其の旨金札役所に申出(もうしい)づれば其の取扱ふ産物高に応じて之を貸付くべし。
1、各府及び列藩領内の農商家にして、金札の借入を願づる者あるときは、能(よ)く其の身元を調査の上にて貸付くべし、但(ただ)し返済の場合には相当の元利を償(つぐな)はしむべし。(1項目省略)」
しかし政府は諸藩には「みだりに藩庁の費用に使うな」といいなはら、みずからは多額を軍事・行政上の緊急支出にまわさざるを得なかった。岩波文庫版『雨夜譚』の公中者長(ちょう)幸男(ゆきお)はその割合を4,800万両の「62%」(同書校注)、しなわち2,976万両とし、『維新史』第5巻は「政府が直接使用せる金額」を3千余万両としている。 なんのことはない、政府の印刷した金札の62.5%前後は政府によって使用されたのである。そのほかへの貸し下げ額を、きわめて信頼できる『維新史』の5巻はこう示している。
諸藩への貸与額は、960余万両。
県府への貸与額は、158万両。
商人への貸与額は、650余万両。
併せて殖産興業資金全額は、1,780余万両(約37.1%)。
駿河府中藩は70万石の所帯だから、70万両の貸し下げが受けられる。栄一は駿河に行って間もなく、そのうち53万両はすでに貸与されたと聞いた。ただし藩庁はまだどんな殖産興業をすすめるか未定のようだし、年が明ければ残りの17万両も貸し下げとなるであろう。 諸藩の側ではこの貸与額を「石高割(こくだかわり)貸付金」「石高拝借金」などと呼んでいたが、栄一いったん政治的に破綻して府中藩となった旧幕府が狭い封土と少ない歳入にあえいでいるのを見てこう考えた。この石高拝借金を藩財政とは別の経済として、これを元手に興業殖産にあたり、そこから生じる利益の1部をもって年に1割の返納金に充てれば、藩も潤うし領民たちの幸福にもつながるのではないか。
府中藩の勘定組頭になることを辞退しておきながら、藩財政を好転させる手法を考えはじめたところに栄一らしさがある。しかも栄一の目から見ると駿府は小都市ながら相応に商人もいるので、藩庁が石高拝借金の1部お原資金としって貸与してやれば、その商業をさらに盛んにするのはさほど難しいことではない。そこで考えを進めたとき、栄一の頭に閃(ひらめ)いたのは「共力合本法」を採用すればよい、というアイデアであった。
この頃、「共力合本法」と訳されていたのは、「株式会社制度」のこと。合本とは資本を持ち寄るという意味である。このときの着想について、栄一はのちに下のように回想することになる。
「今この共力合本法の便利有益を有力の商人に会得させたならば、この地方でも幾分の合本は出来るに相違ないから、この石高拝借金を基礎としてこれに地方の資本を合同させて1個の商金を組立て、売買貸借の事を取扱せたならば、地方の商況を1変して大いに進歩の功を奏することを得るであろう」(『雨夜譚』)
かつて尊攘激派たらんとした栄一は、横浜焼き討ちを計画した際にも一匹狼として行動するのではなく、同志たちを組織化して事に当たろうとした。2年近いヨーロッパ大旅行の間、頑迷な水戸藩士もふくまれる使節団一行を何とか破裂させずに済んだのも、栄一の組織をまとめる能力に負うところが多かった。その「組織をまとめる能力」は理財に関する才覚あってのものであったが、今度栄一は、地元商人たちに呼びかけて資本を出し合ってもらい、「商会」を組織しようと考えたのである。
紹介の頭取に就任
むろん、これはフランスで学んだ知恵のひとつだが、勘定頭の平岡準蔵にこのアイデアを詳しく伝えた栄一は、ひとつだけ条件をつけた。「商会の監督は御勘定頭にお任せするとして、その運用の枢機を自分に1任して下されば、商人たちの中から相応の人財を選んで協力してもらうようにいたしましょう」
「いや、よくわかった。至極面白い考えだ」と平岡が応じたのは師走のうちのこと。明けて明治2年(1869)正月、府中藩は栄一のアイデアを受けて「商法会所」という名の1種の商社を設立することになった。
なお、この年のうちに駿河府中藩の「フチュウ」は「不忠」に通じてよくないという見解により、同藩は静岡藩と改称するに至る。同時に駿府は静岡という地名に変わり、商法会所は静岡の紺屋(こうや)町にあった家屋を事務所としてスタートした。
「会所」ということばは、もともとは「会合」のおこなわれている「場所」を意味したが、次第に役人や商人たちの事務所、取引所、役所などをも指すようになった。明治初年にはまだ英語の「カンパニー」を「会社」とする訳語が生まれていないため、静岡藩は会社の意味で会所という表現を採用したのであろう。
ヨーロッパ滞在中の倹約策が功を奏する
その出資者と額面は左のようであった。静岡藩庁 1万6,628両余
別に金札 38万5,951両余(正金に換算して25万9,463両余)
士民より 1万4,795両余
別に金札 3,830両
総資本 29万4,717両余
(幸田露伴『渋沢栄一伝』)
特に注目したいのは、静岡藩庁の出資した「1万6,628両余」の1/3――約5,542両は、栄一がヨーロッパ滞在中に倹約して貯え、持ち帰って藩庁へわたしたものだったことである。公金をまったく私(わたくし)しようとしなかった栄一の誠意に静岡藩庁がよく応え、栄一からもどされた金を栄一提案の商法会所の設立資金の1部として提供した形であった。栄一はいう。
「地方の重立った商人13名に用達(ようたし)を命じ、あたかも銀行と商業とを混淆したような物が出来ました。(略)全体の取締りは勘定頭の任として、自分は頭取(とうどり)という名を以てその各部の掛員(かかりいん)として、これに用達幾名かを付属して業務を執ることになった」(『雨夜譚』)
栄一は陰の出資者であり、かつ半官半民のこの会所の「民」を代表する立場になったのだ。
静岡藩にとって「福の神」となった渋沢栄一
頭取としての栄一が最初に直面したのは、出資者と額面一覧の中に示したように金札を正金(金銀の貨幣)に両替すると価値がたちまち下落するとことであった。金札使用開始日の慶応4年3月15日は彰義隊の消滅した日だが、奥羽越列藩同盟は結成されたばかりで戊辰戦争の結果はまだどう転ぶか見当もつかない状況であった。すなわち新政府の基盤は弱体である、しかも金札は不換紙幣なのだから、この傾向は当然の結果であった。
使用開始の直後の時点でも、正金100両は対して金札なら112両ないし150両という相場(由利正道編『子爵由利正道伝』)。一次は金札100両を正金40両とする相場にさえなったほどで、これを政府は両替店が多額の打歩(うちぶ/両替え)を取るためとみなし、6月2十日には打歩引換禁止令を出した(『維新史』第5巻)
それでもさほど効果があがらなかったので、12月4日、政府は金札の時価通用を許し,公納に用いる場合は「金札120両を正金100両」の相場とした。それでも金札の価値は下がりつづけたことは、先に引いた『渋沢栄一伝』に明治2年初め、金札38万5,951両余が正金25万9,463両余だった、とあることからもあきらかである(金札の勝ちは額面の67.1%)。対して栄一は、こう考えた。
「将来を予想して見るに、ついにはこの紙幣流通のため諸物価はかえって騰貴を示すに相違ないから、今の内に早くこの紙幣を正金に好感して物品を買入れて置く方が利益は多かろう」(『雨夜譚』)
そこで栄一は、掛員、用達の商人たちと協議して東京では肥料、大阪では米穀を買い入れた。みずからは明治2年に金札を以って東京へ出、〆粕(しめかす)、干鰯(ほしか)、油粕、糠(ぬか)などを買い入れ、ついでに故郷から妻を呼び寄せて3月中旬に静岡へ帰ってきた。
栄一の予想はみごとに当たった。
肥料も米穀も次第に値段が騰貴したので、米穀は利益があると見れば、時々これを売却、肥料は領内の村々へ貸しつけて応分の利益を収めるという運用法は確定。それを見て預け金(資本参加)する士民もおいおい増加し、栄一は商法会所によって静岡藩に利益をもたらすことに成功したのである。
露伴によると、明治2年1月に発足した商法会所は同年8月末までの間に、総資本29万4,717両余によって8万5,651両余の利益をあげていた。静岡藩の士民には、栄一を福の神のように感じた人も少なくなかったのではあるまいか。
- 1