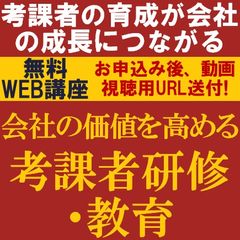副業は容認する方向で検討することが適切
副業を認めるかどうか、またその条件は、企業が独自に決めることができますが、副業に関する裁判例でも「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由である」とされており、原則は副業を容認することが求められます。とはいえ、労働者に対して「副業を自由におこなってよい」と手放しで容認してしまうと、企業としてはリスクがあります。未払賃金の請求や、競合他社への情報漏洩、長時間労働による心身不調など、副業容認によるリスクは労働者本人だけではなく企業にも関わってくるものが多々あるのです。このようなリスクマネジメントの観点からも、労働者がどのような手続きを踏み、どのようなルールを守ればよいのかを、雇用者側がきちんと定めておくことが重要です。
副業で重要なのは「労働時間管理」
副業を容認する上で、おそらく1番重要かつ事務負担になるのが、労働時間管理です。改めて言うまでもありませんが、労働時間は原則、1日の上限は8時間、週の上限は40時間とされ、それを超えて労働者を働かせる場合には、「36協定の締結・届出」と「割増賃金の支払い」が必要です。労働者の行う副業が、複数社で雇用契約を結ぶタイプの場合、この上限時間は、複数社で通算して考える必要があります。
例えば、「A社で1日4時間」、「B社で1日5時間」の所定労働時間で働いている労働者がいたとします。各社で見れば、どちらも1日8時間以下の労働時間のため割増賃金の支払いが不要ですが、2社での労働時間を足すと1日9時間です。この場合、1時間分は割増賃金の支払いが必要になるのです。この1時間の割増賃金が支払われない場合、これは未払賃金と同じです。なお、この1時間分の割増賃金は、その労働者と後に雇用契約を結んだ企業が支払います。
企業からすれば「労働者がどこで何時間働いているのか」がわからないと、この計算ができません。だからこそ「副業を自由におこなってよい」と手放しで容認することが危険なのです。労働者には、必要な情報を正しく届け出てもらう必要があります。
また、先ほどから「雇用契約」という言葉を出しているように、労働時間通算の対象になるのは複数社で労働者として働いている、つまり複数社で労働基準法(以下、労基法)の適用を受けている場合です。フリーランスや副業で起業した場合など、労基法の適用を受けない働き方による副業では、労働時間通算のルールも適用されません。
とはいえ、どのようなタイプの副業でも、長時間労働が発生し業務に支障をきたすことは避けたいものです。秘密保持の観点からも、すべてのタイプの副業で届出だけはしてもらい、労働者の副業の状況を把握しておくべきでしょう。
副業の手続きのために「就業規則」と「届出フォーマット」を定める
企業として副業を認める場合には、就業規則にルールを定めます。その中には、「副業は届出制にすること」や「労働者の届け出た内容に基づいて手続きを行うこと」を定めることを推奨します。また、原則は容認するとしても、例外的に副業を禁止・制限できる条件を設けることも可能です。裁判例やガイドラインでは、以下の場合に副業を制限できると解説されています。(1)労務提供上の支障がある場合
(2)業務上の秘密が漏洩する場合
(3)競業により自社の利益が害される場合
(4)自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
また、労働者には以下の内容を届け出てもらいましょう。届出用のフォーマットを作成しておくと、情報を漏れなく提供してもらえます。
●副業先で従事する業務内容
●労働時間通算の対象となるか否か(他社との雇用契約の有無)
●副業先との労働契約の締結日、期間
●副業先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
●副業先での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
●副業先における実労働時間の報告の方法
●これらの事項について確認を行う頻度
これらの情報は変わることもあるので、定期的に確認します。変更の都度、事業年度が変わるタイミング、36協定更新のタイミングなど、どのタイミングで届け出をし直してもらうかは定めておきましょう。
今後、副業は更に広まっていき、副業を禁止にしていることで優秀な人材の確保に影響してくることも考えられます。今回はリスクばかりを解説してしまいましたが、労働者の知見経験の蓄積、優秀な人材の定着や確保など、メリットも大きいのが副業です。労使どちらのリスクも減らせるような運用ルールを検討しておきましょう。
- 1