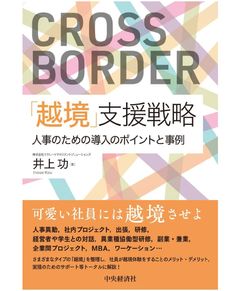成熟しすぎた日本企業が陥った「刺激的な環境」の消滅という落とし穴
最近、多種多様なベンダーさんから「他社留学」や「他社との人材交流」のご提案をいただきます。ご提案は研修会社からだけではありません。人材紹介会社や人材系ベンチャー企業、コンサルティング会社、さらには大手銀行の新規事業部門の方からもご連絡をいただきました。少し前までは、企業ニーズよりもサービスが先行している印象が強く、ご提案をいただいてもあまり乗り気にはなれませんでした。人材育成を目的として一定期間、ベンチャー企業や異業種などの他社へ人材を出向または派遣する「他社留学」は面白いコンセプトではあるものの、実際にやった結果、どんな効果やメリットが享受できるのかはまだまだ不明瞭だったからです。個人的にはやってみたいと思う気持ちがありつつも、効果がわからないものに対して社内決裁が下りるわけもなく、断念してきました。
しかし、風向きが大きく変わろうとしています。「他社留学」や「留職」の事例が少しずつ増えたのと同時に、ユーザーである企業側のニーズも高まってきたのです。
その背景には「日本企業の成熟」があります。東証一部上場で売上高TOP10にランクインしている企業は、どこも古い歴史があります。創業年数が一番若いソフトバンクでさえ、もうすぐ40年を迎えます。また、日本の大企業の多くは戦後の高度成長期に発展した企業です。
高度成長期から半世紀が過ぎようとするいま、日本企業は全体的に「超成熟期」を迎えているのです。超成熟期に入った企業の内部には、完成した仕組みしか存在しません。かつての黎明期やベンチャー企業のような「不確実性が高く刺激のある環境」は存在しないのです。
その一方で、世の中は激しく変化しています。多くの企業ではデジタル化やシェアリングエコノミーの発達などにより、事業戦略を変える必要に迫られています。しかし社内に目を向けてみると、不変的な環境で安定的に働く社員しかいません。そういった環境下で、少しでも社員の視野を広げるような刺激を与えようと「他社留学」が流行りはじめているというわけです。