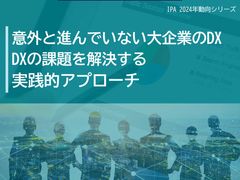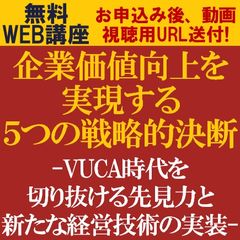最終話となる今回は、手前みそではありますが、私自身の「インドネシアでの挑戦」を書いてみたいと思います。少しでもインドネシアで活動されている皆さんのお役に立てればと思い、できる限り赤裸々に記しました。どうぞお時間のある時にご笑覧ください。
※本コラムは、来月から【日本流グローバル化への挑戦】にテーマを衣替えしてお届けいたします。

淡々とした日常に不安とストレスを抱えていた
私は2005年に株式会社エイムソウルを立ち上げた。現在、日本・インドネシアで300社強のお客様に、社内外のコンサル・インストラクター約40名で人事関連のサポートを実施している。さまざまな問題や新たな挑戦で試練が続く日々だが、充足感はとても高い。しかし私がインドネシアに渡る前の数年間、恥ずかしながらモチベーションが上がらない時期があった。本筋から外れるので詳しくは書かないが、その時の私はある課題を解決できず、日常に疲弊しており、経営者として最低限の業務をこなしながら、日々淡々と過ごしていた。自分自身が変わらなければならないという意識を持ちながらも、なかなか解決の糸口を見出せなかった。
大前研一氏はこう述べている。「自分を変えるのは3つしか方法がない。1番目は時間配分を変える。2番目は住む場所を変える。3番目は付き合う人を変えること。」と。しかし、会社を経営している身として、どれも実行に移すことは難しく、時間だけがいたずらに過ぎていっていた。
当時の私は英語がほとんどできないこともあって、「外国」に対して興味がないどころか、むしろ「拒否」をしているタイプだった。そんなある日、家内から広尾にある「ニュー山王ホテル」という在日米軍施設で開催される“Sunday Brunch”に誘われた。これは元米軍の方々と一緒に会話をしながら食事をする、というイベントだ。実はこの時、少しも興味がわかなかったのだが、家内の強い押しがあって私は渋々出かけた。
会場で、イベントをオーガナイズしている元軍人の“Rick”という人に出会った。英語が苦手な私と、ほとんど日本語を話せないRickだが、不思議と意気投合し、イベントが終わった後も、バーで長時間話し続けた。そこで彼にこんなことを言われた。
「The most importance of human communication is “Empathy”. Takashi already has it, so you can communicate all over the world’s people. (人の会話の中で最も大事なのは、“共感する力”だ。隆司はすでにそれを持っているから、世界中の人と会話ができる。)How about expanding your HR consulting for globally? (人事の仕事を、もっとグローバルに広げてみてはどうだ?)」
自分の中の扉が開かれた気がした。この瞬間私は、淡々とした日常を打破するために、海外へ出ようと決心した。

2014年7月にジャカルタに渡る
私は、いったん決めてしまえば何でもすぐ行動に移す性格だ。社内のメンバーに、エイムソウルの海外展開を自ら行うと宣言し、わがままを受け入れてもらった。数ヵ所の海外視察を経て、移住先はインドネシアに決定。当時、経済成長著しいインドネシアだったが、成長が鈍化した後は、人が採れない、他社に引き抜かれた、社内に元気がない、といった「人と組織の課題」がどんどん生まれてくると考えた。インドネシア語はもちろん、英語すらろくに話せない自分だったが、Rickの言葉を胸に、エイや!と飛び込んだ。インドネシアに来てすぐ、部下が突然退職する、という苦い経験もあったが(第5話参照)、日本で10年以上、人事コンサルの会社を経営していたという、当時の私の経験や肩書に、関心を寄せてくれる人は多かった。徐々に仕事はスムーズに回り始め、「海外でも自分の存在価値を発揮できるかも」と、自信もついてきた。しかしこれはある種の勘違いだった。私という人間は、トラブルに見舞われないと気づかないのだ。

新卒社員のように叱られる40歳
インドネシアに来て1年ほど経った時、ある会社から採用関連のコンサルをご依頼いただいた。長期にわたるプロジェクトでそれまでの中で最も難易度が高かったが、日本では何度も経験のあることなので、「大丈夫だろう」と高をくくって引き受けた。しかし議論ポイントが複雑で、言葉や文化の壁にぶつかった。そして、インドネシアの採用事情も理解が浅いまま、前提条件を間違えた示唆を出した。さらには、自ら率いたインドネシア人のチームさえうまくまとめられず、結果的にお客様をがっかりさせてしまった。新しい環境に十分に適応しようとせず、「自分の知っている日本流のやり方」で進めてしまったため、当然の結果と言えるだろう。
当時40歳を過ぎていたが、お客様から新入社員にされるような指摘を受け、恥ずかしく情けない気持ちを何度も味わった。そこで私は、「兎にも角にも、まずはインドネシアを知らないといけない」と思い、200名以上の日本人・インドネシア人にアンケートやインタビューを実施した。人々がどんなことを感じ、何に困っているかの声を集め、ディスカッションを重ねて自分なりの解決策を編み出していったのだ(第7話参照)。この頃から、インドネシアへ来た当初の「虚勢」は鳴りをひそめ、少しずつ本物の「自信」がつき、お客様の前に立って堂々と課題解決の議論をできるようになった。