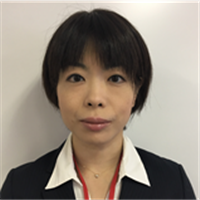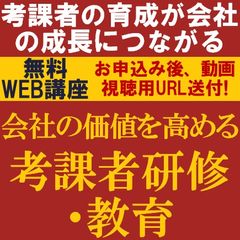「チームビルディング」と「自己開示」に好影響が生まれる“ライフストーリーテリング”
ある日、上司から「ALIVEへの参加が決まったから、どのテーマが良いか希望を出して」と言われたのです。私にとっては突然の話であり、ALIVEとは何か、そもそもテーマとは何なのかと大混乱に陥った。とりあえずGoogleで検索してみると、どうやらリーダーシップを養う研修のようだ。「あー、その手の研修ね。これまでにもマネジメントやリーダーシップの研修は何度も受けているし、演習でも大体こう答えるのが正解だよねってパターンも分かっているし、参加するの面倒くさいなぁ」
それが私のALIVEへの第一印象。この時はまだ「今まで受けてきた研修と同じ様な普通の研修」としか思っていなかった。
そして迎えた研修の当日。ALIVEプロジェクトの説明を聞いて、その印象が変わり始める。今日初めて知り合ったバックグラウンドの全然違う人たちとチームを組んで、4回のSessionでプレゼンを完成させないといけないらしい。不安を感じつつ、チームビルディングのためのワーク「ライフストーリーテリング」の時間に突入した。
「ライフストーリーテリング」とは何か。「心に浮かんだ子供の頃の出来事とその時の自分の感情を話す。チームのメンバーはその話を聞いて感じたことを話す」という対話を1人ずつ順に行っていくものである。
ALIVEの各Sessionの中で重要になってくる「自己開示」と「フィードバック」の第一歩だ。もちろん、この時点で「自己開示」なんてことは全く意識していなかった。ただ、後から考えるとSession1の始めにチームで「ライフストーリーテリング」をすることはとても重要なことだったと感じる。その理由は2つ。
1つ目は、最初に目的として告げられている通り、「チームビルディング」の効果。お互いの子供の頃の話をすることで、自然とメンバーに対する親近感が湧いていく。日頃、自分の子供の頃の出来事を話すのは親しい相手が多いからだろうか。共感を覚える話、第一印象と違うなと感じる様な意外性のある話、メンバーそれぞれの感想も様々だが、一気にチームが親しい雰囲気になった。
そして、2つ目は、参加当初は意識していなかった「自己開示をすること」への抵抗感の軽減だ。子供の頃の印象に残っている出来事とその時の感情を話すというのは、過去の話ではあるが「自己開示」と言えるだろう。後々のSessionで行う「Proud&Sorry」の様な自己開示は、最近の自分を開示しなければならない。
これは意外に難しいことで、いきなり話せと言われても抵抗を感じる人も多いだろう。だが、子供の頃の話であれば、今の時点と遠い自分なので、過去の話として比較的抵抗感なく話すことができる。また、メンバーからのフィードバックも自分にとって耳の痛い話にはなりにくいため、受け入れやすい。
ここで過去の自分を開示することとフィードバックを受けることを経験しておくことで、チームメンバーに対する心理的安全性が高まり、この後のSessionでの自己開示への抵抗感が軽減されたと感じるのだ。
このワークの後、答申先の話を聞き、Session2までどう過ごすかをチームで決めたのだが、Session2でいきなりプレゼンを行うこともあり、それまでに何度かチームで打ち合わせを行うことになった。Sessionの日だけ研修に参加すれば良いと思っていたが、それでは全然対応出来そうにない。これから大変そうだと不安を感じながら、ALIVEの3ヵ月が始まった。
解決策を提案する前に、課題をどう捉えたかを言語化する狙いとは
ession2では「取り組むテーマに対して、解決の肝となる本質的な課題をどう捉えたか?その解決の方向性は?」というお題に対してのプレゼンを行う。通常の業務で行うプレゼンの場合、「解決策の提案」にあたるプレゼンを行うケースが多い。このSessionでは、「解決策を提案する前に課題をどう捉えたか」を言語化してプレゼンを行う。そのステップを踏むことで、テーマに対する理解を深め、課題を深掘りし、提案の質を上げる狙いがある。Session1から2までの間、何度かチームで打ち合わせを行い、その間にも各自で資料を作り、自分たちなりに真剣に取り組んでプレゼンを行った。しかし、プレゼンのフィードバックで受けたのは「根拠が薄い」という指摘。確かに私たちは、答申先から聞いた話やインターネットで調べた話をベースにしており、フィールドワークはほとんど行っていなかった。普通の研修ならそれで充分だったかもしれない。しかし、答申先は日々リアルな社会課題と向き合っている。実際の業務であれば、きっと事前にもっと様々なリサーチを行って根拠を明確にするだろう。
やはり研修だという甘えがあったのかもしれない。ただ、答申先の話を聞くうちに、「答申先の課題を本当に解決できるような提案がしたい」という強い思いが自然に湧いてきた。ALIVEに対するスイッチが入ったのはこの頃だった。
※後編に続く
- 1