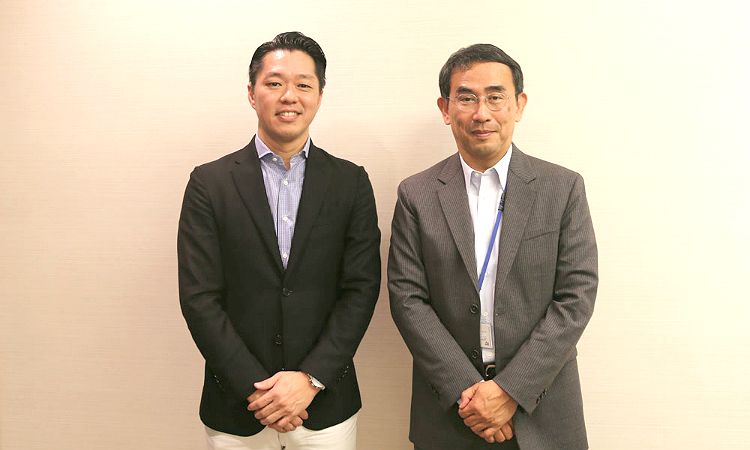
人事ビジネスパートナーとは
稲垣: 中島さんは、「これからの人事部門は、日本だけにとどまらず、高度な『専門性』と自社の事業に対する『深い理解』、そして、その上に立った『論理的な実践』が求められる」と仰っています。これは“人事部が経営者にとっての「右腕」となり、意思決定に影響を与えるパートナーにならなければいけない”という、ミシガン大学のウーリック教授が提唱されている「人事ビジネスパートナー」という役割だと思います。まずは、なぜこの言葉のような見解に至ったのか、中島さんのご経験などから教えていただけますでしょうか。
中島: 私は大学を卒業して富士通に入社し、人事を担当していました。富士通はグローバル化に踏み切っていたのですが、当時のグローバルというのは、企業を買収しても現地企業とは距離を置き、ポートフォリオ管理だけして経営は任せる、という形だったので、基本的に日本にグローバル本社は要りませんでした。一言でいうと、統治をしているのではなく、「仲良しクラブ」みたいな感じです。
変化の契機となったのは、ICLの買収でした(富士通は1990年に英ICLを1,890億円にて株式の80%を取得し、電算機分野で世界2位となり、IBMを追撃する体制を整えた。当時、大変話題となった大型買収)。ICL自体も非常に伝統のある会社で、オペレーションは整備されているし、ガバナンスの手法として、報酬委員会や指名委員会という仕組みも持っていました。
しかし残念ながら、日本サイドでは企業統治のレベルが全然追いついておらず、ICLをマネジメントするノウハウがほぼないに等しい状態でした。当時、MBAを終えて帰国してきたばかりの私には、報酬の仕組みやストックを使ったインセンティブなど、ある程度、欧米企業の人事管理の知識があったのですが、経験も浅かったため、経営のパートナーどころか意見すら出せませんでした。
稲垣: バブル期でお金があったから買収したのはいいものの、グローバル人事視点で経営するノウハウは持ち合わせていなかったんですね。
中島: そうですね。グローバルで人的資産を運用する、という発想はまずなかったですね。
稲垣: それにしても、日本を代表する大企業の富士通がそういう状況だったんですね。そんな時代を経て、現在、日本の人事レベルは世界と比較して上がってきているのでしょうか。
中島: 2015年にコーポレートガバナンスコードが施行されて、指名委員会・報酬委員会を設置する企業も増えましたが、まだまだ十分ではありません。日本はもっとマネジメントを勉強しなければなりません。マネジメントはシンプルです。PDCAサイクルを回す、これに尽きます。そしてPDCAサイクルを回すためのツールは、何と言っても数字です。アカウンティングやファイナンスを、きちんと理解している人事がどれだけいるのでしょうか。
そもそも日本人は、「お金儲けは悪いこと」というデフォルトの考え方が強い。経営には必ずお金が必要で、数字を理解したPDCAサイクルで回さなければならないのに、美学や哲学が先行してしまっているのです。すでにその段階で、グローバルの中で立ち遅れていると言えます。























