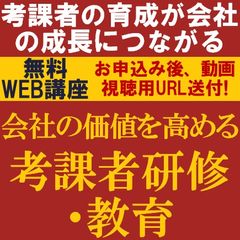能力主義から成果主義へ~日本の評価制度の変遷
我が国にとって「評価制度」を志向し始めたのは1976年の能力主義に遡ることになるだろう。90年代に入ると「成果主義」にとって代わる。この背景にあるのは「実績・評価に基づいた公正・公平な人事処遇を!」ということなのだろう。実際、このような企業に勤めたいと希望する若年層の割合は依然として高い。ただ、適正な評価制度の下で…という前提があることは注意しておきたい。成果主義が台頭した時を考えてみよう。勤続年数や年齢に応じた年功的賃金から、評価に基づく賃金形態へ移行する際は、これに賛同する社員が多数を占めたが、実際に評価がなされ蓋が開かれると、社員の声はたちまち不満へと変わったことが確認されている。この違いは何なのか。これには様々な要因が絡んでいが、大きな理由は2つあると思われる。と同時に、これは評価制度が機能不全に陥っている会社の要因とも一致する。
一つは、評価云々の前に賃金原資が決まっている以上、これをどう分配するかという点に重きが置かれる点だ。つまり、部課内でS評価は1人、A評価は3人…というように予め評価の枠が決められ、この割合ありきで評価せざるを得ない。言わば公正・公平に評価するというのは大義なのである。酷い会社になると、考課者である上司は部下に恨まれたくないため、1年ごとにS・A・B・C・Dを社員ごとに順繰りにまわして付ける場合もある。
二つ目は、評価基準が《人》に準拠しており、《職務(Job)》に対応していない。つまり、なぜこの職務が存在し、どのような状態になったらその仕事が一人で担えると判断されるかという目標達成水準、そして、その職務内容や責任・権限の範囲、必要な知識や資格、経験年数等が詳細に明記された職務記述書(Job Description)が基にされていない。
加えて、情意考課も曲者である。必ずといってよいほど評価にみられる「責任感がある」という内容がそれだ。「責任感」という評価基軸は、極めて抽象的であり人によって捉え方に差がある。ある人の基準では責任感を持って職にあたっていると判断することも、別の人の基準では責任感を持っていないと判断されるからだ。判断基準が明確でないために考課エラーが生じる要因でもある。結局のところ、「賃金をどう分配するか」というための評価に終始している。だから社員は自分の評価だけを気にして協同が希薄になり、職場は荒廃化するのである。
評価と賃金を結びつける前にすべきこと
評価制度を機能させるためには、職務記述書が土台にあり、これに対応した作業手順書が存在し、あわせて教育訓練制度を設けなければならない。言わば、評価と教育は両輪関係にあり、評価だけしても前進することはない。企業にとって非常に手間のかかる不断の運用を覚悟する必要がある。人が人を評価することは実に大変な労力を要するのだ。筆者は、社内を活性化するための施策は評価制度だけではないと考えている。その前にすべきことがたくさんあるのだ。まずは職務を洗い出し、作業マニュアルとコンピテンシー(成果を出すための具体的行動)の整備である。その上で求める職務が達成できるよう能力開発(教育訓練制度)をあわせて実施する必要がある。これらが十分に醸成されるまで評価を賃金に結びつけるべきではない。この工程を蔑ろにし、手っ取り早く社員間に賃金差をつけようとするから社員の不満が噴出し、組織活性どころか荒廃してしまう。賃金差による刺激で社員の競争力を煽り社内活性化に繋げようとする施策は鼻っ面にニンジンをぶら下げて煽るだけの脅しの制度で、長くは続かない。大切なのは各社員を組織の戦力にする社員教育と、これに対応した職務体系の整備である。
SRC・総合労務センター、株式会社エンブレス 特定社会保険労務士 佐藤正欣