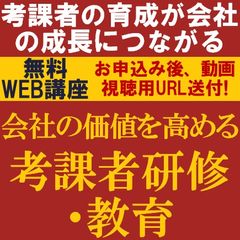「労働法」誕生までの歴史
労働法の歴史をたどってみよう。それは、ヨーロッパで起こった第一次産業革命による工業化社会の到来が発端である。それ以前の農耕社会では、領主と農民は身分差のある関係で、その自由は大きく制約されていた。一方で、領主は農民を庇護する責務を負っていた。つまり、その関係は「支配はするが、庇護もする」という相互扶助的なものだった。親方が職人・徒弟を支配した徒弟制度も同様であった。しかし産業革命以後、農民は土地から離れ、職人は機械に仕事を追われ、いずれも工場に雇われて賃金を得る立場になるしかなくなり、効率性を追求した分業システムの下、機械のごとく単純業務に従事する日々を過ごすことになった。ここにいたって初めて、「雇用契約」という概念が生まれた。資本家たる経営者と労働者は、形式的には自由で対等な立場に立ったように見えたが、実は契約を通じて身分関係が設定されていた。平たく言えば、経営者はその資本力にものをいわせて、労働者を庇護することなく支配を強化してしまったのだ。
そこで、この雇用契約に従前の「庇護」の要素を取り入れようとしたのが、ドイツを中心にヨーロッパで展開された「従属労働論」である。企業に属して働く労働者のために法が介入すべきとする従属労働論は、その後「労働法」の基本原理となり、日本においてもその精神は営々と存在している。
日本型雇用社会と「労働法」
もっとも、戦後の日本では労働争議が頻発した一定の時期を除き、「労働法」の存在感は大きくはなかった。なぜなら、多くの経営者は、あたかも中世の領主や親方のごとく、労働者にロイヤリティを求める一方、彼らの生活の安定を保証もしていたからである。この日本独特の雇用システムが労働法の出番を抑制していたともいえよう。ただし、その対象は正規社員に限られ、非正規社員にはこうした庇護はおよんでいなかった。非正規雇用にスポットライトがあたる時代に立ち至り、政府は労働法上の庇護を労働者全体におよぼそうとしてきたのである。
「働き方改革」のその先
現在、労働法は「働き方改革」のブームにも乗って、極めてリベラルな対応を企業に求めている。しかし、それは長続きしないかもしれない。すでに、生産現場ではドラスティックで本質的な変化が起きているからだ。第四次産業革命といわれる「パラダイム転換」は、雇用が創出されるが、同時に雇用の喪失を引き起こすこともある。工場の無人化は広がっているし、ロボットやAIの活用領域の拡大は、オフィスや現場作業の省力化を劇的に進めるだろう。不要となる労働は、単純作業に従事する非正規社員にとどまらず、労働生産性の低い正規社員にもおよぶことになる。
だからといって、人間がおこなう仕事がなくなるわけではない。AIやロボットを活用するのに必要なIT人材の不足は深刻であるし、それによって代替できない能力もプレゼンスを高める。とりわけ重要性を増してくるのが、新たな発想で価値を生み出す創造力を持った人材だ。しかしながら、彼らが旧態依然たる日本企業の枠組に納まる可能性は低く、企業に雇用されるという選択を想定していない可能性も高い。
そうすると、技術的特異点といわれるシンギュラリティの時期に近づけば近づくほど、時間的・場所的にも「自由な働き方社会」が到来する。組織上の上司と部下の関係性はなくなり、自らの仕事が自己実現に直結する社会だ。そこは、自由ではあるが、手厚い庇護を失う社会でもある。庇護する企業もなく、これまでの労働法による庇護もなくなる。
このような雇用社会の到来を見越せば、現在の働き方改革が過去の遺物になる日もそう遠くではなかろう。また、自助していく職業人が自立していけるような政策を立てることが政府の公助となり、その公助は個人の自助力を高める方向にシフトしていくだろう。それには、社会保障の抜本的改革やセーフティネットの再構築も含まれることはいうまでもない。現在、各企業に求められている「働き方改革」を冷静な目で捉えておくことも必要なのかもしれない。
大曲義典
株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ
社会保険労務士・CFP