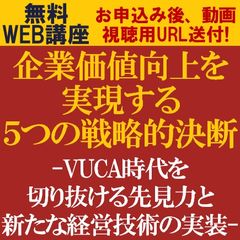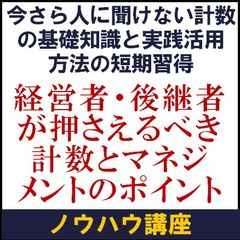従業員の秘密保持義務とは?
従業員は、業務を行う上での営業秘密を守るべき義務を負っている。営業秘密とは何か?
不正競争防止法では「『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定められている。
つまり、①有用性 ②非公知性 ③秘密管理性 の3つの要件により、営業秘密は定義される。
①有用性
秘密として保護することにより、ビジネス上の価値がある情報(営業上あるいは、技術的な情報)であることが必要である。
価値があるとは、その情報を秘密とすることにより、顧客・マーケットの保護や拡大、経営活動の効率性、商品開発等の正当な利益が得られることを指す。具体的には、顧客情報、マーケティング情報、納入価格、技術情報、実験内容やデータ、販売マニュアル、製造マニュアルなどが考えられる。
ネガティブ・インフォメーション、例えば失敗した実験データなども該当することに注意しなければならない。
もちろん、犯罪の手口や脱税情報などの公序良俗に反する内容の情報、反社会的な情報は除外される。
②非公知性
その情報が「公然と知られていない」ことが必要である。つまり、一般的に知られた状態になっていないこと、あるいは誰でも容易に知ることができない情報であること。
企業内において、その情報を知っている人数の多少は問題とならない。多くの者が知っている情報でも、それを知っている者に秘密保持義務が課されている場合は、営業秘密となりうる。
③秘密管理性
その情報が秘密として管理されている必要がある。これは最も重要な要件である。例えば特許等のように一般に公示されておらず、「客観的に」秘密情報として管理されている事が必要である。
具体的には、秘密情報として明確化されており、アクセス制限など秘密情報として適切な管理措置が取られていなければならない。
裁判例によれば、(1)当該情報にアクセスできる者を制限するとともに、(2)同情報 にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できることが必要とされている。
(1)から考えると、例えば社内書類等に『秘』印を押すなどしていても、それが実質的に誰でも見ることが出来る状態であれば、秘密情報とはなり得ない。
(2)から考えると、例えばその情報に触れる事の出来る従業員が限定されていたとしても、その情報が秘密情報であると、従業員が認識できないものであれば、秘密情報とはなり得ない、と考えることが出来る。
秘密保持義務の実務上の問題
①秘密保持義務の内容と明示実務上では従業員との間に、「秘密保持誓約書」等を交わすことが多いだろう。誓約書を交わす上では、対象となる秘密情報が先ほどの3つの要件に合致しているかどうか?を確認しておく必要がある。
「営業上の秘密を保持しなければならない」等の文言だけで、その秘密が何なのか?明確でない場合は、秘密情報となり得ない可能性がある。出来れば、具体的に秘密情報がどのような情報を指すのか、明確にしておくべきである。
また、就業規則で包括的な秘密保持義務を課し、更に具体的には秘密保持義務規程などを作成しておくことが望ましい。「秘密保持誓約書」の提出義務や、それを拒んだ場合の罰則なども織り込むことにより、「秘密保持誓約書」の提出義務の根拠となる。
②秘密保持誓約書の提出時期
入社時、退職時、特定部署への異動時、あるいはプロジェクト参加時など、それぞれの場面において、対象となる秘密情報を明確にするため、その都度、提出してもらう事がベターであろう。少なくとも、入社時および退職時には、提出してもらうべきであろう。
実務上では、従業員に秘密情報保持の重要性について、十分に認識してもらうことが重要である。個人情報漏えい事件でも、意図的な漏えいよりも過失による漏えいが多い。例えば、SNSなどで出先での写真画像を投稿した際に、たまたま自身のノートパソコンや書類も写っており、そこから秘密情報が漏えいした・・等の事例もある。
また、今年1月に施行された改正不正競争防止法では、罰則の強化や営業秘密侵害罪の非親告化、営業秘密の転得者までの処罰拡大、営業秘密侵害の未遂行為への処罰拡大等が新たに定められた。
(詳細はこちら)
これらにより企業側においても、秘密保持の重要性を改めて認識する必要がある。例えば、転職者から前職での秘密情報を取得し、その情報を業務上利用してしまう場合など、悪意無く秘密情報を不正利用してしまうケースも考えられる。
これらを踏まえて、自社の秘密情報の取扱、管理方法について、再考する機会を是非設けてもらいたい。
オフィス・ライフワークコンサルティング
社会保険労務士・CDA 飯塚篤司