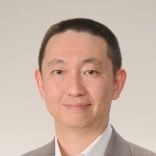雷鳴の轟く中、一人の男が生まれた。彼は維新の時代において回天の志士となり、しかしながら志を成し遂げることなく、この世を去る。
幕末の尊王攘夷の流れを作ったといってもいいこの男は、山形県(庄内藩)の酒屋の長男として生を受けた。
清河八郎である。
幕末の尊王攘夷の流れを作ったといってもいいこの男は、山形県(庄内藩)の酒屋の長男として生を受けた。
清河八郎である。
一般に清河は過激な攘夷論者として描かれている。しかし彼は本当に単なる攘夷論者であったのか。
彼が四歳のころ、天保の飢饉に見舞われ、尋常ではない日照りによる水不足があったかと思えば、最上川の氾濫は村の五分の一を押し流したという。翌年には異常なまでの冷夏、秋にもかかわらずの大雪など、六年間にもわたる異常気象の中、庄内藩は存亡の危機にあった。
本来民を守るべき藩は備蓄米を取り上げ、民を見放した。そんな中、藩の預かり前を持つ清河の家は、民を救うため十五俵の米を村に寄付したのである。
にもかかわらず、盗賊が清河の家を襲い、十一俵からの米を盗み出す。賊は見つからず藩は威信を守るため、清河の家に責任をかぶせようとした。清河の家から家財没収、一家追放、当主を斬首しようとしたのである。
しかし八郎は、盗賊が米を盗む場面を見ていた。八郎の証言により、盗賊はつかまり、家は救われたものの、村人から八郎は憎まれた。
本来は、民を救わない藩こそが、悪である。八郎の家は「善行」をした。しかし、天変地異を起こした自然もそして藩も、全てが敵であったのである。
「上は信ずるに値しないものである(観)。信用したところで(因)、損をするのは自分である(果)。一人で生きる力を付けなければならない(心得モデル)」という行動理論を生み出す原体験がここにあるのではないか。
また彼は幼いころから孔子の教えを学んだ。「経世済民」を学ぶと同時に、「男と生まれたには、事をなさねばならない」、「文事あるものは必ず武備あり」など、彼は民のために己を磨く思想を自らの中に醸成させていった。
つまり「自分は民を救うべき人物である(観)。故に、文武を磨き、力を蓄えることが(因)、その使命を果たすことになる(果)。己を磨け(心得モデル)」という行動理論も生み出され、「己を磨く」ことにすべてを集約させていったのであろう。
事実彼は、学問においても剣の道においても超一流の域に達している。
江戸の学問所に入所したものの、あまりのレベルの低さに失望し、数日で退塾したこともあるという。
彼が四歳のころ、天保の飢饉に見舞われ、尋常ではない日照りによる水不足があったかと思えば、最上川の氾濫は村の五分の一を押し流したという。翌年には異常なまでの冷夏、秋にもかかわらずの大雪など、六年間にもわたる異常気象の中、庄内藩は存亡の危機にあった。
本来民を守るべき藩は備蓄米を取り上げ、民を見放した。そんな中、藩の預かり前を持つ清河の家は、民を救うため十五俵の米を村に寄付したのである。
にもかかわらず、盗賊が清河の家を襲い、十一俵からの米を盗み出す。賊は見つからず藩は威信を守るため、清河の家に責任をかぶせようとした。清河の家から家財没収、一家追放、当主を斬首しようとしたのである。
しかし八郎は、盗賊が米を盗む場面を見ていた。八郎の証言により、盗賊はつかまり、家は救われたものの、村人から八郎は憎まれた。
本来は、民を救わない藩こそが、悪である。八郎の家は「善行」をした。しかし、天変地異を起こした自然もそして藩も、全てが敵であったのである。
「上は信ずるに値しないものである(観)。信用したところで(因)、損をするのは自分である(果)。一人で生きる力を付けなければならない(心得モデル)」という行動理論を生み出す原体験がここにあるのではないか。
また彼は幼いころから孔子の教えを学んだ。「経世済民」を学ぶと同時に、「男と生まれたには、事をなさねばならない」、「文事あるものは必ず武備あり」など、彼は民のために己を磨く思想を自らの中に醸成させていった。
つまり「自分は民を救うべき人物である(観)。故に、文武を磨き、力を蓄えることが(因)、その使命を果たすことになる(果)。己を磨け(心得モデル)」という行動理論も生み出され、「己を磨く」ことにすべてを集約させていったのであろう。
事実彼は、学問においても剣の道においても超一流の域に達している。
江戸の学問所に入所したものの、あまりのレベルの低さに失望し、数日で退塾したこともあるという。
時は幕末である。欧米は武力で日本に開国を迫り、属国化しようと画策している。本来国政を担うべき江戸幕府はその統制力を半ば失いつつあり、朝廷も国を動かすだけの真の力を持っているわけではない。
「優れた自分が日本の民を救わなければならない」
その使命感が彼を突き動かした。ただ悲しいことに彼は武家の出ではない。時代を動かす後ろ盾を持っていなかった。策をめぐらすしかない。
そのため彼は、八方に方便を使い、力をかき集め、無理に無理を重ねる以外手がなかったのである。
清河は時の大老・井伊直弼が、水戸浪士に暗殺されたのとほぼ時を同じくして「虎尾の会」を組織した。外国人を日本から追い払い、天皇を中心に日本を一つにまとめるためには、虎の尾を含むことも恐れない、の意である。
大老の暗殺により、威信が地に落ちた幕府に見切りを付け、自らの力で強い日本を創り、民を救う、その策を考え、動き始めたのである。
しかし同年十二月-虎尾の会の数名がアメリカ人通訳を暗殺したことにより、幕府に目を付けられ、さらに「清河塾」は幕府の手先を無礼斬りしてしまう。清河は追われる身となり、「虎尾の会」は分散。
にもかかわらず逃亡中の彼は、ひそかに上洛して己が意見を天皇に上奏し、薩摩藩の同志を集い勤皇のもとに挙兵する策を押し立てる。
この企ては池田屋の変によって、失敗に終わる。彼は新たな策を創りださなければならなかった。
江戸に戻った一八六二年、今度は幕府の松平春嶽に対し「急務三策」という建白書を提出する。国を救わなければならない時代に、力ある者を広く集め事に当たるべきである、という内容であった。
幕府は、朝廷から「攘夷」を求められていたものの、策がなく困り果てていた。そこに「急務三策」である。暴走し始めている浪士たちを集めて江戸から追い払い、かつ攘夷の大義名分も立つ。
一八六三年、「浪士組」が成り、清河は中心人物として上洛した。
京都に入るやいなや彼は、「われらの使命は朝廷を擁立し、攘夷を断行することである。幕府のための組織ではない」と尊皇攘夷論を打ち出した。各人の血判を集め京都御所へ提出、受理され、浪士組は勅諚を得る。
折も折、江戸では生麦事件に関するイギリスからの強硬な談判に困り果てていた。
清河は天皇に上奏文を出し許可を得た上で、「江戸に戻り、攘夷の先駆けをなす」旨を浪士たちに伝える。
「浪士組は攘夷のために江戸に帰る」旨の勅諚が出てしまっている以上、幕府はこれに逆らうわけには行かない。しかし、一浪士の分をわきまえない行為に対し、黙っているわけには行かなかった。清河は幕府にとってすでに第一級の危険人物であった。
清河が知人を訪ねた帰り道、佐々木只三郎が丁寧に陣笠を取り、声を掛けてきたため、応じて陣笠に手をかけた刹那、斬られるのである。
「近世日本国民史」の薯者徳富蘇峰は、清河八郎をもって「維新回天偉業の魁」と称している。
「魁」を辞書で引くと、
1かしら。頭領。首領
2他に先んじること
とある。
見切りをつけた幕府を利用しようとし、実権のない朝廷をうまく動かそうとした清河は、優れた力を持ちながら後ろ盾を作れなかった。その根底にあるのは「自分以外は信ずるに足りない」という観に起因するように思えてならない。
他を信じることのできない有能な人物は、頭領ではなく「先んじること」のみで生涯を終えるのかもしれない。
「優れた自分が日本の民を救わなければならない」
その使命感が彼を突き動かした。ただ悲しいことに彼は武家の出ではない。時代を動かす後ろ盾を持っていなかった。策をめぐらすしかない。
そのため彼は、八方に方便を使い、力をかき集め、無理に無理を重ねる以外手がなかったのである。
清河は時の大老・井伊直弼が、水戸浪士に暗殺されたのとほぼ時を同じくして「虎尾の会」を組織した。外国人を日本から追い払い、天皇を中心に日本を一つにまとめるためには、虎の尾を含むことも恐れない、の意である。
大老の暗殺により、威信が地に落ちた幕府に見切りを付け、自らの力で強い日本を創り、民を救う、その策を考え、動き始めたのである。
しかし同年十二月-虎尾の会の数名がアメリカ人通訳を暗殺したことにより、幕府に目を付けられ、さらに「清河塾」は幕府の手先を無礼斬りしてしまう。清河は追われる身となり、「虎尾の会」は分散。
にもかかわらず逃亡中の彼は、ひそかに上洛して己が意見を天皇に上奏し、薩摩藩の同志を集い勤皇のもとに挙兵する策を押し立てる。
この企ては池田屋の変によって、失敗に終わる。彼は新たな策を創りださなければならなかった。
江戸に戻った一八六二年、今度は幕府の松平春嶽に対し「急務三策」という建白書を提出する。国を救わなければならない時代に、力ある者を広く集め事に当たるべきである、という内容であった。
幕府は、朝廷から「攘夷」を求められていたものの、策がなく困り果てていた。そこに「急務三策」である。暴走し始めている浪士たちを集めて江戸から追い払い、かつ攘夷の大義名分も立つ。
一八六三年、「浪士組」が成り、清河は中心人物として上洛した。
京都に入るやいなや彼は、「われらの使命は朝廷を擁立し、攘夷を断行することである。幕府のための組織ではない」と尊皇攘夷論を打ち出した。各人の血判を集め京都御所へ提出、受理され、浪士組は勅諚を得る。
折も折、江戸では生麦事件に関するイギリスからの強硬な談判に困り果てていた。
清河は天皇に上奏文を出し許可を得た上で、「江戸に戻り、攘夷の先駆けをなす」旨を浪士たちに伝える。
「浪士組は攘夷のために江戸に帰る」旨の勅諚が出てしまっている以上、幕府はこれに逆らうわけには行かない。しかし、一浪士の分をわきまえない行為に対し、黙っているわけには行かなかった。清河は幕府にとってすでに第一級の危険人物であった。
清河が知人を訪ねた帰り道、佐々木只三郎が丁寧に陣笠を取り、声を掛けてきたため、応じて陣笠に手をかけた刹那、斬られるのである。
「近世日本国民史」の薯者徳富蘇峰は、清河八郎をもって「維新回天偉業の魁」と称している。
「魁」を辞書で引くと、
1かしら。頭領。首領
2他に先んじること
とある。
見切りをつけた幕府を利用しようとし、実権のない朝廷をうまく動かそうとした清河は、優れた力を持ちながら後ろ盾を作れなかった。その根底にあるのは「自分以外は信ずるに足りない」という観に起因するように思えてならない。
他を信じることのできない有能な人物は、頭領ではなく「先んじること」のみで生涯を終えるのかもしれない。
- 1