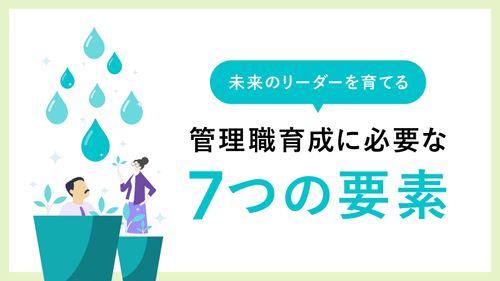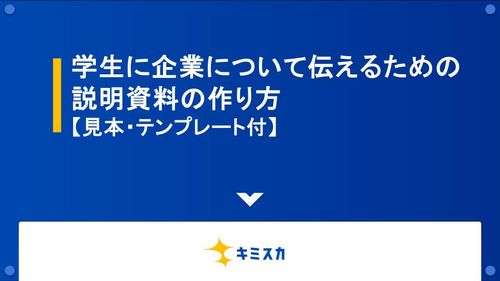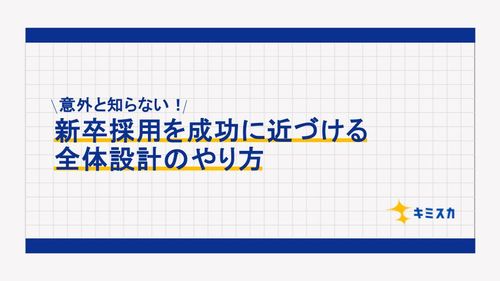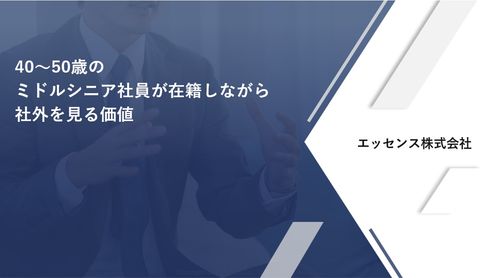日本の新卒採用・就職には様々な問題が指摘されているが、そこには当事者として、採用する企業側、就職する学生、その親、学生を送り出す大学、バックに控える官庁、就職情報会社などが関わっている。
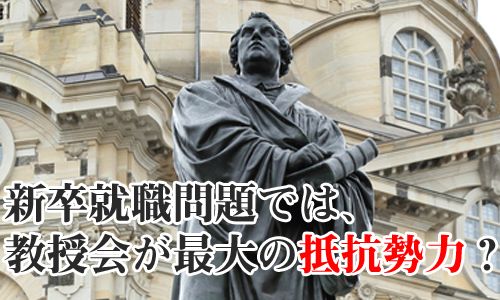
さて、日本の新卒採用・就職問題を改革するに当たって、何が一番抵抗勢力になっているかと聞かれれば、私は躊躇なく「大学の教授会」と答えるだろう。なぜか。「決められない」「保身」「他人事」がキーワードだ。
大学が「決められない」のは、新卒採用・就職問題に限ったことではない。そもそも一般の企業と違い、ほとんどの大学では、学長、学部長は教員の選挙で決められる。社長や役員を一般社員の選挙で決めるようなもので、改革で血を流し、自分たちに厳しい判断を下す人を決めるはずがないだろう。
それでも一旦学長になると、大学が抱える多くの問題を直視せざるを得ず、改革を行おうとするケースが少なくない。ところが、学長が何を言っても、教授会の反対があれば何も決められず、物事が前に進まないことが多いのだ。前・国際教養大学学長の中嶋嶺雄氏(故人)が、以前に某大学学長を務めていた時は教授会の抵抗で多くのことが決められず、ずいぶんと悔しい思いをしたと講演で話をされていたことを思い出す。中嶋氏はその思いで国際教養大学の設立に関わられ、大学の統治方法自体を改革された、志の高い本当に素晴らしい方だったと私は思う。ただ、このような学長は少なく、妥協を強いられ無力感に浸ったままの状態が多いのが現状だ。
そして、大学教授たちの「保身」。教授というのは、一旦なると降格というのはほとんどない、身分を強く保障された職業と言える。いくらつまらない授業をしても、研究成果が上がらなくとも、不祥事さえ起こさなければ首になることはほとんどない。しかも、教授という職業は社会的地位が高く、一旦やるとやめられない魅力が、今もある。
私の大学時代も、何十年も同じテキストを使って、学生に順番に読ませているだけという教授が複数いたが、単位を簡単にくれるのでかえって人気が高かった。知り合いの教授に聞くと、そういう人は今でもたくさんいますという答えだった。もちろん意識の高い、素晴らしい成果を挙げている教授はいるが、全体の割合としては多いとは言えないだろう。
大学が「決められない」のは、新卒採用・就職問題に限ったことではない。そもそも一般の企業と違い、ほとんどの大学では、学長、学部長は教員の選挙で決められる。社長や役員を一般社員の選挙で決めるようなもので、改革で血を流し、自分たちに厳しい判断を下す人を決めるはずがないだろう。
それでも一旦学長になると、大学が抱える多くの問題を直視せざるを得ず、改革を行おうとするケースが少なくない。ところが、学長が何を言っても、教授会の反対があれば何も決められず、物事が前に進まないことが多いのだ。前・国際教養大学学長の中嶋嶺雄氏(故人)が、以前に某大学学長を務めていた時は教授会の抵抗で多くのことが決められず、ずいぶんと悔しい思いをしたと講演で話をされていたことを思い出す。中嶋氏はその思いで国際教養大学の設立に関わられ、大学の統治方法自体を改革された、志の高い本当に素晴らしい方だったと私は思う。ただ、このような学長は少なく、妥協を強いられ無力感に浸ったままの状態が多いのが現状だ。
そして、大学教授たちの「保身」。教授というのは、一旦なると降格というのはほとんどない、身分を強く保障された職業と言える。いくらつまらない授業をしても、研究成果が上がらなくとも、不祥事さえ起こさなければ首になることはほとんどない。しかも、教授という職業は社会的地位が高く、一旦やるとやめられない魅力が、今もある。
私の大学時代も、何十年も同じテキストを使って、学生に順番に読ませているだけという教授が複数いたが、単位を簡単にくれるのでかえって人気が高かった。知り合いの教授に聞くと、そういう人は今でもたくさんいますという答えだった。もちろん意識の高い、素晴らしい成果を挙げている教授はいるが、全体の割合としては多いとは言えないだろう。
そういう恵まれた(?)環境を、教授たちの多くは手放したくない。教育者として学生の能力向上に貢献し、その成果によって査定されるなんて、とんでもないと思っている人が少なくないのだろう。大学の就職部、キャリアセンターの職員からは、「余計な仕事を増やさないでくれ」という教授の無言の圧力があると聞く。そうした教授たちが多数決で物事を決めるのが教授会なのである。 最後に「他人事」。学生の就職問題などは自分たちに関係ないと思っている教授は少なくない。悪いのは、採用活動を早期化し長期化させ、学業を圧迫する企業の方だというわけだ。大学の授業に出てこないと激怒し、就職活動の真っ最中でも出席を強要し、困る学生もいると聞く。
しかし、HR総合調査研究所が調査で当の学生たちに聞くと、選考時期をいかに後ろ倒しにして遅延させても、学業を頑張るかといえば8割以上がノーという回答だ。学生が勉強しないのは、日本の大学の教育システム、教授側の問題の方がはるかに大きいのではないか。そのことを棚に上げておいて、企業ばかりを非難する大学側の姿勢には、正直唖然とする。
変化のスピードが非常に速い時代、しかも日本の大学が置かれている環境を見れば、物事を迅速に決められない大学の組織形態、教授会の存在そのものが最大のリスクである。新卒採用・就職では、大学の就職部、キャリアセンターの職員は様々な問題、危機に直面し、現実的な対応、改革の必要性を認識しているが、「教授会の反対で、何も決まらない。トライしても無駄」という声を彼らから本当によく聞く。
文部科学省が求めるキャリア教育などで、教員が研究に閉じこもらず教育に注力するように注文を付けても、「大学は職業専門学校ではない」などと理屈をつけて、多くの教授は協力に積極的ではない。就職ガイダンスの要素を必修授業にすることすら、ほとんどの大学で実現していない。悪しき民主主義、大学自治のこだわりの産物である教授会という存在が、日本の新卒採用・就職問題の改革を阻んでいる。
HRプロ 代表/HR総合調査研究所 所長 寺澤康介
しかし、HR総合調査研究所が調査で当の学生たちに聞くと、選考時期をいかに後ろ倒しにして遅延させても、学業を頑張るかといえば8割以上がノーという回答だ。学生が勉強しないのは、日本の大学の教育システム、教授側の問題の方がはるかに大きいのではないか。そのことを棚に上げておいて、企業ばかりを非難する大学側の姿勢には、正直唖然とする。
変化のスピードが非常に速い時代、しかも日本の大学が置かれている環境を見れば、物事を迅速に決められない大学の組織形態、教授会の存在そのものが最大のリスクである。新卒採用・就職では、大学の就職部、キャリアセンターの職員は様々な問題、危機に直面し、現実的な対応、改革の必要性を認識しているが、「教授会の反対で、何も決まらない。トライしても無駄」という声を彼らから本当によく聞く。
文部科学省が求めるキャリア教育などで、教員が研究に閉じこもらず教育に注力するように注文を付けても、「大学は職業専門学校ではない」などと理屈をつけて、多くの教授は協力に積極的ではない。就職ガイダンスの要素を必修授業にすることすら、ほとんどの大学で実現していない。悪しき民主主義、大学自治のこだわりの産物である教授会という存在が、日本の新卒採用・就職問題の改革を阻んでいる。
HRプロ 代表/HR総合調査研究所 所長 寺澤康介